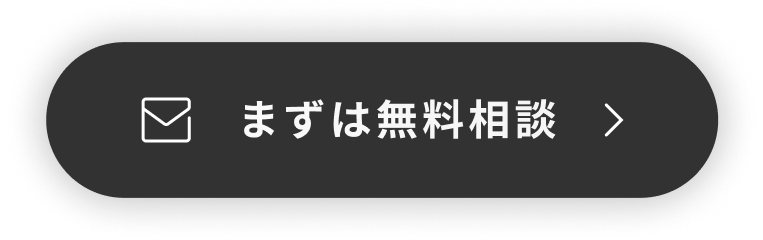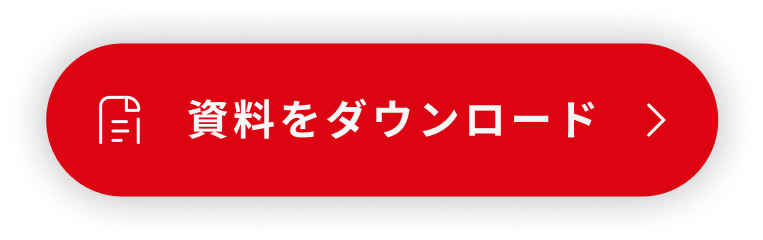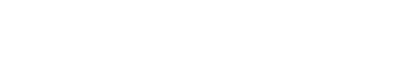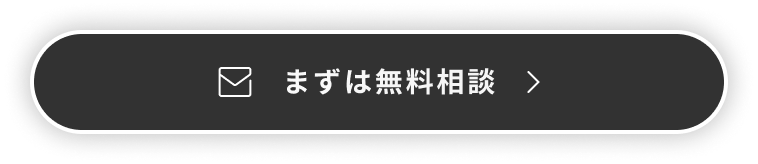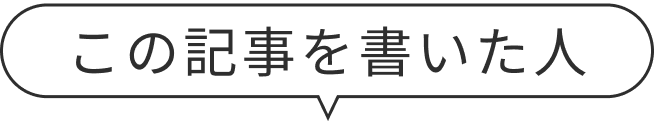社内運動会の面白い企画例を紹介!流れ・形式・メリットも解説
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



目次
社内運動会とは、レクリエーションとして実施される社内イベントです。ファミリーデーとして社員の家族も参加できる形式での実施も可能で、社内交流を促進させることができます。
本記事では、社内運動会の概要や種目・形式、おすすめの会場、実施するメリット、実施する際の流れ・ポイント、効果的な企画例を紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
社内運動会とは

社内運動会とは、社員の休養やリフレッシュを目的とした社内レクリエーションの1種です。社員の休養やリフレッシュの他に、社内の交流促進や、社員とその家族のコミュニケーション促進、チームビルディングなどの効果も得られます。
テレワークの普及に伴って社内コミュニケーションの不足が人材の定着や成果向上における課題として認識されるようになり、対面形式(オフライン)での交流ができる社内運動会を実施する会社が増えています。社内運動会は大人数での実施が可能なため会社全体としての社内イベントとして実施しやすく、社員同士の協力・連携が必要なためチームビルディング効果が高いことが特徴です。
社内運動会の定番種目

ここからは、社内運動会の定番種目を紹介します。
リレー種目
以下では、リレー種目を紹介します。
400mリレー
400mリレーは、4人で100mずつ、または8人で50mずつ走るリレー種目です。
運動会の花形種目の1つで、盛り上がりやすいことが特徴です。スプリント能力が求められ、足が速い人が有利になります。また、バトンパスが重要なため、スムーズに受け渡せるようになるまで練習することも大切です。
障害物リレー
障害物リレーは、ネットや平均台などの障害物を配置したリレー種目です。
スプリント能力だけでなく、安定して障害物を突破していくことが求められるため、足の速さだけでは結果につながらない可能性があることが特徴です。障害物を突破するために両手を使う必要がある場合は、バトンではなく襷(たすき)を受け渡す形にするのがおすすめです。
バケツリレー
バケツリレーは、水を入れたバケツを受け渡すリレー種目です。
水がこぼれないようにバケツを運ぶ必要があり、スプリント能力が求められにくいことが特徴です。水をこぼしてしまった場合は3~5秒ほど静止するペナルティが課されます。慎重にバケツを運ぶことに加え、速さも求められるため、集中して取り組む必要があります。
徒競走種目
以下では、徒競走種目を紹介します。
徒競走
徒競走は、200m走、100m走、50m走などのタイムを競う種目です。
純粋なスプリント能力がもっとも重要になりますが、スタートの反応速度や、トップスピードに至るまでの早さ、トップスピードの持続力(持久力)なども求められます。シンプルなルールで、勝敗がわかりやすいことが特徴です。
障害物競走
障害物競走は、ネットや平均台、麻袋、アメ探しなどの障害物を配置し、タイムを競う種目です。
スプリント能力だけでなく、障害物を安定してクリアするテクニックや、運なども求められるため、スプリント能力に自信がない人でも活躍しやすいことが特徴です。
パン食い競走
パン食い競走は、パンを紐で吊るした障害物を配置し、タイムを競う種目です。パンを早く口でキャッチするテクニックが求められますが、障害物の数が少ないためスプリント能力も重要になることが特徴です。また、パンは素早く口でキャッチするには運も求められます。パンはコッペパンを使用するのが一般的です。
借り物競走
借り物競走は、ランダムに並べられたお題が書かれた紙を手に取り、それに書かれた物を借りてからゴールに向かう種目です。
たとえば、お弁当、腕時計などのお題を紙に書いておき、参加者はそれを借りる必要があります。物を借りる際にコミュニケーションを取り必要があることが特徴です。実施する際には、腕時計や電子機器などには高価な物や愛着のある物がある可能性があり、物の破損が起こらないように、出場する参加者に大き目の巾着袋などを渡しておくとよいでしょう。
借り人競走
借り人競走は、ランダムに並べられたお題に人の特徴を書き、それに合う人と一緒にゴールを目指す種目です。
たとえば、身長が180cm以上の人、営業部の人など、特定の条件をお題として設定します。借り人競走を実施する際にはお題が周知されるため、実施する際には客観的に失礼だと感じられる可能性のあるお題を含めないようにすることが重要です。
ムカデ競走
ムカデ競争は、4~5人のチームを組んで一列に並び、右足と左足をそれぞれ前後の人と紐でつないで走る競走種目です。
全員が足を前に出すタイミングを合わせることが求められ、上手におこなうには練習する必要があります。そのため、チームビルディング効果が高いことが特徴です。また、スプリント能力が求められにくく、多くのチームに勝つチャンスがあることもポイントとなります。
キャタピラ競走
キャタピラ競走は、キャタピラの形につなぎ合わせた段ボールなどのなかに入り、赤ちゃんのハイハイのようにして進んでゴールを目指す種目です。
屋外で実施する際は手のひらやひざなどをケガしてしまう可能性があるため注意が必要です。キャタピラ競走は屋内で運動会をおこなう際におこなうとよいでしょう。
大玉・玉入れ種目
以下では、大玉・玉入れ種目を紹介します。
大玉転がし
大玉転がしは、大玉を地面に置き、押して転がしてタイムを競う種目です。
徒競走としておこなう場合と、リレー形式でおこなう場合があります。
大玉送り
大玉送りは、大玉を持ち上げ、チーム全員で地面につかないように気をつけながら送っていき、ゴールを目指す種目です。
大玉が地面についた場合は、その地点からやり直しとなります。参加者は大玉を送ったら順に前に移動する必要があるため、持久力が求められます。また、大玉が地面に落ちないようにするためには大玉をコントロールしたり支えたりする役割が重要です。チームで協力する必要があるため、チームビルディング効果が高いことが特徴です。
玉入れ
玉入れは、小さな玉を高い位置に設置したかごに投げ入れる種目です。
スプリント能力や持久力などは求められず、玉を投げるコントロール力のみが重要となります。
綱引き種目
以下では、綱引き・棒引き種目を紹介します。
綱引き
綱引きは、大綱を複数人で引っ張り合う種目です。
個々の腕力や持久力だけでなく、チームで強く引くタイミングを合わせることが求められるため、結束力があるチームが有利となります。
大繩種目
以下では、大縄跳び種目を紹介します。
大縄跳び
大縄跳びは、大繩を回し、全員の足がひっかからないように気をつけながら縄跳びをする種目です。
4~10人程度で、足が引っかからずに連続して跳べた回数を競うのが一般的です。大繩を回す役割の人が同じリズムでおこなうことが大切です。また、タイミングを合わせる必要があるため、練習を積むことも重要となります。
組体操種目
以下では、組体操種目を紹介します。
人間ピラミッド
人間ピラミッドとは、参加者が四つん這いになり、ピラミッド型になるように積み重なっていく種目です。
最下段から4人、3人、2人、1人のように積み重なっていくことでピラミッド型になります。競技性は低く、すべてのチームが完成させられることが重要です。
チーム対抗種目
以下では、チーム対抗種目を紹介します。
棒倒し
棒倒しは、立てた棒を先に倒すことを目指す種目です。
チームごとに棒を支える役割と敵の棒を倒しに行く役割に分かれます。チームは2チーム以上あれば問題なく、3~4チームに分かれて実施することもできます。
棒引き
棒引きは、中央に置かれた棒を自陣に持ち帰ることを目指す種目です。
他のチームと競合した場合は、棒を引っ張り合う必要があるため棒引きと呼ばれます。開始直後に棒がある位置まで走る必要があるためスプリント能力が求められますが、棒を引っ張る腕力や持久力なども幅広く求められます。また、どの棒に人員を割くかなどの戦略性もあるため、頭を使うことも重要となります。
騎馬戦
騎馬戦は、2~3人が馬をつくってそのうえに1人が乗り、帽子やハチマキを取り合う種目です。
帽子やハチマキを取る際に接触する可能性があり、目の周辺に指が当たってケガをするなどのリスクがあるため、実施する際には注意が必要です。騎馬戦を実施する際は、相手の騎馬を崩す形式にすることもできます。安全に実施することが大切です。
社内運動会を実施するメリット

ここからは、社内運動会を実施することで得られるメリットを紹介します。
社員の休養・リフレッシュ
社内運動会はレクリエーションの1種であり、社員の休養・リフレッシュが目的の1つです。また、会社が費用を負担して実施することが一般的でるため福利厚生の一環となり、体を動かすことを通じて健康増進(健康経営)につながることも期待できます。
社内の交流促進
社内運動会では、種目やランチタイムなどを通じて、社員同士が交流することができます。社内運動会の参加は全社員が対象となることが一般的で、部門・部署や支店の垣根を越えてコミュニケーションが促進されます。
社員とその家族のコミュニケーション促進
社内運動会をファミリーデーの形式で実施することで、社員とその家族のコミュニケーション促進にもつながります。社員が家族との間でコミュニケーションに関する課題を抱えている場合は、社内運動会を通じて、家族とのコミュニケーション改善や関係構築につながる可能性があります。また、社内運動会に社員の家族が参加することで、社内風土や社員の特徴などを知ることができるため、家族からの理解を得ることも期待できます。社員の定着・離職防止の観点で、家族からの理解を得られていることも一因となります。社内運動会を実施することで、離職を防ぐことにつながる可能性もあります。
チームビルディング
チームビルディングとは、社員が主体的に協力して連携し、効率的に成果を上げられるチームづくりを指します。チームが効率的に成果を上げるには、心理的安全性などのコミュニケーション上の課題がなく、互いに助け合うことが重要です。社内運動会を通じて、相互理解が深まったり、コミュニケーションが促進されたりすることで、チームビルディングにつながると期待できます。
社内運動会の形式・チーム分け

以下では、社内運動会を実施する際の形式について紹介します。
部門・部署・支店ごとのチーム分け
社内運動会をおこなう際には、チーム分けをする必要があります。部門や部署で分けたり、支店で分けたりすることで、業務上のチームビルディングにつながります。
チームビルディングが社内運動会を実施する重要な目的となる場合は、業務上のチームを優先してチーム分けをするとよいでしょう。また、ファミリーデーとして社内運動会を実施する際には、家族が同僚と接することができるため部門・部署・支店ごとのチーム分けがおすすめです。
ランダムなチーム分け
業務とは切り離して、ランダムにチーム分けをする方法もあります。
ランダムにチーム分けをすることで、業務上で関わりのない社員同士のコミュニケーションを促進させることができるため、社内交流が重要な目的となる場合におすすめです。
社内運動会をおこなう際におすすめの会場

会場を借りて社内運動会をおこなう場合は、雨天時などに日程変更をすることが難しく、天気による影響を受けにくい屋内会場を選ぶことが大切です。
以下では、社内運動会をおこなう会場の種類について紹介します。
屋内にある体育館・イベントホール
社内運動会を実施する際は、体育館やイベントホールなどの屋内会場がおすすめです。社内運動会に参加する人の数に応じて、十分な広さがある体育館・イベントホールを借りましょう。
200~500人程度の大人数でおこなう社内運動会の場合は1,000㎡程度が目安となり、数十人程度であればバスケットコート2面分ほどの広さで十分な場合もあります。会場側に参加者数や実施する種目などを伝えて、十分な広さがあるかを確認しておくとよいでしょう。
屋内にあるフットサルコート
屋内にあるフットサルコートも社内運動会の実施に適しています。フットサルコートは人工芝が一般的で、転倒時などにケガをしにくいことが特徴です。また、複数のフットサルコートがある会場が多く、大人数の社内運動会が実施可能な場合もあります。
ただし、フットサルコートで運動会をおこなう場合は、障害物競走などで使用する用具・機材などをフットサルコート上に置くことができない可能性があります。社内運動会の実施が可能か、用具の持ち込み・設置が可能かなどを会場の管理者に確認しておきましょう。
社内運動会を実施する際の流れ・ポイント
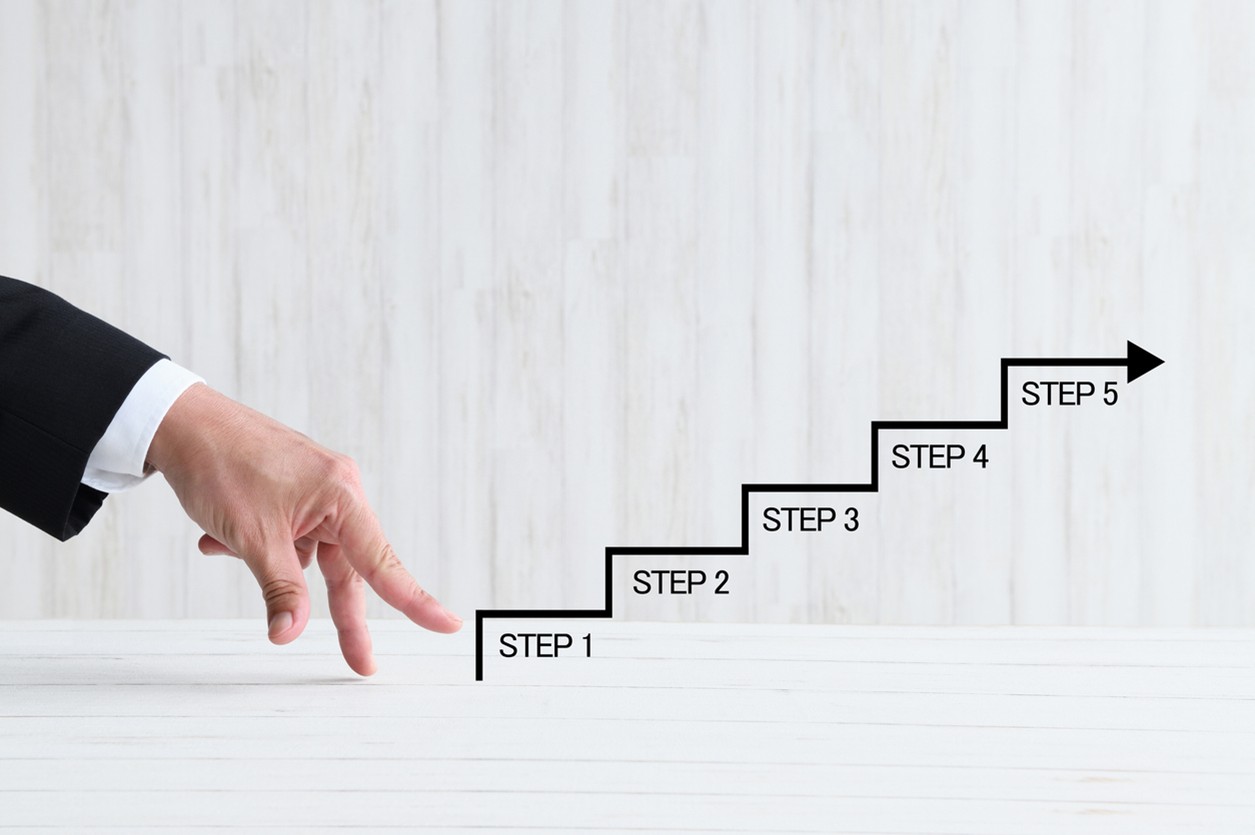
運動会に関するサービスを提供しているイベント会社を利用することで、実施するために必要な準備や運営の大部分を委託することができる場合があります。ここからは、イベント会社を利用せずに、自社で準備・運営をおこなう際の流れ・ポイントを紹介します。
運動会を実施する際の流れとしては、下記が一般的です。
- 担当者決め
- 企画立案
- 会場の選定・予約
- 用具・機材のレンタル
- 人員の手配
- 食事の手配
- 社員への案内
- 会場設営・準備
- 運営
以下で、それぞれの工程についてポイントを詳しく紹介します。
担当者決め
社内運動会を実施する際には、準備・管理・運営などをおこなう担当者を決める必要があります。参加者数やおこなう種目などの内容にもよりますが、会場の設営や当日の運営には10~20名程度の人員が必要な場合があるため、企画を立てる段階から十分な人数を確保しておくことが大切です。
また、社内運動会を実施する際には、会場や用具・機材の手配などをおこなう必要があり、漏れを防ぐために複数名の担当者で互いに確認しながら管理することもポイントになります。
企画立案
社内運動会の企画を立案する際には、実施までの詳細なスケジュール、社内運動会のプログラム、各担当者の進捗状況を管理するシートの作成などをおこないます。
社内運動会の実施に関する項目を洗い出し、いつまでに何をおこなえばよいかを明確にしておくことが大切です。社内運動会の実施に関する項目については、下記を参考にしてください。
社内運動会におけるチェックリストの一例
- 会場の手配・管理(キャンセル可能な日時・キャンセル料の確認などを含む)
- 社員への告知・案内(実施日時・場所の案内)
- 挨拶をおこなう社長・役員への依頼
- 用具・機材の手配・管理(用具リストを別途作成する)
- 人員の手配・管理(キャスティングを含む)
- 食事の手配・管理(お弁当の手配・管理)
- 社員への直前案内(リマインド)
- 会場への搬入確認(いつから搬入可能か、搬入できないものがないかなど)
- 搬入・設営(配置・設計、動線確認などを含む)
- 運営(担当者、流れの確認を含む)
会場の選定・予約
企画を立てたら、会場の選定・予約から進めていきます。収容人数、アクティビティスペースの広さ、機材・器材の有無、搬入可能な機材・器材などを確認したうえで、予算内におさまる会場を選定します。
会場によっては1年前から予約が可能だったり、仮押さえが可能だったりするため、適した会場が見つかったらまず日程を押さえておくことが重要です。
用具・機材のレンタル
社内運動会を実施する際には、おこなう種目によりますが、大玉、大綱、大繩などの用具が必要になります。準備する用具をピックアップし、必要な個数を含めてリスト化しておきましょう。
人員の手配
社内運動会をおこなう際には、運営に関わる人員の他に、司会者・MC、実況者などをキャスティングする場合もあります。必要な人員を洗い出し、リスト化しておきましょう。
食事の手配
社内運動会をおこなう際に正午をまたぐ場合は、食事を手配する必要があります。人数分のお弁当を発注できる業者に依頼するとよいでしょう。アレルギーや苦手な食べ物を避けるために、3~4つほどのお弁当をピックアップし、参加者自身が選べるようにすることがおすすめです。
社員への案内
運動会の実施に関する準備が進んだら、社員に案内メールを送ります。案内メールには日時、場所、服装、持ち物などを記載します。また、社内運動会に多くの社員が参加できるようにするために、会場の予約をした段階で日時・場所のみを先に伝えておくことも大切です。
会場設営・準備
運動会をおこなう当日または前日に、会場設営・準備をおこないます。会場によっては前日の夜から搬入や設営をおこなえる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
当日に搬入から設営までおこなう場合は、事前にシミュレーションをしておくことが大切です。短時間で搬入・設営を終えられるように準備しておきましょう。
運営
社内運動会の運営をおこなうには、プログラム表を作成し、項目ごとに誰が、何を、いくつ、どこに用意するのかを明確にしておくことが重要となります。
また、進行台本を作成することも大切です。オープニングからエンディングまでの司会進行に関する台本や、実況に関する台本などを作成しておきましょう。
社内運動会の面白い企画例
以下では、社内運動会の面白い企画例を紹介します。
戦国運動会
戦国運動会は、戦国時代の世界観を取り入れたオリジナル種目をおこなえる運動会サービスです。
大俵転がし、兵糧入れ、米騒動などの戦国時代をモチーフとした種目をおこないます。また、運営スタッフが戦国武将や忍者などの衣装を着たり、会場装飾にのぼりなどを活用したりすることで、戦国時代の世界観を表現します。
防災運動会
防災運動会は、災害発生時に役立つ知識を得られる種目をおこなえる運動会サービスです。
防災クイズラリー、防災障害物リレー、防災謎解き、防災借り物競走などの種目を通じて、災害時に実際に活用できる知識やスキルを身につけることができます。また、昼食時に非常食体験会をおこなうことで、災害発生への備えとしておこなうことが重要な備蓄に対する意識を高めることにもつながります。
謎パ
謎パは、全員参加型の謎解きアクティビティです。
参加者の各々に異なる謎のピースを配布し、社員同士でコミュニケーションを取りながら謎を組み上げていくため、社員の交流が促されます。また、ミッションが取り入れられていることで、謎解きが苦手な人も活躍することができます。全員で協力し、一緒に取り組むことができるため、チームビルディング効果が高いことも特徴です。
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、戦略性とチームワークが重要な合戦アクティビティです。
スポンジの刀を手に持ち、肩についているカラーボール(命)を落とし合います。合戦をおこなう前に軍議をおこない、チームとしての作戦を立てます。勝利を目指すには作戦と協力が重要なため、チームビルディング効果が高いことが特徴です。また、運動能力が求められにくい設計になっており、全員が没入感をもって楽しく取り組むことができます。小学生以上の子どもも参加可能で、ファミリーデーとして実施する社内運動会にも適しています。
まとめ

社内運動会を実施することで、社員の休養・リフレッシュ、社員の交流促進、社員とその家族のコミュニケーション促進、チームビルディングなどの効果が得られます。社内運動会の実施を検討している方はぜひIKUSAにご相談ください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る