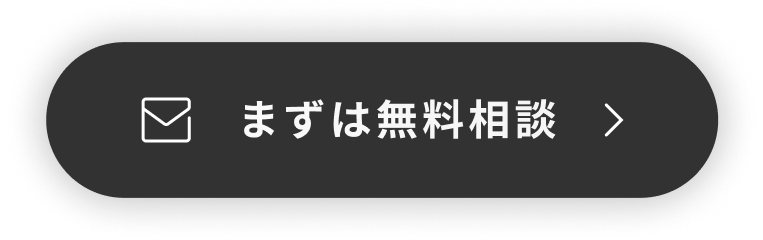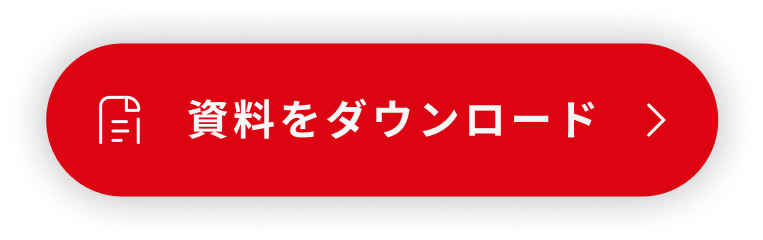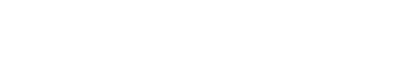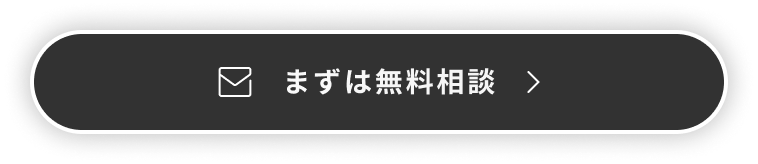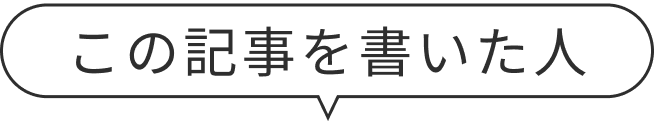社内レクリエーションの企画アイデア60選!メリット・注意点も紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



目次
社内レクリエーションとは、社員の心身を癒やすことを目的とした楽しみ・休養を指します。社内レクリエーションを実施することで、社員をリフレッシュさせ、社内コミュニケーションの促進・関係構築や、帰属意識・モチベーションの向上などにもつなげることができます。
本記事では、社内レクリエーションの概要、種類、必要とされる背景、メリット、実施する際のポイント、企画アイデア60選を紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
社内レクリエーションとは

社内レクリエーションとは、社員に蓄積された日々の疲れを癒やしたり、労ったりするために実施される社内イベントです。社員旅行や社内運動会などが社内レクリエーションに含まれ、実施することで社員のリフレッシュや社内コミュニケーションの促進などにつなげることができます。
社内レクリエーションを実施する際は、社員がリラックスして楽しめる企画を立てることが大切です。たとえば、体を動かしたり、特別な体験ができたりするアクティビティを取り入れることで、社員が楽しく主体的に取り組むことを促せます。社内レクリエーションを実施する際は、参加者の年齢層や性格などに特徴に合わせ、実施することで喜ばれると期待できるアクティビティを取り入れましょう。
社内レクリエーションに含まれる社内イベントの種類
以下では、社内レクリエーションに含まれる社内イベントを紹介します。
社員旅行
社員旅行は、全社員を対象として実施される年間行事の1つで、社員のリフレッシュや人間性の向上などを目的として実施される社内イベントです。多くの社員が一緒に旅行をすることで、業務上では知ることができない意外な一面が見られたり、相互理解が深まったりして、社員同士の関係構築が促されます。また、リフレッシュすることが前提となるため、アクティビティを取り入れることで社員が気兼ねなく主体的に楽しみやすいことも特徴です。
社員旅行には、全社員を対象とした旅行行事の他に、会社に貢献した・成果を上げた社員を対象とした報奨旅行などもあります。報奨旅行は社員を労うことが目的となるため、社員旅行と同様にアクティビティの実施が適しています。少人数の報奨旅行の場合は、アクティビティ施設を利用するのがおすすめです。ただし、10~20名以上の大人数の場合は施設を利用できない可能性があるため注意が必要です。施設側に確認しておきましょう。
社内運動会
社内運動会は、全社員やその家族などを対象として実施される年間行事で、社員のリフレッシュや健康増進などを目的として実施されるため社内レクリエーションに含まれます。社内運動会は100人以上の大人数でも実施することが可能で、体を動かせるためリフレッシュ効果が高いことが特徴です。また、社員同士の交流を促進させたり、チームビルディングにつなげたりすることもできます。
懇親会・忘年会
懇親会や忘年会は、食事・歓談を通じて社内交流を促進させたり、関係構築につなげたりすることを目的とした社内イベントです。食事を伴う社内イベントには、体験型アクティビティや簡単なゲームを取り入れやすいため、社内のコミュニケーションを促進させたり、チームビルディングにつなげたりすることが目的となる際に適しています。
季節イベント
会社における季節イベントは、年間行事として実施する季節的な社内イベントを指します。レクリエーションを目的とした季節イベントとしては、花見、納涼祭、クリスマスパーティーなどが挙げられます。季節イベントは毎年の同時期に実施することができるため、年間行事にしやすいことが特徴です。
社内レクリエーションが必要とされる背景
会社の社内風土や業界、社員の年齢層などによって異なりますが、社内レクリエーションが必要とされる背景としては、社内コミュニケーションの希薄化がまず挙げられます。テレワークにより社内で雑談をする機会が減っていたり、若手社員の中心に社内行事への参加率が低かったりすると、社内のコミュニケーションが希薄化していきます。社内コミュニケーションを促進させるために、社内レクリエーションが必要とされています。
また、健康増進(健康経営)や福利厚生の充実に関しても、社内レクリエーションが適しています。社内レクリエーションには体を動かすアクティビティを取り入れやすく、運動する意識を向上させたり、運動不足を緩和させたりする効果が期待できます。また、社内レクリエーションの社内イベントは多岐に渡り、さまざまな福利厚生を充実させることにつながります。
社内レクリエーションを実施するメリット

ここからは、社内レクリエーションを実施することで得られるメリットを紹介します。
社員のリフレッシュ
社内レクリエーションを実施することで、社員をリフレッシュさせることにつながります。好きなこと・楽しいことをして気分転換や休養をすること自体は、社員の各々が休日などを利用しておこなえます。しかし、たとえば社内レクリエーションを通じて相互理解が深まり、少しコミュニケーションに壁のある社員同士の関係が改善し、気持ちが楽になるといった効果が得られれば、業務上のストレス改善を含めたリフレッシュにつながる可能性があります。
社内コミュニケーションの促進・関係構築
社内レクリエーションをおこなうことで、業務外での社員同士のコミュニケーションを促進させたり、関係構築につなげたりすることができます。業務外で楽しくコミュニケーションを取ることで、新たな一面が見え、相互理解が深まります。また、互いの共通点が見つかり、会話が弾むこともあるでしょう。社内レクリエーションは、コミュニケーション促進・関係構築の課題解決に適しています。
帰属意識の向上
社員旅行や社内運動会などの全社員を対象とした社内レクリエーションを実施することで、帰属意識の向上につながります。帰属意識とは、社員が会社に属していることに対する意識を指します。全社員と共通体験をすることで、会社に所属し、同僚と一緒に仕事をしていることを実感できるため、帰属意識の向上につながります。
モチベーション向上
社内レクリエーションを通じて社員同士が交流し、業務上では接することがない社員と意見交換や情報交換をおこなうことで、刺激を受け、モチベーションが向上することにつながります。社員旅行の部屋割りや食事をする際の席を他の部門・部署・支店の社員と同じにすることで、交流を促進させることができます。
社内レクリエーションを実施する際のポイント・注意点

以下では、社内レクリエーションを実施する際のポイントや注意点を紹介します。
社員が好きなアクティビティを選択できるようにする
社内レクリエーションのなかで社員自身が体験するアクティビティを選べるようにすることで、主体性を高めることができます。社員が体験する内容をすべて会社側が決めてしまうと、社員が受け身になる可能性がありますが、社員自身の意志で選択することで主体的に取り組むことにつながります。社内レクリエーションを実施する際には、社員自身の意志で決めるポイントを含めることが大切です。
特別な体験ができるようにする
社内レクリエーションは社員旅行や社内運動会などの会社がコストをかけて実施され、多くの社員が参加する特別な行事となります。日常生活では体験できないことや、業務上で活用できる学びがあることなど、社員にとって特別な体験となるようにすることが大切です。
体を動かすレクリエーションのアイデア30選

ここからは、体を動かすレクリエーションのアイデア30選を紹介します。
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、複数の軍に分かれて、スポンジ製の刀を使い、腕につけた命と呼ばれるカラーボールを落とし合うアクティビティです。
1,000人規模での実施も可能で、全社的な社内レクリエーションにも適しています。チャンバラ合戦では軍議と実戦を繰り返すため、チームでPDCAサイクルを回しながら改善をはかり、協力することでチームビルディングにつなげることができます。
バブルサッカー
バブルサッカーは、上半身がやわらかい大きな球状のバブルで包まれた状態で行うニュースポーツです。
ルールはサッカーやフットサルに似ており、4~5名でチームを組んでおこなうのが一般的です。4~5人のチームのうちの1人はバブルキーパー(ゴールキーパーの役割)となります。バブルを装着することで動きや視界が制限されるため、運動が得意な人が活躍できるとは限りません。また、接触しても怪我をしにくく、安全性が高いことも特徴です。また、バブルを活用したバブル相撲や、バブルロワイヤルなどのアクティビティをおこなうこともできます。
キンボールスポーツ
キンボールスポーツは、大きくて軽いボールを「オムニキン!」という掛け声とともに打ち、コールされたチームがキャッチするニュースポーツです。
キンボールスポーツは、4人1チーム、計3チームで試合をおこなうことが一般的です。大きさ122cm、重さ1㎏で大きくて軽いボールを使用します。ボールを打つ際は3人で持ち上げ、残りの1人が打ちます。ボールを打つ際には「オムニキン!」という掛け声とともに、次にキャッチするチームを色で指定します。チームで協力して取り組む必要があり、楽しくコミュニケーションを促進させることができます。
参考:コンペティション(ルール) | 競技を知る | 一般社団法人 日本キンボールスポーツ連盟
ドッジボール
ドッジボールは、2チームそれぞれが外野と内野に分かれてボールを投げ合うスポーツです。
小学生が学校でおこなうスポーツの定番といえますが、大人も熱中して取り組みやすいことが特徴です。1チーム6~10名程度で実施することが一般的で、屋内・屋外のどちらでも実施することができます。開始時点では3名が外野となり、敵陣側の各辺に1人ずつ立ちます。内野にいる人がボールをキャッチできずに当てられた場合は、内野に一度も入っていない外野の選手と入れ替わり、全員がボールを当てられたら負けとなります。ルールがシンプルでわかりやすく、短時間で盛り上がることができます。
フットサル
フットサルは、5人制でおこなわれるサッカーに似たスポーツです。
フットサルコートは、サッカーコートの1/4ほど(長さ25~42m、幅16~25m)と狭く、攻守の切り替えが早いことが特徴です。ボールはサッカーよりも一回り小さい4号球(サッカーは5号球)を使用します。また、足の裏を使用する頻度が高く、ゴールキーパーが攻撃に参加する戦術などもあり、サッカーとは違った特徴があります。サッカーのように足の速さや力の強さが求められにくく、社内レクリエーションに適しています。
キックベースボール
キックベースボールは、野球とサッカーが融合したスポーツです。
野球は内野が1塁からホームベースまで4つの点を結ぶひし形(四角ベース)ですが、キックベースボールでは1塁からホームベースまで3つの点を結ぶ3角形(三角ベース)でおこなうこともできます。守備はピッチャー1人、内野2~3人、外野2~3人でおこなうことが一般的です。ピッチャーはボールを転がし、攻撃側のバッター(キッカー)がボールを蹴ります。地面につかずにキャッチできたり、ボールをバッター(キッカー)やその他の走者にタッチすることができたりすればアウトとなります。やわらかいボールを使用することが一般的で、ルールがシンプルなため、社内レクリエーションとして実施しやすいことが特徴です。
サバイバルゲーム
サバイバルゲームは、エアガンとBB弾を使用して撃ち合うアクティビティで、サバゲーとも呼ばれます。
サバイバルゲームをおこなうフィールドには障害物が配置されており、身を隠しながら攻め込み、相手にBB弾を当てることを目指します。殲滅戦(敵チームを全滅させられたら勝ち)、拠点制圧戦(より多くの拠点を制圧したチームの勝ち)などの形式があり、チームで協力して勝利を目指すことが求められます。BB弾が当たると痛みを感じ、目などを守る必要もあるため、サバイバルゲームを実施する際は、専用の施設を利用し、きちんと説明を受けることが大切です。サバイバルゲームはチームで協力する必要があるためチームビルディング効果が高く、大人が熱中できるアクティビティといえます。
レーザーシューティングバトル
レーザーシューティングバトルは、レーザー銃を使用して安全にサバイバルゲームを実施できるアクティビティです。
サバイバルゲームと同様に殲滅戦や拠点制圧戦などの形式でおこない、チームで協力して勝利を目指します。レーザー銃を使用するため痛みを感じることがなく、安全に実施することができます。
グラウンド・ゴルフ
グラウンド・ゴルフは、ゴルフのようにクラブでボールを打ち、ホールポストにホールインするまでの打数を数え、全ホールの合計打数の少なさを競うニュースポーツです。
ホールポストに向かってクラブでボールを打ち、ホールインするまでにかかった打数を各ホールで数えます。また、1打目でホールポストにホールインできた(ホールインワン)場合は、合計打数から3打分を引くことができます。年齢や性別などに関わらず実施しやすく、やり方・ルールがシンプルなため、社内レクリエーションでの実施に適しています。
参考:グラウンド・ゴルフとは?
スラックライン
スラックラインは、木やポールなどの間を専用のラインでつなぎ、そのラインのうえを歩いたり跳ねたりするニュースポーツです。
地面から10cm程度の高さに専用のラインを設置することが一般的で、安全に実施しやすいことが特徴です。専用のラインに乗ったり歩いたりする簡単な動作でも難しく、大人が熱中して取り組みやすく、簡単に実施できるため、社内レクリエーションに適しています。
参考:スラックラインとは – 一般社団法人スラックライン推進機構
ドッヂビー
ドッヂビーは、ソフトディスクを使用し、ドッヂボールと同様に当てることとキャッチすることを繰り返すニュースポーツです。
コートの広さは9m×18mで、1チーム13人でおこないます。制限時間が設けられ、終了時点で内野にいる人数が多いチームの勝ちとなります。ボールと異なる軌道で飛ぶソフトディスクをキャッチすることの難しさがあり、大人が熱中して楽しみやすいことが特徴です。
フロアカーリング
フロアカーリングは、体育館などの床で専用のストーンを滑らせ、氷上でおこなうカーリングのように的(ターゲット)に近づけることを目指すニュースポーツです。
カーリングで使われるストーンのような形をした木製のフロッカーを使用し、ターゲットに近づけることを目指します。1チームの人数は4人を基本とし、1~3人でおこなうこともできます。先行と後行に分かれ、先行のチームがまずターゲットを投げます。その後、交互にストーンを投げ、グリーンゾーン内でターゲットにより近い位置にフロッカーがあるチームに得点が入ります。9点先取したチームの勝ちとなります。フロッカーをバウンドさせるように投げると床を傷つける恐れがあるため注意が必要です。軽くスイングさせ、バウンドしないように床に対して水平に押し出すように投げましょう。
参考:新得生まれのニュースポーツ「フロアカーリング」 | スポーツ | 文化・スポーツ | 北海道 新得町
HADO
HADOは、AR(拡張現実)の技術を取り入れ、ゲームのなかのように戦うことができるスポーツです。
HADOゴーグルとアームセンサーを装着することで、エナジーボールを放ったり、シールドで防御をしたりすることができます。参加者は自身のパラメーターをカスタマイズすることができ、チーム内で戦略を立てて取り組むことで勝利が近づきます。アタッカー、ディフェンダー、テクニッカーの役割があり、チームで協力することが重要です。戦略性や協力性が高く、チームビルディングを目的とした社内レクリエーションに適しています。
参考:エナジーボールを放って対戦する新感覚ARアクティビティ|HADO
カバディ
カバディは、インドやバングラデシュなどの南アジアでなどで数千年の歴史を持つ伝統的なスポーツです。
1チーム7人で、攻撃側のうち1人が敵陣に入ったらスタートとなり、相手チームの選手にタッチして自陣に戻る(ミッドラインを体の一部が越えることができればOK)ことができれば1点獲得できます。逆に、守備側が攻撃側の選手を捕まえることができれば守備側に得点が入ります。攻撃側の選手は「カバディ」と息継ぎなしで声を発し続ける必要があり、体力や持久力が求められます。
参考:カバディの歴史・ルール・道具 – スポーツ辞典 – 笹川スポーツ財団
ヨガ
ヨガは、呼吸法と正姿勢を組み合わせ、心身を正しい状態に近づけるためのエクササイズです。
大人数で一緒に実施することが可能で、屋内で実施することが一般的です。ヨガをおこない、正しい姿勢や呼吸法を実践することで、呼吸を楽にしたりリラックスしたりすることができます。また、ヨガで呼吸や姿勢を改善することで充実感が得られ、ウェルビーイングの向上につながることも特徴です。
参考:ヨガとは | ヨガ:認定NPO法人日本ヨガ連盟 ヨガ:認定NPO法人日本ヨガ連盟
ボッチャ
ボッチャは、ヨーロッパを発祥とし、四肢重度機能障がい者を対象として生まれたスポーツです。
バラリンピックの正式種目で、障がいの有無に関わらず幅広い世代の方々が一緒に楽しめることが特徴です。ボッチャでは、ジャックボールと呼ばれる目標となるボールを軸として、自チームのボールを近づけることを目指します。各チーム6球ずつを投げたり転がしたりすることができます。投げ方は上からでも下からでもよく、投げることができない人もランプ(勾配具)を使用して投げることができます。自由で奥深く、またシンプルなルールで実施できるため、社内レクリエーションに適しています。
モルック
モルックは、フィンランド発祥で、モルックと呼ばれる棒を投げてスキットル(木製のピン)に当てるニュースポーツです。
フィンランドの伝統的なゲームであるキイッカに基づいて開発されました。スキットルには番号が書かれており、モルックを投げて倒すことができるとその得点が入りますが、複数のスキットルを倒した場合はその本数が得点となります。得点が加算していき、先に合計50点ちょうどに達したチームの勝ちとなります。なお、50点を超えてしまった場合は、25点に減点されます。モルックを投げる位置からスキットルまでの距離は3~4メートルです。倒れたスキットルは再び立てられるため、進むごとにスキットルとの距離が遠くなっていきます。簡単に実施できますが奥深く、大人が集中して取り組みやすいことが特徴です。
スポレック
スポレックは、バドミントンコートとバドミントンネットを使用し、プラスチックのラケットとスポンジのボールを打ち合うニュースポーツです。
ネットの高さやルールはさまざまですが、1試合3セットとして、先に2セット先取した側の勝利となる形式が一般的です。サーブは下から上にラケットを振っておこない、対角にあるサービスエリアに入れる必要があります。また、サービスをレシーブする側は、ボールがワンバウンドしてから打ち返します。得点の入り方はバドミントンと同様にラリーポイント方式(サーブ権に関わらず得点が入る方式)で、11点を先取した側がセットポイントを獲得できます。
スポールブール
スポールブールは、1㎏ほどの小さなボールを目標球に当てるスポーツです。
古代エジプトやギリシャの文献にも記されており、原型は5000年前に存在した世界最古の球技であるとされています。ボールはソフトボールほどの大きさで、下投げで目標球に当てます。目標球は、はしご型の専用マットに置きます。5分間のうちに多く目標球に当てる「プログレッシブ」、5分間のうちに2人で4球ごとに入れ替わる「ラピット」、難易度が異なる11球の目標球に当てる「プレシジュン」、16球のボールを転がして目標球に近づける「コンビネ」などの形式があります。フランスやイタリアなどのヨーロッパで人気がありますが、オーストラリア、南米、アフリカなどにも強豪国があります。シンプルなルールですが難易度は高く、大人が熱中して取り組みやすいことが特徴です。
参考:世界最古の球技スポールブールとは | スポールブール公式HP
クッブ
クッブは、スウェーデン発祥の薪投げをするスポーツです。
四隅にコーナーピンナを立て、両チームのベースラインにベースクッブ、コートの中央に大きな木片であるキングを置きます。両チームは6本の木の棒であるカストピンナを投げてベースクッブを倒し、すべて倒し終えたらキングを倒すことができます。また、倒されたベースクッブは相手の陣地に投げ入れることができます。ベースクッブを倒す前にフィールドクッブを倒す必要があり、それによって戦略性が高まります。すべてのクッブを倒すまでキングに触れることはできず、誤ってキングを倒してしまうと負けになります。
カーリンコン
カーリンコンは、小さなディスクを投げてポイントを競うカーリングに似たニュースポーツです。
コートは長さ10m、幅3mを基本とし、中央にポイントを配置します。ポイントに近いディスクの数だけポイントが得られ、7点先取で勝敗が決まります。ポイントからディスクまでの距離が同じであった場合は、その2枚のディスクを除いて次に近いディスクがあるチームが1点を得られます。また、途中でポイントがコート外にはじき出された場合は、コート内にあるディスクの枚数が多いチームに、ディスクの枚数差に応じて得点が入ります(4枚と3枚の場合は1点)。ディスクはチームごとに交互に投げ入れます。ポイントをはじき出したり、相手チームのディスクの位置を考慮してどこに投げるかを決めたりする必要があり、奥深さがあります。
参考:日本カーリンコン協会
ラダーゲッター
ラダーゲッターは、両端にボールがついた紐をラダーに向かって投げ、引っかけることができたら得点が入るニュースポーツです。
ラダーの地面に対して水平の棒に紐が引っかかれば得点が入ります。得点は地面に近い棒から1~3点となり、地面に一度バウンドしてからラダーに引っかかった場合は5点となります。紐を投げる際は、片側のボールを手に持ち、振り子のように投げるのがポイントです。投げる位置からラダーまでの距離は7.5メートルが基本となります。また、試合は5セットマッチでおこなわれ、21点を先取したチームがセットポイントを取ります。3セットを先取したチームの勝ちとなります。
参考:ラダーゲッター | 公益財団法人日本レクリエーション協会
インディアカ
インディアカは、羽根がついたインディアカボールと呼ばれるボールを手で打ち合うスポーツです。
1チーム4人を基本として、3人が前列、1人が後列に配置されます。また、競技としておこなう際は、交代可能な選手を4人まで配置できます。バドミントンコートとバドミントンネットを使用してインディアカをおこなうことができますが、インディアカ専用のネットもあります。インディアカボールには4枚の羽がついており、バドミントンのシャトルのように減速します。手で打ち返すことがポイントで、ネット越しに打ち合います。バレーボールバレーボールと同様に3回以内に相手側のコートに返す必要があります。ラリーポイント制で21点を先取したらセットポイントを獲得し、2セット先取したチームの勝ちとなります。
参考:インディアカとは – 一般社団法人日本インディアカ協会
ユニホック
ユニホックは、体育館などのフローリングの床でおこなうニュースポーツで、ホッケーの一種です。
6人ずつの2チームで試合をおこない、より多くの得点を獲得したチームの勝ちとなります。試合時間は前半・後半が各10分の計20分で、前後半の間に2分間のハーフタイム(休憩時間)を設けます。選手はスティックを手に持ち、プラスチックのボールを打ちます。安全に実施するには、ゴールキーパーだけでなく、すべての選手がフェイスガードを使用することが推奨されています。
参考:ユニホックの歴史・ルール・道具 – スポーツ辞典 – 笹川スポーツ財団
ペタンク
ペタンクは、ペタンクボールと呼ばれる金属製のボールをビュットと呼ばれる目標球に近づけることを競うニュースポーツです。
1人あたり3球を基本とし、ダブルス(2対2)やトリプルス(3対3)の場合は1チームあたり6球になるように振り分けます。まず地面に35~50cmの円を描き、そのなかからビュットを投げます。円からビュットまでの距離は6~10mである必要があります。両チームがすべてのペタンクボールを投げ終えたあとに得点を計算します。ビュットからの距離が近いペタンクボールが3つの場合は3点を得ることができます。13点を先取したチームの勝ちとなります。
参考:ペタンクゲームの仕方・用具 – 公益社団法人 日本ペタンク・ブール連盟
スカイクロス
スカイクロスは、布製のやわらかいリングを投げて遊ぶ日本発祥のニュースポーツです。
小さなカラーコーンにリングを投げる競技形式が一般的で、最少回数でコーンにリングをかけることを目指します。複数の選手のリングが重なった場合は、重なるごとにリングが上にある選手のスコアに足されます。たとえば、リングが3つ重なった場合は、1つ上のリングを投げた選手に1回分、2つ上のリングを投げた選手に2回分の回数が足されます。また、一番下にリングがある人は、乗っているリングの数だけ減算されます。スカイクロスのルール・遊び方はさまざまで、実施しやすい方法・ルールでおこなうとよいでしょう。
参考:日本スカイクロス協会
シャフルボード
シャフルボードはキューを使用してディスクを押し出し、より多くの得点を獲得することを競うスポーツです。
シャフルボードは15世紀にスコットランドで生まれたスポーツとされており、シャッフルボードとも呼ばれます。コート内のスコアリングダイアグラムと呼ばれる得点区域にディスクを多く集めることがポイントとなります。コートの幅は1.8m、長さは15.8mで、コート上に得点が書かれています。得点の境目となるライン上にディスクが乗っていると得点が加算されません。また、コート上にはマイナス10点となるゾーンがあり、相手チームのディスクを押し出してそのゾーンに入れることが可能です。勝つためには戦略を立てることが重要となります。
参考:シャフルボードの歴史・ルール・道具 – スポーツ辞典 – 笹川スポーツ財団
コーフボール
コーフボールは、ゴールがコート内に配置されているため360度のどこからでもシュートを打つことができるバスケットボールに似たスポーツです。ドリブルをすることができない点や、ボールをキャッチしてから移動できる歩数が2歩までであることなどがバスケットボールと異なります。また、男女混合でおこなうことも特徴です。試合時間は前半・後半が各30分と長めに設定されており、ハーフタイム(休憩時間)は10分となります。
スカットボール
スカットボールは、スティックでボールを打ち、得点が定められた穴に入れるニュースポーツです。
ボールは各チーム5個ずつで、1~5人で実施することができます。スティックでボールを打って穴に入れるというシンプルなルールで、得点が定められた穴があるスカット台までの距離が5mと短く、初心者でもおこないやすいことが特徴です。また、スカット台の同じ穴に複数のボールを入れることはできません。合計得点が多いチームの勝ちとなります。
バッゴー
バッゴーは、傾斜のある台にある穴にビーンバックを入れるニュースポーツです。ビーンバックが穴に入れば3点、台のうえに乗れば1点が獲得できます。1チーム2人ずつでおこなうのが基本で、21点を先取したチームの勝ちとなります。台は2つ配置され、各チーム1名ずつが台の脇に立ちます。片方の2人が投げ終えたら、もう片方の2人が投げ、交互におこないます。
頭を使うレクリエーションのアイデア5選

ここからは、頭を使うレクリエーションのアイデア5選を紹介します。
謎パ
謎パは、参加者の全員が協力して謎を解き、ミッションクリアを目指すアクティビティです。
各々に謎のピースが配布され、組み合わせなければ謎解きを進められないため、必然的にコミュニケーションが促進されます。また、謎解きに行き詰った際にも協力することが求められるため、チームワークの強化につながることが特徴です。
謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームは、4~5人のチームで協力し、制限時間内に脱出することを目指す謎解きアクティビティです。
謎解き脱出ゲームはグループワーク形式でおこなうアクティビティで、チームごとに着席できるテーブルとイスがあればどこでも実施することができます。制限時間内に脱出するには役割分担をすることが重要となるため、チームで連携し、共通の目標に向かうことでチームビルディングにつながります。
リアル探偵チームビルディング
リアル探偵チームビルディングは、小グループと大グループを行ったり来たりして、真相を解き明かす推理ゲームです。
小グループごとに異なる情報が与えられ、対処法を小グループで考えたあとに、大グループで情報共有をおこないます。異なる情報を共有する「ジグソーメソッド」が取り入れられており、共有された情報を集めて活用することを学べます。最終的に、大グループで答えを決めて正解できればクリアとなります。
ワールドリーダーズ
ワールドリーダーズは、戦略と交渉により、利益の最大化を目指すなかでSDGs経営の本質を学ぶことができるビジネスゲームです。
ワールドリーダーズでは、4~5人のチームに分かれ、他チームより多くの利益をあげることを目指します。労働力や資金、事業カードなどが配布され、他チームと交渉して事業カードを交換したり、自チームで勝つための戦略を立てたりして利益の最大化を目指します。SDGsに対して取り組む際には、環境にいいことや、社会にいいことを優先して考える場合がありますが、本質的には持続可能であることが重要です。環境や社会にいいことばかりを優先するのではなく、利益も両立し、長期的に持続できるようにすることの大切さを学べます。また、戦略思考や交渉の方法やポイントも学ぶことができます。
eスポーツ
eスポーツは、テレビゲームやパソコンゲームを活用したスポーツ競技です。
格闘ゲームやFPSゲーム、スポーツゲームなどのジャンルがあり、国際大会も多数開催されています。eスポーツは配信することが可能で、支店が多かったり海外勤務の社員がいたりする場合の社内レクリエーションでも対戦や観戦をすることができます。
体験型ワークショップに関するレクリエーションのアイデア10選

ここからは、体験型ワークショップに関するレクリエーションのアイデア10選を紹介します。
染物体験
染物体験は、白い生地の布などに染料で色や模様をつける伝統工芸に関する体験型ワークショップです。
藍染め、ろうけつ染め、絞り染めなどの手法があり、ハンカチや手ぬぐい、Tシャツなどをつくることができます。
扇子づくり体験
扇子づくり体験は、白地の扇子に筆や絵の具で絵つけをする体験型ワークショップです。
扇子に好きな絵や言葉を書きます。また、伝統工芸の技術を活用し、和風の扇子をつくる扇子づくり体験もあります。扇子を手作りするキットが市販されているため自社で扇子づくり体験を実施することも可能です。
粘土アート体験
粘土アート体験は、粘土を使って動物や食べ物、植物などのミニチュア細工をつくる体験型ワークショップです。
粘土アートはクレイアートとも呼ばれます。粘土アートでは置物・オブジェの他に、ネックレスやピアスなどのアクセサリーをつくることもできます。粘土アート体験を実施している工房は多くあり、本物とそっくりなミニチュア細工をつくる体験をすることも可能です。
キャンドルづくり体験
キャンドルづくり体験は、ガラス細工、砂、花、貝などを入れてキャンドルをつくる体験型ワークショップです。工房やレジャー施設などで体験することができる場合があります。つくったキャンドルを家に飾ったり、実際に使ったりすることができます。キャンドルはグラス型が主流ですが、ろうそく型やスイーツ型などもあります。また、光るキャンドルをつくることも可能です。
万華鏡づくり体験
万華鏡づくり体験は、筒のなかに鏡、ビーズなどを入れて万華鏡をつくる体験型ワークショップです。
体験型ワークショップとしては紙素材やガラス素材の筒にビーズを入れる形式が主流といえますが、陶器の筒を使用したり、ビーズではなくプリザーブドフラワーを入れたりして万華鏡をつくる場合もあります。また、ドライタイプとオイルタイプの万華鏡があり、オイルのほうがやや高価です。筒のなかに幻想的なアートをつくることができ、特別な体験につながるでしょう。
木工クラフト体験
木工クラフト体験は、木材を使ってインテリアや食器、キーホルダーなどをつくる体験型ワークショップです。
木工は伝統工芸の1種で、木工クラフト体験として日本の伝統的なものづくりを体験することもできます。たとえば、下駄、弁当箱、皿、木工グラス、彫刻などが挙げられます。木には木目、肌触り、香りなどの味わい深さがあり、リフレッシュ効果が高いことが特徴といえます。
レザークラフト体験
レザークラフト体験は、革を使用して名刺入れ、キーケース、ブレスレットなどをつくる体験型ワークショップです。
革にはヌメ革、銀つき革、エナメル革、シュリンク革、オイルレザー革などのさまざまな種類があり、新品には高級感があり、使い込むことで味わい深さがでてくることが特徴です。また、穴あけや縫製などの工程を通じて、手作業で日用品をつくれることにも魅力があるといえるでしょう。
ガラス細工体験
ガラス細工体験は、アクセサリー、グラス、重し・置物、花瓶、とんぼ玉などをつくる体験型ワークショップです。
ガラス細工には、熱を利用して成形するホットワークと、常温の状態で加工するコールドワークの2種類があります。ホットワークとしては吹きガラスやバーナーワークなど、コールドワークとしては切子やサンドブラストなどがあります。伝統的な技法を体験し、美しいガラス細工をつくることができます。
陶芸体験
陶芸体験は、粘土を使って茶碗、湯呑、皿などをつくる体験型ワークショップです。
陶芸の技法には、粘土をこねるようにしてつくる手びねりと呼ばれる方法と、電動ろくろで成形する方法があります。陶器への色づけには釉薬と呼ばれる染料を使用します。同じものを二度とつくれないというところに味わい深さがあり、土を成形する面白さ・奥深さもあります。
アクアリウム体験
アクアリウム体験は、グラス、ボトル、水槽などのなかに植物、砂・石、植物などを配置する体験型ワークショップです。
また、アクアリウムを活用して熱帯魚などを飼うこともできます。植物や砂・石の色や形、大きさはさまざまで、好きなようにアクアリウムをつくる創作体験をすることで、リフレッシュ効果が期待できます。
鑑賞に関するレクリエーションのアイデア5選

ここからは、鑑賞に関するレクリエーションのアイデア5選を紹介します。
マグロ解体ショー
マグロ解体ショーは、30~50キロほどの本マグロを捌くパフォーマンスです。
迫力のある職人の技を間近に鑑賞することができます。また、解体したマグロを寿司や刺身にして食べられることも特徴です。会場が盛り上がりやすく、食事にもつながるためレクリエーションに取り入れるアイデアとして人気があります。
演劇
演劇は、台本がある物語・人物を舞台上で演じる芸術です。歌舞伎、能・狂言、喜劇などの伝統的な舞台劇の他に、バレエ、舞踏、日本舞踊などを取り入れた演劇もあります。感情表現や動作などの演技を間近で見ることに感動があることが特徴です。
落語
落語は、落語家が1人で物語の登場人物を演じ分ける話芸です。
落語家は伝統的な物語に基づいて話芸をおこないます。落語家の仕草や話し方に技術があり、集中して鑑賞することができます。また、話芸で扱われる演目には笑いや人情があることが特徴で、物語そのものを楽しめます。
マジックショー
マジックショーは、手品・マジックをパフォーマンスとしておこなうショーです。
手品・マジックはカードやコインなどを活用したテーブルマジックが一般的ですが、イリュージョンなどを取り入れた大規模なマジックショーもあります。種や仕掛けがわからない手品・マジックを見ることは特別な体験となるでしょう。
即興アート
即興アートは、画家や書道家などが即興で作品をつくるパフォーマンスです。
ライブアートや書道パフォーマンスなどがあり、芸術家が即興で作品をつくる姿を鑑賞することができます。パフォーマンスに音楽や照明を取り入れる芸術家もおり、迫力あるパフォーマンスを楽しめます。
食事に関するレクリエーションのアイデア5選

ここからは、食事に関するレクリエーションのアイデア30選を紹介します。
バーベキュー(BBQ)
バーベキューは、屋内または屋外で肉、野菜、マシュマロなどを焼く食事会です。
バーベキュー器材を持ち込むことで、川辺やキャンプ場などでバーベキューをおこなうことができ、自然のなかでリフレッシュすることができます。バーベキューをおこなう際は、バーベキューコンロ、炭、着火剤、網、食材、調理器具などを用意する必要がありますが、手ぶらバーベキューのサービスを利用することで食材や機材をレンタルすることも可能です。バーベキューは屋外での実施が可能で開放的な体験ができるためリフレッシュ効果が高いことが特徴です。また、自分たちで調理をおこなうため、役割分担や協力・連携ができるため、チームビルディング効果もあります。
飲み会
飲み会は、飲食を通じて社員同士の親睦を深めることを目的とした食事会です。
少し飲酒をすることで緊張がほぐれたり、新たなコミュニケーションや人間関係の構築につながったりすることが特徴です。また、食事会のため社員旅行などのレクリエーションに取り入れやすいことや、コミュニケーションを促進させるゲームや余興を実施できることもポイントといえます。懇親を深めることを重視する場合は、飲み会を取り入れるとよいでしょう。飲み会を実施する場合は、お酒を飲み過ぎたり、飲めない人に勧めたりしないように注意喚起することが大切です。
格付けバトル
格付けバトルは、絵画、俳句、牛肉などの一流の品を見極めるアクティビティです。
お題ごとに、複数の選択肢のなかから、一流だと思うものを選びます。正解すると現状維持、不正解になると降格となります。不正解になった際に降格演出をおこなうことで、会場を盛り上げます。また、MCやサポートスタッフが盛り上げをおこなうことも可能です。お題ごとの選択肢に社員やAIなどが制作したものを取り入れてカスタマイズすることもでき、回答の送信や集計にブラウザアプリケーションを活用することで円滑な進行が可能になります。また、格付けバトルはオンライン懇親会やオンライン忘年会などのオンラインで実施するレクリエーションでも実施可能です。
ゴチバトル
ゴチバトルは、高級店のシェフが考案した高級メニューを実食し、レストランで提供する場合の金額を予想するアクティビティです。
全員が同じものを食べて共通体験ができるため、チームビルディング効果があります。また、高級メニューを食べながら周囲の同僚と歓談を楽しみながら取り組むこともできるため、コミュニケーションを促進させられます。格付けバトルと同様に、金額の送信や集計にはブラウザアプリケーションを使用します。また、ゴチバトルはオンラインのレクリエーションでも実施可能です。
利き茶
利き茶は、香りや味の異なる複数のお茶を用意し、飲んだり香りを嗅いだりしてどのお茶なのかを当てるアクティビティです。
正解することができなかったとしても、集中して取り組むことでお茶ごとに異なる味や香りが感じられ、新たな発見を得られることが特徴です。利き茶をおこなう際は、目隠しをする方法と、お茶の色を見られる状態でおこなう方法があります。また、利き茶の形式については、静岡茶・京都茶などのように産地で分ける形や、緑茶・ほうじ茶などのように茶葉そのものが異なる形などが挙げられます。レクリエーションで利き茶を実施する場合は、味や香りの違いを大きくするために、異なる茶葉を使用する形がおすすめです。
施設を利用するレクリエーションのアイデア5選

ここからは、施設を利用するレクリエーションのアイデア5選を紹介します。
ボウリング
ボウリングは、レーンの奥に配置された10本のピンを目掛けて硬く重たいボールを投げ、倒れたピンの本数によって決まるスコアを競うスポーツです。
実施するにはボウリング施設を利用する必要がありますが、日本では定番とされる遊びの1種で、多くの人が気軽に楽しみやすいことが特徴です。また、会社のレクリエーションとしても一般的といえます。
ダーツ
ダーツは、円形の的に向けて1ターンごとに3本の矢を投げ、刺さった位置に応じて得点が決まるスポーツです。
施設を利用することで簡単に実施することができ、ボウリングと同様に社内レクリエーションの定番といえます。ダーツには、得点を加算していくカウントアップ、持ち点から減算していってちょうど0にすることを目指すゼロワン、陣地を取りつつ加算していくクリケットなどの種目があります。レクリエーションで実施する際には、運や戦略の要素があるゼロワンやクリケットがおすすめです。
アーチェリー
アーチェリーは、弓を引いて矢を放ち、的に当てた際の得点を競うスポーツです。
アーチェリーをおこなう際は、安全に実施するための指導を受けることが大切で、実施可能な場所も限られているため体験施設を利用する必要があります。アーチェリーで矢を放って的に当てるには、弓を引く強さ、角度、風などを考慮することが重要です。考えながら集中して取り組むことが求められ、没入して楽しめることが特徴です。
クライミング
クライミングは、指をかける突起物(ホールド)が配置された壁を登るアクティビティです。
クライミング施設を活用することで体験することができます。クライミングには、決められたルートで登りきった回数を競うボルダリング、より高く登ることを競うリードクライミング、登りきるタイムを競うスピードクライミングなどがあります。レクリエーションで実施する際には、時間をかけて落ち着いて登ることができるボルダリングかリードクライミングがおすすめです。
フィットネス
フィットネスは、筋トレ、有酸素運動、ストレッチなどをおこなうアクティビティです。
フィットネス施設を利用することで、フィットネスマシンなどを体験することができます。また、体幹を鍛えるピラティス、音楽に合わせて体を動かすエアロビクス、ボクシングの動きを取り入れたボクササイズなどもフィットネスに含まれます。
まとめ
社内レクリエーションを実施することで、社員のリフレッシュ、コミュニケーション促進・関係構築、帰属意識やモチベーションの向上などの効果を得られます。社内レクリエーションを実施する際は、社員が交流できたり、協力して楽しく取り組めたりする企画アイデアを取り入れることが大切です。社内レクリエーションについては、ぜひIKUSAにご相談ください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る