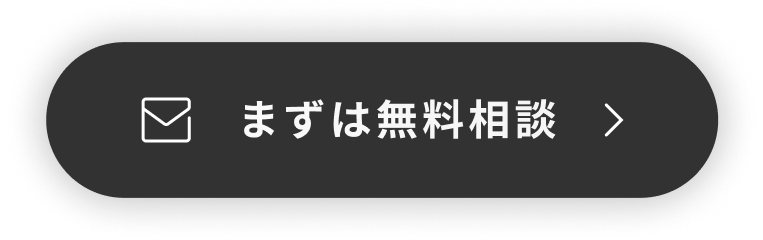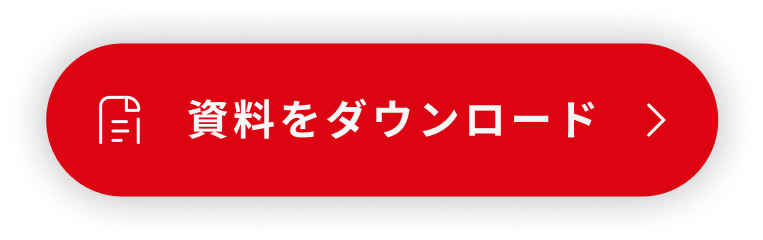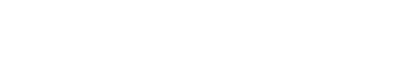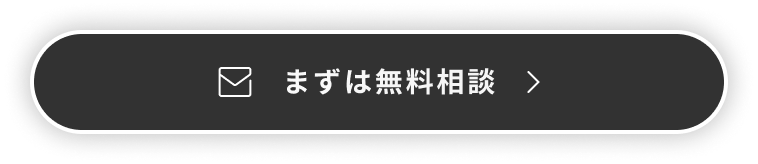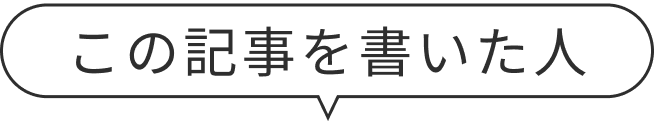懇親会の幹事は何をする?チェックリスト・役立つツールも紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



目次
懇親会は大人数で行われることも多く、目的を持って開催されることから、幹事の役割は非常に重要です。準備から当日の運営まで、スムーズな進行には細やかな配慮と段取りが欠かせません。
本記事では、懇親会を実施する目的や幹事に求められるスキル、準備のチェックリストに加え、便利なツールや会場選びのポイント、予算・社内調整、若手社員の参加促進、リスク対策、事後対応、そしておすすめの企画例まで幅広く紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
会社の懇親会を実施する目的

ここからは、会社の懇親会を実施する目的を紹介します。
コミュニケーション促進
会社の懇親会は、社員同士の交流を深め、組織の一体感を高めるための重要な取り組みです。特に組織の課題として挙げられることの多いコミュニケーション不足や、部署間の連携強化に効果が期待できます。また、業務時間内では見えにくい社員の一面を知る機会にもなり、通常業務をする際の関係構築にも役立つでしょう。定期的な懇親会を通じて、組織の風通しの良さや社員のエンゲージメント向上を図ることができます。
部署をまたいだ交流の促進
業務で接点の少ない社員同士が会話できる機会をつくることで、部署間の理解が深まり、社内の連帯感が高まり、連携が取りやすくなるでしょう。部署間で連携が取れるようになると、情報共有や課題解決のスピード向上にもつながるため、部署を越えた協力体制の強化につながります。
新入社員・中途入社社員の定着支援
入社後間もない社員にとって、懇親会は職場に早くなじむための貴重な場です。上司や先輩社員との会話を通じて、緊張をほぐしたり、会社の雰囲気をつかめたりするため、定着率や満足度の向上につながる可能性があります。また、他部署の社員と接点を持つことで、社内への理解も深まり、自分の居場所や役割を見出しやすくなります。
企画の完了や期末の節目としての労い
懇親会を1つの節目として位置づけることで、関係者への感謝を伝える機会となり、達成感やチームの一体感を強化することができます。マネジメント層がメンバーの成果や過程について直接伝える機会としても効果的であり、社員のモチベーション維持に役立つでしょう。また、次のプロジェクトに向けた士気の向上にもつながります。
心理的安全性の向上
仕事上では話しづらいことも、くだけた場での交流を通じて話しやすくなり、心理的な壁が取り除かれることがあります。オープンな関係性になることで、日々の業務においても意見が言いやすい風土づくりにつながるため、上下関係や部署間の垣根を越えた信頼関係を築く場として、懇親会の価値は非常に高いです。
幹事に求められるスキル

幹事は裏方業務と思われがちですが、実際には社内の連携を支える非常に重要な役割です。以下のようなスキルが発揮されることで、評価や信頼を得られるでしょう。
懇親会の幹事のスキルは、幹事自身のキャリアにおいてもプラスに働く可能性があります。イベントの成功だけでなく、懇親会で培った信頼関係や経験が、社内での立場向上にもつながるでしょう。
| スキル | 詳細 |
| 企画力 | 懇親会を開催する目的を明確化し、目的に応じた企画を考案する |
| 部署や上司との調整力 | 関係部署と日程や業務の擦り合わせをし、上司に予算や企画内容の了承を得る |
| スケジュール管理能力 | 複数人のスケジュールを調整して日程を決定した上で、「いつまでに」「何をすべきか」を明確にして遂行する |
| 情報整理と発信力 | 会場情報や当日のスケジュールなど必要な情報をわかりやすく整理して、参加者に案内する |
| リスクマネジメント | 当日起こり得るトラブルを懇親会前に想定し、対策を立てる |
| トラブル対応力 | 突発的な問題を冷静に対処する |
| 気配りや観察力 | 場の空気を読んで、全体の満足度が上がるように行動する |
| 組織横断的な視点 | 周りを巻き込み、部署や立場を越えて関係を構築する |
懇親会の準備チェックリスト

懇親会の企画から実施までには、さまざまな準備が必要です。以下のステップに沿って進めることで、円滑な運営が可能になります。
- 懇親会を開催する目的の明確化と社内共有
- 対象者・参加人数の確認と出欠の見込み調査
- 日程調整(社内カレンダー、アンケートツールを活用)
- 会場の選定と仮予約
- 社内での稟議申請、予算確保
- イベント内容の設計と役割分担
- 社内告知・出欠リマインド(メール、チャットツールを活用)
- 当日の運営(司会進行・受付・写真撮影・トラブル対応準備など)
- 終了後のアンケート、お礼の連絡、精算処理・報告
この一連の流れを把握しておくことで、幹事業務を体系的に進められます。
出欠確認・管理に役立つツール5選

出欠確認や管理に役立つツールを、おすすめポイントと併せて5選紹介します。
- Googleフォーム:自由記述や選択肢も設定でき、集計も自動化可能です。
- 調整さん:複数候補日からの出欠回答に便利で、操作がシンプルです。
- LINEオープンチャット:気軽なコミュニケーションやリマインドにも活用できます。
- Notion:懇親会の目的、進行表、TODOリストなどを一元管理できます。
- Googleスプレッドシート:参加者リスト、費用管理、進行表の共有に適しています。
懇親会の会場を選ぶ際のポイント

参加者の負担を軽減するため、会社から近い場所や駅から徒歩圏内の立地が望ましいです。会社から近いと終業後にすぐ参加しやすくなります。雨天時や悪天候でもアクセスしやすい立地か、公共交通機関で帰宅しやすいかも考慮しましょう。
雰囲気と清潔感
参加者がリラックスして過ごせるよう、落ち着いた雰囲気と清潔感のある内装が整っている会場を選びましょう。カジュアルすぎず、かといって堅苦しくない絶妙な空間が求められます。
個室・貸切の可否
プログラム中に上司の挨拶があったり、ゲームや発表などのコンテンツを実施したりする場合は、声を張ったりマイクを使用することで他の利用客に迷惑をかける恐れがあるため、個室や貸切の空間があると安心です。
設備の有無
イベント中の進行に必要な機材が利用可能か確認しておきましょう。マイクといった基本的な設備の他に、映像を投影したプログラムがある場合は、音響設備の種類やプロジェクター、スクリーンのサイズをチェックし、当日不備がないよう念入りに準備しましょう。電源タップの有無も事前にチェックすることが重要です。
食事の対応
また、提供される料理がバイキング形式や共有皿の場合は、アレルギー食材の混入や誤食を防ぐため、メニュー表示を明確にし、個別対応が必要な場合は別盛りにするなどの工夫も大切です。調味料や出汁に含まれる成分についても注意が必要なケースがあるため、会場やケータリング業者と事前に詳細を共有し、柔軟に対応できる体制を整えておきましょう。
懇親会の予算・社内調整

ここからは、懇親会の予算・社内調整について紹介します。
予算の目安
一般的な懇親会の場合は、一人当たり〜5000円程度が平均的な予算帯です。補助の有無によって会場の選択肢やコンテンツの幅が変わってきますので注意が必要です。
経費精算における注意点
懇親会の費用を会社で負担する場合、領収書の記載内容や提出期限など、経費処理ルールに則って対応する必要があります。懇親会の形態によって勘定科目が変わるため、補助される額も変動します。会計担当と事前に連携し、不備が出ないよう注意しましょう。
| 飲食の形態 | 対象 | 参加者 | 勘定科目 | 条件 |
| 社内全体での懇親会 | 全社員 | 全社員、一部社員 | 福利厚生費 | 現金支給でないこと、社会通念上の額であること(1人5,000円目安) |
| 業務にまつわる会議中の軽食、ランチミーティングなど | 会議の参加者 | 会議の参加者 | 会議費 | 業務上必要であり、内容・金額が妥当であること(1人3,000円目安) |
| 社内の一部だけでの飲み会、社外の人と飲食 | 一部社員、社外の人も含む関係者 | 一部社員、社内外の関係者 | 交際費 | 社内外との関係維持・構築が目的であること。飲食の内容・金額が社会通念上妥当であること(1人5,000〜10,000円目安)
|
参考:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
キャンセル対応と予備費
急な欠席や当日キャンセルが出ることを想定し、キャンセル料が発生する時期や金額を事前に設定し、周知しておくことが大切です。また、予期せぬ追加費用が出た際に備え、少額でも予備費を確保しておくと安心です。
社内調整のコツ
懇親会の企画書や稟議書を作成する際は、「目的」「期待される効果」「金額の根拠(人数×単価)」を明確にし、承認を得やすい形で提出しましょう。過去実績やアンケート結果を添付するのも効果的です。
懇親会へ若手社員の参加を促すポイント

ここからは、若手社員に積極的に参加してもらえるように促すポイントを紹介します。
飲み会離れへの対応
社員の中には、ライフワークバランスを重視し、仕事後のプライベート時間を確保したい人も多くいるでしょう。ランチ懇親会や、出勤日を一日使っての大型イベント懇親会など、プライベートに配慮した構成にするのもおすすめです。飲み会の場合は「お酒を飲まなくても楽しめる懇親会」であることを事前に明示し、心理的な参加ハードルを下げる工夫が必要です。中には、飲酒している上司とのコミュニケーションを敬遠する社員もいるでしょう。飲酒することで、双方向的なコミュニケーションが難しくなる場合もあります。一方的なコミュニケーションが生まれないように一律で、ノンアルコールにすることも視野に入れましょう。
参加しやすい雰囲気づくり
懇親会の雰囲気が堅苦しくなりすぎると、特に若手や新入社員にとっては心理的な壁になります。幹事は、自由に席を移動できる立食形式を検討したり、「次に来た人と一言話してから座る」といった軽いアイスブレイクを取り入れたり、「簡単にグループ化して、時間ごとに入れ替える」など、横断した交流を促すことで、会話が自然に生まれる空間を設計することができます。また、司会者がユーモアを交えた進行を心がけると、緊張感がほぐれます。
多様なコンテンツの導入
食事と歓談だけでは場が間延びすることがあります。若手社員も楽しめるような工夫として、以下のようなコンテンツを取り入れると効果的です。
- スマートフォンを活用したオンラインビンゴやリアルタイム投票ゲーム
- 「もしも動物になるなら?」「理想の休日は?」など架空設定でゆるく答えるランキング形式の投票企画
- ミニ謎解きやクイズ大会(部署対抗戦など)
- チームに分かれて行う「ジェスチャーゲーム」や「お絵描き伝言ゲーム」
これらは特別な道具が不要で導入しやすく、短時間でも十分盛り上がるため、幹事にとっても準備負担が少ないのが特徴です。内容としては、「価値観はなんとなくわかるが、過度に自己開示の必要がない」設計にすると、若手社員の抵抗感も少なく楽しんでもらえることが期待できます。
懇親会のリスク対策

ここからは、懇親会で発生する可能性のあるトラブル対策について紹介します。
飲酒に関するリスク管理
飲みすぎによる体調不良やトラブルを防ぐために、アルコールの提供方法や量をコントロールすることが重要です。中には、飲酒することで、双方向的なコミュニケーションが難しくなる場合もあり、飲酒している上司とのコミュニケーションを敬遠する社員もいるでしょう。一方的なコミュニケーションが生まれないように一律で、ノンアルコールにすることも視野に入れましょう。
ハラスメントの予防
飲み会の場ではセクハラやパワハラが起きやすくなる傾向があります。幹事として、配席や会話内容にも気を配ることが求められます。万が一トラブルが起きた場合の対応フローも確認しましょう。パワハラが起こった場合の対応フローについて、厚生労働省告示第五号に明記されています。
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- により、職場におけるパワーハラスメントかの事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
- により、職場におけるパワーハラスメントの事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- 改めて、職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発するなどの再発防止に向けた措置を講ずること。 なお、職場におけるパワーハラスメントの事実が確認できなかった場合においても、 同様の措置を講ずること。
参考:厚生労働省|事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上構図べき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第五号)(PDF)
急病や体調不良時の対応
懇親会の最中に体調不良を訴える参加者が出た場合に備え、救急連絡先や最寄りの医療機関を調べておくと安心です。必要に応じて保険証の持参を呼びかけるのもよいでしょう。
天候トラブル(屋外開催時)の備え
屋外イベントの場合は、悪天候時の中止・延期判断基準と代替案を事前に用意しておく必要があります。急な天候変化にも対応できるよう、テントや室内スペースを併設できる会場が理想です。
写真撮影・SNS投稿の配慮
写真の撮影やSNSへの投稿については、あらかじめ参加者に確認を取りましょう。顔がはっきり写る写真は特に注意が必要で、掲載許可を得ていない写真を外部に公開することは避け、会社の広報方針やプライバシー保護の観点を踏まえ、必要に応じて撮影範囲や使用目的を明示しておくと安心です。
懇親会の事後対応

ここからは、懇親会の事後対応について紹介します。
当日の様子を共有する
当日の様子を写真やレポートにまとめて社内に共有することで、懇親会の効果を可視化し、他部署にも波及させることができます。共有する際には撮影可否に配慮し、参加者の表情がよく写った写真を選ぶことが大切です。
アンケートによる振り返り
懇親会の満足度や改善点を把握するために、参加者アンケートが有効です。Googleフォームなどを使って簡易に実施し、「良かった点」「改善点」「また参加したいか」などを尋ねましょう。設問はシンプルに絞り、回答しやすい内容にすることで、集計・分析もしやすくなります。次回の企画に活かすヒントが得られるはずです。
次回につながる情報整理
開催履歴や参加率、人気のあったコンテンツなどの情報は記録に残しておくことで、次回以降の企画に活かせます。次回の幹事や他チームの担当者にスムーズに引き継げるように、チェックリスト化や社内マニュアルとしてまとめておきましょう。会社全体のノウハウとして活用できる社内資産になります。
懇親会に“あそび”を取り入れるメリット

ここからは、懇親会に“あそび”の要素を取り入れるメリットを紹介します。
笑いがもたらす心理的効果
笑うことは、ストレスを軽減し、心身のリラックスを促すとともに、相手への信頼感や親近感を高める効果があるとされています。懇親会にユーモアや「あそび」の要素を取り入れることで、日常の業務で生じがちな緊張感がやわらぎ、フラットな関係性が築きやすくなります。また、笑いを共有する体験は、その場の一体感を生み出し、チームの結束力を高める効果も期待できます。仕事以外の側面で人となりが見えることで、互いの理解が深まり、日常のコミュニケーションも円滑になります。
“あそび”の力で関係性が変わる
役職に関係なく、同じルールで一緒に楽しめるゲームやクイズは、関係性を一気に近づける力を持っています。特に、チーム対抗型や協力型のゲームは、自然と連帯感が生まれ、日常業務では見えにくい個性や強みが垣間見える場にもなります。“あそび”を通して築かれる関係は、上下や壁を越えたフラットなつながりを生み、日常のコミュニケーションにも良い影響を与えるでしょう。
形式にとらわれない発想
ゲームをすることだけが“あそび”ではありません。ユーモラスな司会進行、仮装やドレスコード、くじ引き、ちょっとしたプレゼントなど、ささやかな工夫でも十分に「あそび心」を演出できます。形式にとらわれない発想が懇親会を特別なものにし、参加者の気持ちをほぐすでしょう。“まじめすぎない場”づくりが、上下関係や部署の垣根を越えた対話を促し、組織の風通しをよくするきっかけに繋がります。
非言語コミュニケーションの大切さ
すべての人が会話を得意としているわけではありません。懇親会では、雑談が苦手な人、言葉でのやりとりに気疲れしてしまう人たちにも安心して参加してもらえるよう、非言語的なコミュニケーションの工夫が大切です。たとえば、共通の作業を伴うワークショップ形式や、ボードゲームなどは、言葉が少なくても自然に関わり合えるきっかけになります。言葉に頼らない交流の場があることで、無理せずその場にいられる空気が生まれ、真の「誰もが参加しやすい懇親会」に近づけるでしょう。
体験型の仕掛けを取り入れる
一緒に絵を描く、組み立て作業をする、軽く身体を動かすアクティビティなど、言葉を使わずに共有できる体験型の仕掛けは、参加者同士の距離を自然に縮めてくれます。会話が得意でない人でも無理なく関われる点が魅力で、共同作業を通じて相手の人柄や思考のクセが垣間見えることも。懇親会にこうした体験を取り入れることで、場の空気「参加する」から「一緒に楽しむ」雰囲気へと変わり、より深い信頼関係の構築につながります。
懇親会が“あそび”で盛り上がる!おすすめの企画例5選
ここからは、“あそび”の要素を取り入れた企画例を紹介します。
格付けバトル
格付けバトルは、高級品と一般品を見分ける「格付けチェック」をチームで競い合う、体験型のレクリエーション企画です。ワインや紅茶、アートなどの複数のジャンルで、高級品と一般品を見分ける体験型クイズを、チームで協力しながら楽しめます。「知識」よりも「感覚」で反応できる内容なので、話すのが得意でない人も含めて、誰でも気軽にその場に参加でき、会話が生まれやすく、ランキング形式の結果発表で盛り上がりも自然と高まります。
【開催事例】「格付けバトル」
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
ゴチバトル
ゴチバトルは、懇親会の食事そのものがゲームになる企画です。高級料理を味わいながらその合計金額をチームで予想する、体験型のゲームです。まるでバラエティ番組のような盛り上がりが楽しめます。料理は一流シェフ監修の本格派で、食とゲームの両方を堪能できるのが魅力。自然な会話が生まれ、チームの連携やコミュニケーション活性化にもつながります。
【開催事例】「ゴチバトル」
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀を使って、相手の腕につけられた“命(いのち)”を落とし合うチーム対抗戦のゲームです。シンプルなルールで、年齢や運動の得意・不得意に関係なく楽しめます。チームで作戦を立てて協力しながら進めるため、自然とコミュニケーションが生まれ、チームビルディングにも最適です。
【開催事例】「チャンバラ合戦」
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームは、制限時間内に謎を解き、脱出を目指す没入型の体験ゲームで、参加者同士が自然と協力・対話する流れが生まれる設計になっています。会議室などで行うオフライン型のほか、オンライン開催も可能で、規模や場所を問わず柔軟に実施できるのが魅力です。非日常のシチュエーションに引き込まれることで、普段見えない一面やチームワークの強さが発見できる場にもなります。
【開催事例】「謎解き脱出ゲーム」
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
戦国運動会
戦国運動会は、戦国時代をテーマにしたユニークな競技です。チームで協力しながら戦うことで自然と一体感が生まれます。運動が苦手な人も楽しめる種目構成で、誰でも活躍できるのが魅力。非日常の世界観に没入することで記憶にも残りやすく、世代や部署を超えた交流のきっかけになります。楽しみながらチームワークと組織の結束力を高めたい場面にぴったりの企画です。
【開催事例】「戦国運動会」
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
まとめ

懇親会は、いつもとちょっと違う形で社員と向き合える大切な機会です。社員の立場や気持ちに寄り添い配慮しながら、“あそび”のある懇親会にすることで、自然なつながりや信頼が生まれやすくなります。幹事という役割には、場づくりの面白さも詰まっています。本マニュアルを活用しながら、あなたらしい工夫を加え、温かく実りある懇親会を実現してください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る