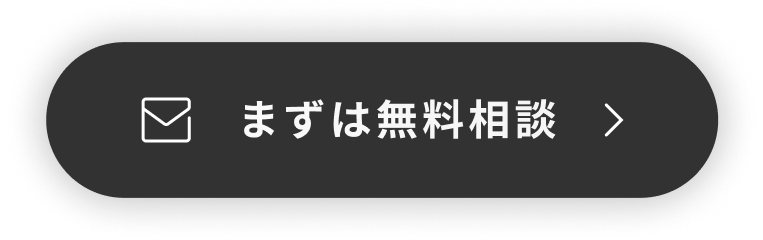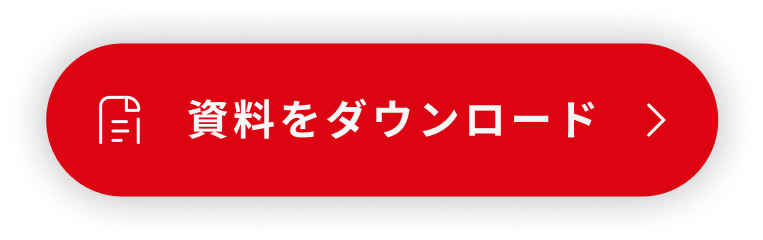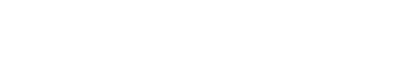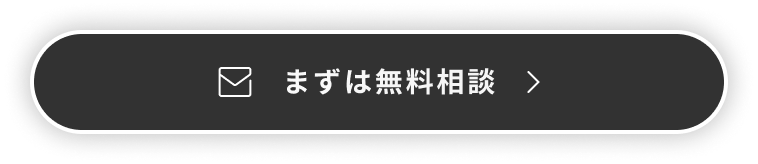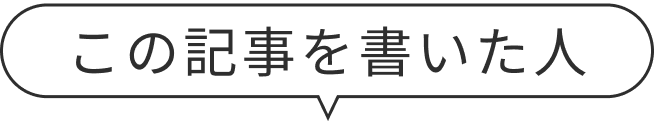防災イベントとは?開催するまでの流れやおすすめの企画アイデアを紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年9月2日



目次
防災イベントとは、地震や水害などの災害に備えるために、参加者が主体的に防災を考えるきっかけをつくる取り組みのことです。近年は従来の避難訓練に加え、ゲームやワークショップを取り入れた体験型のイベントが広く注目されています。災害はいつどこで発生するか予測できないからこそ、地域や会社を問わず、事前の備えが欠かせません。
本記事では、防災イベントの概要や開催するメリット、開催までの流れ、さらに参加者が関心を持ちやすい企画アイデアまでを幅広く解説します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
防災イベントとは

防災イベントとは、地震や水害、火災などの災害を想定し、参加者が防災に関する知識や行動を体験的に学ぶ取り組みのことです。従来は避難訓練や講義が中心でしたが、近年ではゲームやワークショップを取り入れた「体験型プログラム」が広がりつつあります。
その背景には、知識を身につけるだけでは防災意識が定着しにくいという課題があります。資料や講話で理解できても、実際に災害が発生した際に行動に移せるとは限りません。そのため、参加者が主体的に考え、体を動かす体験を通じて学ぶことが重視されています。
防災イベントを実施するメリット

防災イベントは、単なる訓練にとどまらず、地域や会社に多くの効果をもたらします。ここでは主催者・参加者の双方にとっての代表的なメリットを4つ紹介します。
- 知識が定着し、防災意識を自分ごととして捉えられる
- 災害時に役立つ実践的なスキルが身につく
- 地域や組織のつながりが強まる
- 主催者のPRや社会貢献にもつながる
知識が定着し、防災意識を自分ごととして捉えられる
配布資料や講義を聞くだけでは、「知っている」にとどまり、行動につながらないことが少なくありません。防災イベントでは、クイズや謎解き、シミュレーションなどに参加することで、学習した内容が体験と結びつき、記憶に残りやすくなります。
たとえば「非常食を実際に試食する」体験をすれば、どの製品が自分や家族に合うのかを考えるきっかけとなり、備蓄の見直しにつながるでしょう。体験を通じて「やらなければならないこと」から「自分のためにやっておきたいこと」へと意識が変わる点は、防災イベントならではのメリットです。
災害時に役立つ実践的なスキルが身につく
防災の知識を持っていても、災害発生時に実際に活かせなければ意味がありません。防災イベントでは、水消火器を用いた初期消火訓練や、止血・心肺蘇生といった応急手当、ロープワークや段ボールベッドの組み立てなどを体験できます。
たとえば「AEDの操作方法」を知っている人は多くても、実際に使った経験がある人は限られます。イベントで操作を練習しておけば、「知っている」から「できる」へと変わり、災害現場や職場で突然対応を迫られた際にも冷静に対応できるでしょう。
地域や組織のつながりが強まる
災害時には、公的な支援がすぐに届かない場合も多く、住民同士や社員同士による「共助」が欠かせません。防災イベントでは、普段はあまり接点のない人同士が協力して課題を解決することで、自然と信頼関係が生まれます。
地域で防災イベントを実施すると、自治会・学校・商店街といった多様な主体が顔を合わせる機会となり、防災ネットワークの構築につながるでしょう。会社で実施する場合でも、部署を越えた協力を通じてチームワークが強化され、災害時の初動対応がスムーズになります。
主催者のPRや社会貢献にもつながる
会社や商業施設が防災イベントを実施する場合、その取り組みは地域住民の安全に貢献する姿勢として評価されます。「社会に貢献している」と評価されることでブランド価値が高まり、長期的な信頼構築につながるでしょう。
一方、地域住民にとっては楽しみながら防災教育を学べる機会となります。結果として、主催者と地域の双方にメリットが生まれ、地域全体の防災力が向上します。
防災イベントを開催するまでの流れ
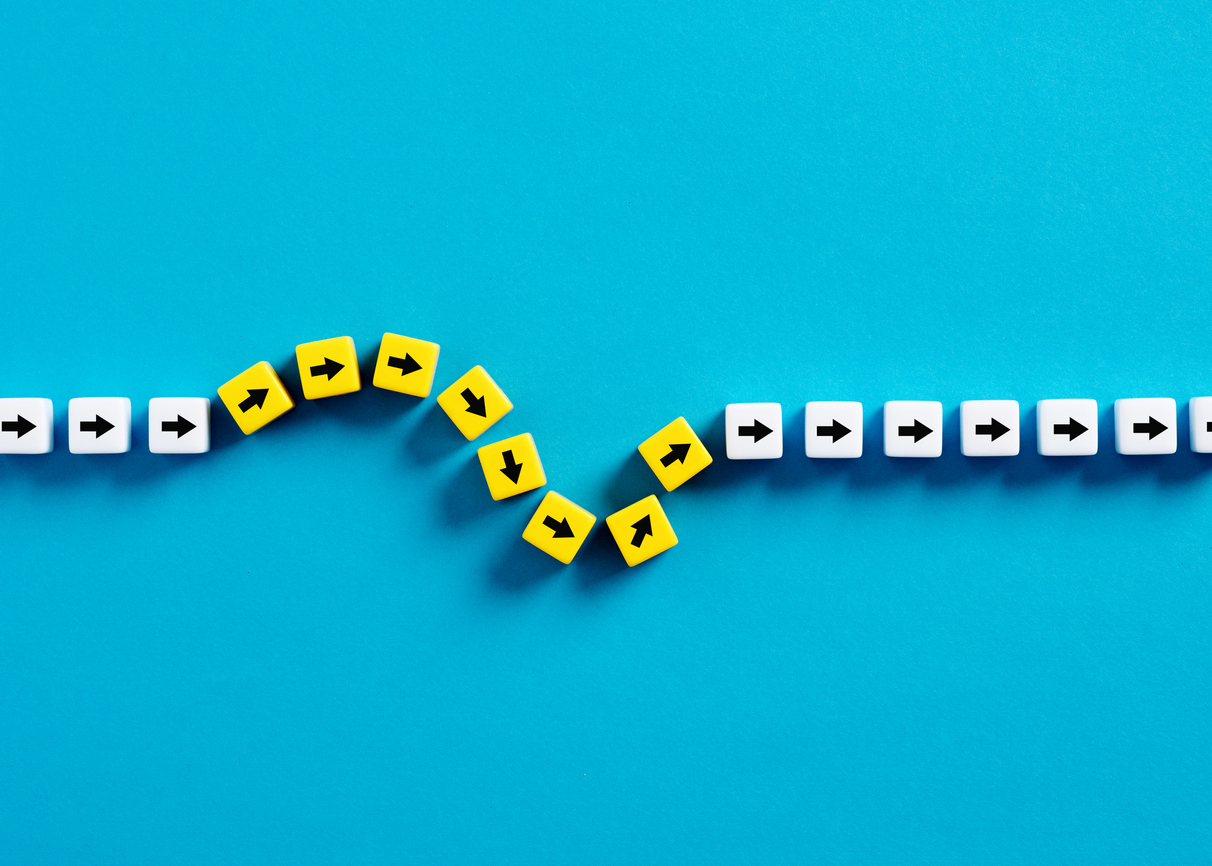
防災イベントは、場当たり的に実施するのではなく、目的の整理から当日の運営体制づくりまでを計画的に進める必要があります。ここでは、計画から当日までの一連の流れを7つの段階に分けて解説します。
- ターゲットとゴールを設定する
- コンセプトと中心となる「体験」を決める
- プログラム内容とタイムスケジュールを作成する
- 会場を選定する
- 必要な備品を用意する
- 集客・告知を行う
- 運営マニュアルを作成・共有する
段階ごとに意識すべきポイントを押さえておけば、トラブルを防ぎやすくなり、参加者にとって有意義な体験を提供できます。
1.ターゲットとゴールを設定する
最初に行うべきは「誰に参加してもらい、どのような変化を期待するのか」を明確にすることです。
【ターゲットとゴールの例】
| ターゲット | ゴールの例 |
| 小学生とその保護者 | 家庭での備蓄や避難所への関心を高める |
| 社員 | 安否確認や初動対応の知識を身につける |
ゴールが定まれば、その後のプログラム設計や告知方法も自ずと決まっていきます。ゴールを設定する際は、成果が具体的にイメージできるように決めることが大切です。
2.コンセプトと中心となる「体験」を決める
次にイベントの核となる「コンセプト」を決定します。コンセプトは単なるタイトルではなく、「参加者にどのような価値や考えなどを持ち帰ってもらうか」を示す指針です。コンセプトが定まることで、防災イベント全体に統一感が生まれ、参加者の印象に残りやすくなります。
たとえば「親子で挑戦!防災チャレンジ」というコンセプトを設定すれば、体験型ゲームや親子で協力するプログラムが中心となります。一方「会社の研修としての災害対応力強化」であれば、コンセンサスゲームや避難シミュレーションなど判断力を養う内容がおすすめです。
3.プログラム内容とタイムスケジュールを作成する
コンセプトが決まったら、次は複数のプログラムをどのように組み合わせるかを検討します。体験型・ワークショップ・講話などをバランスよく取り入れると、参加者の集中力が続きやすいでしょう。
たとえば半日イベントなら、開会式で目的を共有し、午前中に体験型プログラムを配置、休憩を挟んでワークショップを行い、最後に振り返りとアンケートで締めくくる流れがおすすめです。
例:タイムスケジュール(半日開催の場合)
| 時間 | プログラム |
| 10:00〜10:15 | 開会式・オリエンテーション |
| 10:15〜11:00 | メインプログラム(体験型) |
| 11:00〜11:15 | 休憩 |
| 11:15〜12:00 | ワークショップ |
| 12:00〜12:15 | 振り返り・閉会式 |
当日の進行をスムーズにするためにも、プログラムごとの所要時間を細かく設定しておきましょう。
4.会場を選定する
プログラム内容を決めたら、それを行える会場を選定します。屋内であれば天候の影響を受けず、映像機材の活用も容易ですが、起震車や炊き出し訓練など大規模な体験は難しい場合があります。屋外であればダイナミックな企画が可能ですが、雨天時の代替案を準備しておく必要があります。
また、電源の有無、トイレや水道の位置、駐車場やアクセスの利便性なども事前に確認しておくと、当日のトラブルを防げます。
5.必要な備品を用意する
備品の準備は見落としが起こりやすいポイントです。受付で必要な名簿や筆記用具、マイクやスピーカーなどの基本機材に加え、プログラムごとに必要となる備品も用意しましょう。備品リストを作成して進捗を確認することで、抜け漏れを防止できます。
6.集客・告知を行う
準備が整ったら、対象者に確実に届く方法で告知を行います。地域住民向けなら回覧板や自治体の広報誌、社員向けなら社内メールや掲示板、ファミリー層には学校やSNS広告など、対象に応じて手段を組み合わせましょう。
告知では「参加無料」「親子で楽しめる」「景品あり」などのメリットを具体的に示すと、ターゲットの参加意欲を高めやすくなります。
7.運営マニュアルを作成・共有する
最後に、スタッフが迷わず行動できるように運営マニュアルを作成します。全体統括、受付、プログラム担当、誘導、安全管理、救護など役割を明確に分け、それぞれの具体的な行動をマニュアルにまとめます。あわせて、連絡手段や緊急時の対応手順も記載しておきましょう。
さらに、本番前に必ずリハーサルを行い、スタッフ同士で動きを確認しておけば、当日の不測の事態にも落ち着いて対応できるでしょう。
住民や社員が夢中になる防災イベントアイデア9選

防災イベントを初めて開催する際は、従来型の訓練や講話だけでは参加者の関心を十分に引きつけられないことがあります。そのような場合は、体験性や楽しさを取り入れたプログラムを組み込むことがおすすめです。ここでは、住民や社員が夢中になる9つの防災イベントアイデアを紹介します。
| 防災イベントアイデア | 概要 |
| 防災謎解き | 災害をテーマにしたストーリーの中で、チームで謎を解きながら学ぶ体験型プログラム |
| 防災コンセンサスゲーム | 災害時の行動として「何が最も適切か」をグループで議論し合意形成を行うプログラム |
| 防災カードゲーム「シャッフル」 | 応急手当や紙食器の折り方など12種類以上の防災知識をカードで学べるゲーム |
| 防災運動会 | 運動会の競技に防災要素を組み込んだ体験型イベント |
| 防災ヒーロー入団試験 | 子どもが「防災ヒーロー」を目指して複数のミッションに挑戦するプログラム |
| 水害サバイバル | 洪水や豪雨災害をテーマにしたボードゲーム型プログラム |
| 起震車による地震体験 | 震度5強〜7クラスの揺れを再現する車両を使い、実際の地震を体感するプログラム |
| 水消火器の体験 | 中身が水の消火器を使い、火に見立てた的に放水する訓練 |
| 炊き出し訓練 | 災害時に避難所などで温かい食事を提供できるよう、限られた資源で調理を行う訓練 |
ゲーム・クイズ形式で「知識」を楽しく学ぶアイデア3選
座学では理解しにくい内容も、ゲームやクイズを通じて学ぶことで記憶に残りやすくなります。チーム形式にすれば交流も生まれ、子どもから大人まで幅広い層が楽しめます。
ここでは、ゲーム・クイズ形式で「知識」を楽しく学ぶアイデアを3つご紹介します。
- 防災謎解き
- 防災コンセンサスゲーム
- 防災カードゲーム「シャッフル」
防災謎解き
防災謎解きは、災害をテーマにしたストーリーの中で、参加者がチームを組んで謎を解いていくアクティビティです。次々と現れる課題を解決していくなかで、自然に防災知識や判断力が身につきます。
最大の特徴は「楽しさ」と「学び」を両立できる点にあります。単に知識を詰め込むのではなく、謎解きに没頭しているうちに災害時の行動を理解できるため、子どもから大人まで熱中できます。さらに、協力して謎を解いたときの達成感は強く記憶に残り、「また挑戦したい」と思うでしょう。
学校の授業や地域イベント、会社の研修まで、さまざまな場面で活用できる企画です。
⇒防災謎解きを実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
防災コンセンサスゲーム
防災コンセンサスゲームは、災害時に「どのような行動を取るべきか」をグループで話し合い、合意形成を図る体験型プログラムのことです。現実に起こるかもしれないシナリオをもとに、限られた情報や物資をどう扱うかを話し合います。参加者はお互いの意見を聞き、意見を擦り合わせながら一つの答えを導き出すため、防災の理解を深めると同時に、判断力・協調性・優先順位付けの力を養うことが可能です。
なかでも、「帰宅困難サバイバル」が特におすすめです。帰宅困難サバイバルは大地震などで交通が麻痺し、自宅に帰れない状況を想定したシミュレーションゲームです。参加者は「自分の身に実際に起こったらどう行動するか」を真剣に考えるなかで、災害が身近に感じられ、現実感のある学びにつながります。さらに、地域の特性に合わせて内容をカスタマイズできるため、実際の災害対応にも役立つ実践的なプログラムです。
⇒防災コンセンサスゲームを実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
防災カードゲーム「シャッフル」
防災カードゲーム「シャッフル」とは、災害時に役立つ知識や技術をカードを通じて楽しく学べる教育型ゲームのことです。カードには「応急手当」「紙食器の折り方」「災害用伝言ダイヤルのかけ方」など12種類以上のテーマが描かれており、遊びながら学べる工夫が詰まっています。
大きな特徴は、繰り返し遊ぶうちに自然と知識が定着することです。ルールがシンプルで可愛らしいイラストも添えられているため、子どもでも取り組みやすく、家族や地域住民同士で盛り上がることができます。ファミリー向けのイベントや学校教育に導入すれば、防災イベントを「楽しい体験」として記憶に残せるでしょう。
ワークショップ形式で「実践スキル」を身につけるアイデア3選
実際に体を動かし、手を使って学ぶことで、防災に関する知識は定着しやすくなります。ワークショップは「知っている」から「できる」に変える効果的な手段です。
ここでは、ワークショップ形式で「実践スキル」を身につけるアイデアを3つご紹介します。
- 防災運動会
- 防災ヒーロー入団試験
- 水害サバイバル
防災運動会
防災運動会とは、運動会の競技に防災要素を組み込み、楽しみながら災害対応を学ぶプログラムのことです。毛布を担架代わりにして人を運ぶリレーや、防災用品を使った借り物競走など、遊び感覚で実際の行動を体験できます。
ゲーム性の高さに加え、災害時に取るべき行動が自然に理解できる仕組みが魅力です。運動会ならではの一体感や競争の楽しさがあるため、子どもから大人まで夢中になれます。
⇒防災運動会を実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
防災ヒーロー入団試験
防災ヒーロー入団試験とは、「防災ヒーロー」を目指して複数のミッションに挑戦する、子どもを対象とした体験型プログラムのことです。水消火器を使った射的や非常持ち出し品の間違い探しなど、子どもが楽しめる工夫を凝らした課題が用意されています。
一つひとつのミッションを突破していく達成感があり、最後に「認定証」を手にした瞬間には大きな誇りを感じられるでしょう。親子で一緒に取り組めるため、家庭で防災について話し合うきっかけにもなります。
⇒防災ヒーロー入団試験を実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
水害サバイバル
水害サバイバルとは、洪水や豪雨災害などをテーマにしたボードゲーム型の体験プログラムのことです。プレイヤーは街の住民となり、迫りくる水害から避難を試み、情報交換や協力を通じて生き残りを目指します。各プレイヤーには異なる達成条件があり、ゲーム終了時点まで生き残り、自分が達成すべき条件をクリアしていれば勝利となります。
時間が刻々と過ぎる中で意思決定を迫られるスリルは、参加者を引き込みます。同時に「一人では助からない」「共助が欠かせない」という現実を体感できる点も大きな特徴です。
⇒水害サバイバルを実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
五感で感じる「リアルな体験」ができるアイデア3選
災害を擬似体験することは、防災の必要性を理解するうえで非常に効果的です。五感を通じた体験は、参加者の記憶に残りやすくなります。
起震車による地震体験
起震車による地震体験は、震度5強〜7クラスの揺れを再現できる専用車両を用いて、地震の恐ろしさを体感するプログラムのことです。
体験者の多くが「想像以上に動けなかった」と口を揃えるほど、実際の揺れは強烈な印象を残します。机の下に潜る、頭を守るといった基本動作を身体で覚えられるため、机上の知識を実際の行動へと結びつけやすくなります。
水消火器の体験
水消火器を使った体験では、中身を水にした消火器を実際に操作し、火に見立てた的に放水します。「ピンを抜く」「ホースを向ける」「レバーを握る」という一連の動作を実際に経験することで、初めて本当に使えるようになります。射的感覚で行えるため子どもも楽しく参加しやすく、体験を通じて初期消火の重要性を実感することが可能です。
炊き出し訓練
炊き出し訓練とは、災害時に避難所などで温かい食事を提供できるよう、限られた資源で調理を行う訓練です。
災害時に温かい食事は心の支えになります。電気や水道が使えない状況を想定し、LPガスや非常用炊飯袋を活用しながら、限られた資源で安全に食事を用意する方法を学びます。調理を協力して進める過程で、食の大切さや助け合いの重要性を同時に実感できる点が魅力です。
防災イベントを成功に導く3つのポイント

防災イベントを計画的に進めても、参加者が十分な学びや満足感を得られなければ、効果は限定的になります。ここでは、防災イベントを実施する際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
- 参加者が主体的に取り組める体験を重視する
- 学びと楽しさのバランスを取る
- 最新の災害事例や地域の特性を反映させる
これらのポイントを意識すれば、参加者の理解が深まり、継続的な取り組みへとつなげやすくなります。
参加者が主体的に取り組める体験を重視する
防災イベントで最も大切なのは、参加者が受け身にならず、主体的に行動しながら学べる場を作ることです。講義や説明だけが中心になると集中が途切れやすく、学びも定着しにくくなります。
そこでおすすめなのが、クイズやワークショップ、グループディスカッションなどの体験型プログラムです。自分の判断が結果に影響を与えたり、仲間と意見を交わしたりする過程を通じて、防災を「自分ごと」として捉えられるようになります。
学びと楽しさのバランスを取る
幅広い層に参加してもらうためには、楽しさと真剣な学びの両方を取り入れた構成が欠かせません。楽しさに偏れば啓発効果が薄れてしまい、逆に真面目な内容が中心となると参加意欲が高まりにくいからです。
たとえば、イベントの序盤はゲーム性のあるプログラムで関心を引き、中盤以降には応急手当や避難行動といった実践的なスキルを学ぶ体験を組み込むと効果的です。最後に専門家の短い講話を加えれば、楽しみながらも深い学びを得られる充実した防災イベントになります。
最新の災害事例や地域の特性を反映させる
防災に関する知識や対策は日々進化しており、また地域によっても重視すべきリスクは異なります。さらに、古い事例や汎用的な説明だけでは説得力に欠け、参加者の行動につながりにくい場合もあります。
そこで重要なのが、防災イベントに最新の情報や地域特性を取り入れる工夫です。たとえば、気象庁や自治体が公表している最新のハザードマップを活用したり、その地域で実際に起きた災害を題材にしたクイズを取り入れたりすることで、学びがより現実的になり、参加者の記憶にも残りやすくなります。
防災イベントに関するよくある質問

ここでは、防災イベントを企画する際によく寄せられる質問と、その回答をまとめました。
防災イベントの開催に適した時期はいつですか?
9月1日の「防災の日」を含む「防災週間」(8月30日〜9月5日)に実施されることが多いです。この時期はニュースや地域の取り組みも重なるため、自然と参加者の防災への関心が高まりやすくなります。また、阪神・淡路大震災が発生した1月17日前後の「防災とボランティア週間」(1月15日〜1月21日)も、防災意識を高めるタイミングとして適しています。
予算が限られていても実施できるアイデアはありますか?
はい、可能です。消防署や自治体に協力を依頼すれば、職員派遣や備品の貸し出しを受けられる場合があります。また、新聞紙スリッパやペットボトルランタンといった工作、無料アプリを使ったクイズなど、身近な素材やツールを活用すれば、費用をかけずに十分に学びのあるイベントを実現できます。
会社の研修として実施する場合、どのような効果が期待できますか?
防災イベントを会社の研修に取り入れることで、社員の防災意識を高めるだけでなく、チームで協力する体験を通じて部署を超えた交流が生まれます。さらに、判断力やリーダーシップの育成につながり、CSR活動としての会社のイメージ向上の効果も期待できます。
まとめ

本記事では、防災イベントの概要や、実施するメリット、開催までの流れ、具体的なアイデア、成功のためのポイントまで解説しました。
防災イベントは、参加者が主体的に取り組むことで、防災を自分ごととして捉えるきっかけを提供するイベントです。知識の定着や実践的なスキルの習得に加え、地域や会社のつながりを強める効果も期待できます。開催の準備にあたっては、ターゲットと目的を明確にし、楽しさと学びを両立させながら、最新の事例や地域の特性を反映させることが重要です。
ぜひ本記事の内容をもとに、参加者の満足度が高く、記憶に残るイベントを実現してみてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る