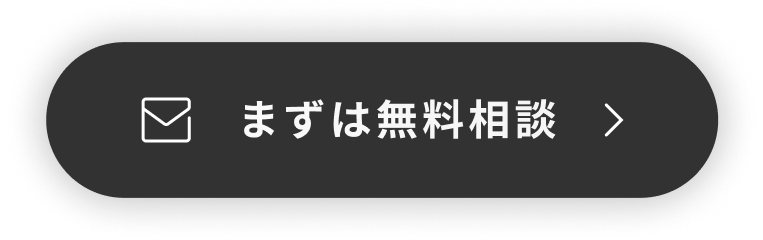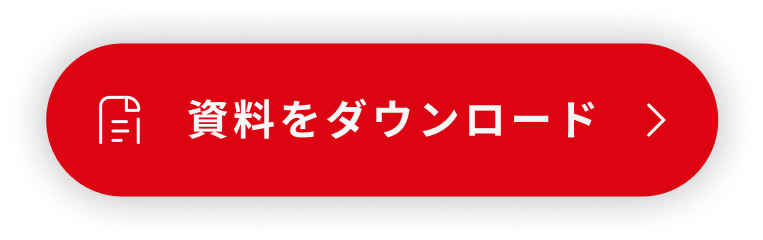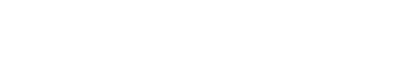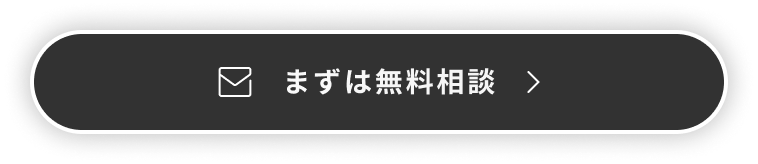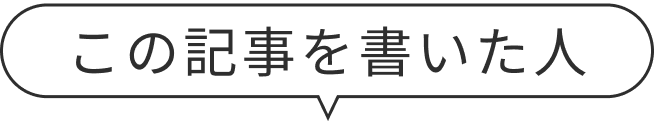歓迎会の幹事はどうすべき?準備・注意点・空気づくりのポイントを紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



歓迎会は、新たに加わった社員が職場に早くなじむための大切な交流の場です。幹事は、単に段取りをこなす役割ではなく、参加者全員が自然に会話できる雰囲気をつくるキーパーソンでもあります。
本記事では、歓迎会の幹事を任された方に向けて、企画の目的や事前に確認することのポイント、準備から当日の運営、事後対応の流れを紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
歓迎会を実施する目的

ここからは、歓迎会を実施する目的について紹介します。
社員の早期定着を促す
歓迎会は、新しく入社する社員が新しい職場で人間関係を築くための第一歩です。新しく入社する社員の不安を和らげ、早く職場へなじんでもらうためには、最初の印象づくりが非常に重要になります。たとえば、歓迎会の冒頭で、「今日は皆さんと少しでも気軽に話せる場にできればと思います」と一言添えるだけでも、場の緊張がほぐれやすくなります。あいさつの段階で温かく迎え入れる空気をつくることが大切です。緊張しなくて良い空間を作ることが、早期退職の防止にもつながるでしょう。
職場の人間関係づくりを後押しする
歓迎会は、単なる形式的な紹介にとどまらず、既存のメンバーとの信頼関係を築く場として活用できます。特に新しく入ったメンバーにとっては、部署や役職を超えた人間関係を築くきっかけとなります。たとえば「配属先に関係なく2人ずつで話す時間を設ける」といった交流を生み出す仕掛けを用意することで、普段接点の少ない人とも自然につながりやすくなります。早い段階で安心できる関係性ができると、職場へのなじみやすさにも大きく寄与します。
チーム全体の心理的安全性を高める
新しいメンバーが「安心して話せる」と感じられる場は、チーム全体の心理的安全性を高めるうえで重要です。新しく入社する社員だけでなく、既存の社員にとっても、自由に発言できるゆとりや余白が生まれ、良い関係を築きやすくなるでしょう。たとえば、歓迎会の前に先輩社員へ「ぜひ声をかけてあげてください」と一言伝えておくだけでも、関わりのきっかけが生まれやすくなります。ちょっとした声かけが、チーム全体の雰囲気づくりに大きな効果をもたらします。
歓迎会の事前準備

ここからは、歓迎会の事前準備について紹介します。
対象者の情報を把握する
歓迎会を成功させる第一歩は、「誰を歓迎するのか」を正しく理解することです。新卒か中途か、異動か、人数や年齢、部署構成、バックグラウンド(前職・出身地など)を把握することで、会の演出や進行の方向性が定まります。たとえば新卒なら同期とのつながりづくりを、中途入社なら既存社員との交流を重視するなど、工夫が必要です。必要に応じて配属先の上司や人事にヒアリングし、性格や話しやすい話題も把握しておくと、より温かい歓迎につながります。
日程を調整する
歓迎会は多くの関係者を巻き込むため、できるだけ早い段階で候補日を提示し、出欠を確認することが重要です。調整さんやGoogleフォームなどの無料ツールを活用すれば、複数日から選択できる形で効率よく調整できます。上司や歓迎会の主役の予定を優先して押さえたうえで、他の参加者にも周知しましょう。業務繁忙期や定例会議直後など、負担が大きいタイミングは避けるのがベターです。候補日を2〜3日確保しておくと、急な変更にも柔軟に対応できます。
会場を選定・予約する
会場選びは、歓迎会の雰囲気を大きく左右します。アクセスの良さはもちろん、参加者が落ち着いて会話できる「騒がしすぎない店」を選ぶことが大切です。周囲の客に迷惑をかけないよう、個室または半個室のある店舗が望ましいでしょう。予約時には「歓迎会利用」と伝えると、スタッフの協力を得やすくなる可能性が高いです。支払い方法(現金かカードか、領収書対応の可否)も事前に確認しましょう。実際に下見が可能なら、次の点も確認しましょう。
- 座席のレイアウト:交流がしやすいレイアウトになっているか、参加者が孤立しないように調整が可能か
- BGMの音量や利用者層:会話がしやすいか
- 料理の内容:コースの場合はアレルギーを持つ人向けに別メニューが用意できるか
- 飲み放題の内容:ソフトドリンクやノンアルコール飲料のバリエーション
出欠を確認・リマインドする
参加メンバーの確定は、席の配置や食事手配に直結するため、日程が決まり次第、正式な案内と出欠確認を行いましょう。メールやチャット、社内掲示など、職場で普段から使われているツールを活用すると確実です。「◯日までに回答」「返信がない場合は不参加とみなします」といった、締切とルールを明記しておくと集計がスムーズになります。返信がない場合は、個別でやんわりとリマインドしましょう。また、アレルギーや苦手な食材、当日の移動手段(車移動か否か)もあわせて確認できるとより丁寧に対応することができます。
会の進行を設計する
歓迎会の流れを事前に設計しておくことで、進行の遅延や場の間延びを防げます。基本的な構成は、「開会のあいさつ→紹介→歓談→企画→締めのあいさつ」といった流れになります。たとえば「乾杯は18:10、企画開始は19:00」といったように、時間の目安を設定し、乾杯や企画をスタートするタイミングを進行表にまとめておくと安心です。話す人の順番や所要時間、あいさつ内容も事前に共有しておきましょう。また、プログラムの進行については、すべてを自分一人で行うのではなく、副幹事や先輩社員と分担すると負担が軽減され、スムーズに運営できるでしょう。
コンテンツ・企画を準備する
初対面が多い歓迎会では軽い企画を取り入れることで場がほぐれやすくなります。おすすめは、「共通点探しビンゴ」「簡単なクイズ」「チーム対抗の2択ゲーム」など、話のきっかけになりやすいもの。全員が気軽に参加でき、準備にも手間がかからない内容にするのがポイントです。景品を用意する場合は、文房具やお菓子、コンビニ商品券など、幅広い層に喜ばれるものがおすすめ。歓迎会の主役に負担をかけないよう、主役に過度な注目が集まりすぎないような設計にすることも重要です。必要な備品は、リスト化して事前に準備しておきましょう。
案内・告知を行う
歓迎会を実施する際は、参加者への案内と告知も幹事の重要な仕事です。告知文では「日時・会場・会費・対象者(誰の歓迎会か)・出欠締切」を簡潔にまとめましょう。案内する相手が上司を含む場合や、比較的フラットな関係の相手に送る場合、さらにメールとチャットでも文調を使い分けると良いでしょう。テンプレート文を活用することで、状況に応じた伝え方が可能になります。
【フォーマルなテンプレート文の例】
件名:新入社員歓迎会のお知らせ(4/12 木 18:00〜)
各位
平素より大変お世話になっております。
下記の通り、歓迎会を開催いたしますので、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
- 日時:4月12日(木)18:00〜20:00
- 場所:〇〇駅前 居酒屋△△(詳細地図は添付)
- 会費:3,000円(会社補助あり)
- 対象:〇〇部の新入社員××さん
- 出欠回答期限:4月5日(金)
【カジュアルなテンプレート文の例】
〇〇部に新しく入社された××さんの歓迎会を、下記の通り開催します!お時間合う方はぜひご参加ください!
- 日時:4月12日(木)18:00〜20:00
- 場所:〇〇駅前 居酒屋△△(詳細地図は添付)
- 会費:3,000円(会社補助あり)
- 出欠回答期限:4月5日(金)
必要な情報を網羅し、返信しやすい形式にすると出欠の集計もスムーズになります。
会場選びのポイント・注意点

ここからは、会場選びのポイント・注意点について紹介します。
アクセスのしやすさ
参加者がスムーズに参加できるよう、会場はアクセスの良さを重視しましょう。会社から徒歩圏内、または会社の最寄り駅から近い場所を選ぶことで、開始前の移動負担が軽減されます。たとえば、会社から徒歩10分以内、会社の最寄り駅から徒歩5分以内の飲食店であれば、仕事終わりでも参加のハードルが下がります。悪天候の場合や業務後の疲れを考慮すると、移動時間が短い会場ほど歓迎会への参加率を高める効果が期待できます。意外と見落とされがちな歓迎会の満足度のポイントです。
会場の雰囲気と音の環境
会場選びでは、落ち着いた雰囲気と会話しやすい音の環境が整っていることが大切です。照明が明るすぎたり、BGMが大音量だったりすると、せっかくの交流の場でも会話がしづらくなってしまいます。特に歓迎会では、初対面で話すことも多いため、適度な静けさと距離感が求められます。事前に下見ができる場合は、「BGMの有無」「音量の調整が可能か」「席同士の距離感」もチェックしておくと安心です。心地よく会話できる空間づくりが、交流の質を左右します。
席の構成(テーブルの配置・固定or移動)
歓迎会では、たとえ着席型であっても席の構成を工夫することで交流の幅を広げることができます。2〜3回程度の席替えを取り入れると、自然と多くの人と話すきっかけが生まれ、場の一体感も高まります。事前にくじ引きや番号カードを配布し、移動タイミングや方法をアナウンスしておくとスムーズな運営につながります。無理のない形で会話のきっかけをつくる仕掛けを用意することが、参加者の心理的ハードルも下がり、全体の満足度向上に効果的でしょう。
歓迎会の流れ

ここからは、歓迎会の流れについて紹介します。
歓迎会のプログラム例
歓迎会を円滑に進行するには、あらかじめ基本的なプログラム構成をおさえておくことが重要です。一般的なプログラム例を紹介します。事前に依頼する人と内容を整理し、漏れがないようにしましょう。
【一般的な歓迎会プログラムの例】
- 開会のあいさつ(5分):上司や主催者に歓迎の気持ちを込めた短いあいさつを事前に依頼する。
- 歓迎会の主役の紹介・あいさつ(5〜10分):事前に話せもらう内容や順番を共有しておく。
- 食事・歓談(60分):幹事がテーブルを回り、場の空気を確認。
- 軽いゲーム・企画(15〜20分):共通点ビンゴや二択クイズなど、具体的なテーマを用意。
- 締めのあいさつ(5分):幹事または上司が感謝の言葉を伝え、「また一緒にランチなどに行きましょう」など軽い提案を添えて、今後も気軽に交流できる雰囲気づくりにつなげる。
歓迎会で幹事が空気づくりをする方法

ここからは、幹事が空気づくりをする方法について紹介します。
会の冒頭で「安心して過ごせる場である」と明言する
歓迎会は、新たに入社する社員にとって「職場の雰囲気」を感じ取る最初の場です。幹事が冒頭のあいさつや乾杯前に、「今日はリラックスして交流することが目的です。緊張せず自由に過ごしてください」といったメッセージを伝えるだけで、その後の空気が大きく変わるでしょう。歓迎される本人だけでなく、周囲の参加者にも「頑張って盛り上げなくては」「上司に気を遣わなければ」といった無意識の負担を与えないように、ラフに過ごしてもらう空気づくりが大切です。この言葉は幹事がフラットな立場で伝えることで、安心感が増す効果があり、自然な交流につながることが期待できます。
話しやすい場をつくる座席の配置と声かけを工夫する
座席配置は、歓迎会の空気づくりにおいて非常に重要なポイントです。例えば、円卓や島型のテーブル配置にすることで、会話が分散され、1対1の緊張を和らげる効果があります。自然な交流を促すために、みんなでサポートし合う空気をつくることも大切です。新しく入った社員の隣には、話しやすい先輩や同年代の社員を配置し、幹事が事前に「今日は◯◯さん、初めての場なので、タイミングあったら話しかけてもらえると嬉しいです」などと軽く声をかけておくと、リラックスした会話のきっかけが生まれます。なお、役職の高い上司と新しく入社した社員が隣り合う場合は、フォロー役を間に挟むなど、会話のしやすさに配慮した座席配置を意識するとよいでしょう。物理的な距離感を工夫することで、心理的な壁も取り除きやすくなります。
沈黙を怖がらず、幹事がゆるく話題を投げ続ける
歓談中、場が静まり返る瞬間が訪れることは珍しくありません。そんな時こそ焦らず、幹事がゆるく話題を投げかけ続けることが大切です。たとえば、「最近、社内で人気のランチって何ですか?」「〇〇駅周辺でどこか行ったりしますか?」など、軽く答えやすい話題は会話のきっかけとなり、その後も自然に会話が生まれやすくなります。重要なのは、無理に盛り上げようとせず、自然体で振ることです。また、幹事自身が笑顔でうなずきながら話を聞く姿勢を見せるだけでも、場の空気はやわらかくなります。盛り上げ役ではなく、安心感をつくる存在として振る舞いましょう。
自己紹介タイムはテーマを用意して自由度を下げる
自己紹介の時間では、「自由にどうぞ」と言われると話す側の負担が大きくなりがちです。そこで幹事がテーマを用意し、たとえば「名前・出身地・最近ハマっていること」など、複数の項目を指定して紹介する形式にすると、内容も具体的になり、聞きやすくなります。事前に「1分程度でお願いします」と目安の時間を伝えておくと、テンポよく進行できます。幹事が最初に自己紹介をして手本を見せると、場がやわらぎ、初対面でも話しやすい雰囲気が生まれるでしょう。自己紹介の項目を指定することは、一見機械的に見えるかもしれませんが、初対面の多い場では安心感につながることが期待できます。
歓迎会の主役の話題を過度に掘り下げない
歓迎会では、「主役にたくさん話してもらおう」とするあまり、過度な質問攻めや過剰な称賛につながってしまうことがあります。「恋人いるの?」「就活どうだった?」など、プライベートに踏み込みすぎる話題は相手を委縮させてしまう原因になります。幹事としては、話題が行きすぎそうなときにはさりげなく話題を変えたり、「そういえば◯◯さんも似た話ありましたよね?」と別の参加者に振ったりして、空気やわらげる役割にまわりましょう。新しく入った社員を「主役」として迎える一方で、無理に目立たせず、安心して過ごせる空気感を整えることが大切です。
歓迎会の事後対応

ここからは、歓迎会の事後対応について紹介します。
写真・メッセージの共有
歓迎会後は、当日撮った集合写真やスナップショットを社内チャットや共有フォルダで共有すると、場の雰囲気や思い出が残りやすくなります。写真とあわせて、たとえば「改めて〇〇さん、ようこそ!これからご一緒できるのを楽しみにしています!」といった一言を添えると、歓迎の気持ちがより丁寧に伝わるでしょう。写真を共有する際には、写っている人の同意を得るほか、関係者以外に不用意に共有されないように、共有先を限定的する、参加者にも不用意に写真を共有しないことを周知するなど、プライバシー面にも十分配慮して行いましょう。
次の交流へのつなぎ方
歓迎会を一度きりのイベントで終わらせず、日常の中で自然な交流につなげることが関係構築において大切です。とはいえ、具体的な予定を組むと負担に感じることもあるため、気負わず参加できるような小さな仕掛けがあると効果的です。たとえば、歓迎会の翌日や週明けに「お疲れ様でした!」と一言添えて、ちょっとしたお菓子を置いておくだけでも、自然と会話が生まれるきっかけになるでしょう。無理に盛り上げようとせず、「よかったら○○さんにも声かけてみてください」と周囲に軽く促すことで、チーム全体で新メンバーを迎える雰囲気が育つことが期待できます。負担にならない程度に、交流の場を生む第一歩を仕掛けてみるのはいかがでしょうか。
よくある失敗と対策

ここからは、よくある失敗と対策について紹介します。
歓迎会の主役が話す機会を得られない
歓迎会では、主役である新しく入ったメンバーが話す機会を得られないことがあります。これは決して誰かの落ち度ではなく、自然な流れの中で起こり得ることです。話題のきっかけとして自己紹介の時間を設けることは有効ですが、自己紹介は一過性に終わりやすく、長期的な関係づくりには繋がりにくい場合も。そこで、共通点を探す簡単な企画をする、少人数での雑談タイムを設けるなど、相互のやりとりが生まれる仕掛けを取り入れると、効果を発揮する可能性があります。新しく入った社員が自ら話すきっかけを持てるような、場の仕掛けを事前に組み込むことがポイントです。
会話が一部のグループに集中してしまう
歓迎会では、同じ部署や入社時期が近い社員同士で集まりやすく、会話が一部のグループに偏ることがあります。その結果、話に入りづらい人が出てしまうことも。こうした偏りは無意識に起こりやすいため、幹事が意図的に「話のきっかけ」を仕込んでおくと安心です。たとえば、席替えの時間を設けたり、テーブル単位で自己紹介を行ったりすることで、会話の分散を促すことができます。幹事自身が各テーブルを回って、軽く話題を投げかけるだけでも、固定化しがちな会話の流れを横断する交流へと広げる効果が期待できます。
内容を詰め込みすぎて時間が足りなくなる
あいさつや企画を盛り込みすぎると、肝心の話す時間が削られてしまい、交流の機会が十分に取れないことがあります。歓迎会の主な目的は「話すこと」。幹事は事前に進行表を作成し、各コーナーの時間に余裕を持たせることが大切です。歓談時間は全体の6〜7割を確保すると、場にゆとりが生まれます。あいさつやゲームの時間が長くなりそうな場合は、当日の様子を見ながら柔軟に調整し、臨機応変に対応しましょう。場の雰囲気を大切にしながら、構成に余白を残すことで、自然な会話が広がりやすくなります。
企画が盛り上がりすぎて全員がついていけない
会場を盛り上げようと用意したゲームや企画が、思いのほかテンションの高いものになってしまい、一部の人がついていけなくなることがあります。特に、初対面が多い歓迎会では、落ち着いた雰囲気を好む人もいるため、全体に同じノリを求めるのは控えるのが無難です。対策としては、「見ていても楽しめる企画内容」や「選択参加制」の企画にするのが効果的です。たとえば、ビンゴや2択ゲームは、ルールがシンプルでリアクションが生まれやすく、見ているだけでも楽しめる設計が可能です。全員に同じテンションを求めず、さまざまな過ごし方を許容する余地を持たせることが、参加者の満足度を高めるポイントになります。
会の終わりが曖昧で締まらない印象になる
盛り上がったまま自然解散してしまうと、歓迎会全体が締まりのない印象になってしまうことがあります。特に入社したばかりの社員にとっては、「いつが正式な終わりなのか」「どのタイミングで帰っていいのか」がわからず、気を使ってしまうケースもあります。対策としては、幹事があらかじめ「19時50分頃に締めのあいさつを行い、その後自由解散にします」といったタイムラインを伝えておくことが大切です。締めのあいさつでは、歓迎の言葉と今後の期待を簡潔に伝え、拍手で締めると場が自然に収束します。その後も残る場合は「お時間ある方はぜひ」などと声をかけておくと、帰りたい人と残りたい人の両方に配慮できます。
まとめ
歓迎会は、新しく入った社員にとって、職場の雰囲気をつかむために大切な場です。幹事は派手な演出よりも、参加者一人ひとりが無理なく話せる「安心できる空気づくり」を意識することが何よりも重要です。参加者全員が心地よく過ごせるよう工夫された空間は、自然と良い関係の土台になります。この記事を参考に、あたたかく、記憶に残る歓迎会を企画してみてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る