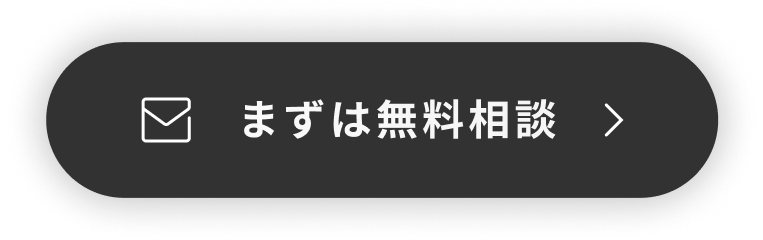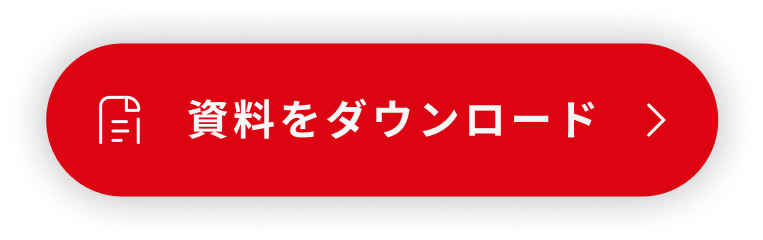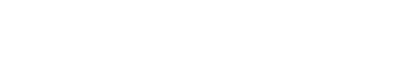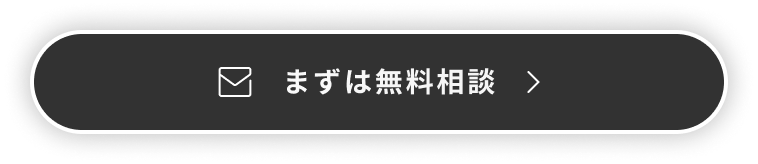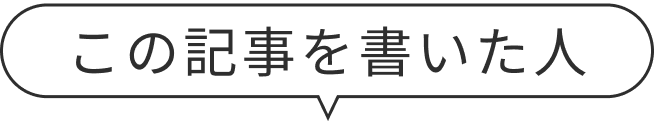地域活性化イベントとは?注目されている理由や事例・おすすめの企画例を紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



目次
人口減少や都市部への人口集中、地域経済の停滞など、多くの地方がさまざまな課題を抱えています。そうした状況を打開する手段として、現在「地域活性化イベント」が各地で注目を集めています。
本記事では、地域活性化イベントの概要や注目される背景、開催によるメリット・デメリットに加え、全国各地で実際に開催された事例、さらにおすすめの企画例まで幅広くご紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
地域活性化イベントとは

地域活性化イベントとは、地域の魅力を発信し、外部から人を呼び込むことで、地域経済やコミュニティの活力を高めることを目的としたイベントです。地域の資源や伝統文化、自然環境、地元産品などを活かし、住民と来訪者が交流する機会を設けることで、多様な効果を生み出します。具体的には、芸術フェスティバルやご当地グルメイベント、伝統芸能祭、スポーツ大会などが挙げられ、イベントの規模や形式も地域によってさまざまです。
そうした取り組みは、地域が抱える課題の解決に向けた手段として注目されています。次の章からは、その背景について詳しく解説します。
地域活性化イベントが注目されている理由

近年、多くの自治体や地域団体が、地域活性化イベントに力を入れています。その背景には、現代の日本社会が抱えるさまざまな課題があります。
- 都市部に人口が流出しているため
- 地域コミュニティが希薄化しているため
都市部に人口が流出しているため
多くの地方では、進学や就職を機に若者が地域を離れ、そのまま戻らないケースも少なくありません。そうした人口減少は、地域の経済やコミュニティの衰退に影響を与える深刻な課題です。
地域活性化イベントは、地域ならではの魅力や価値を示し、帰郷や移住を促すきっかけとして機能します。特にUターン・Iターンを検討している人にとって、イベントはその地域の雰囲気や人の温かさを体感できる絶好の機会でしょう。
地域コミュニティが希薄化しているため
過疎化や高齢化が進むなか、住民同士の関係は希薄になりがちです。昔ながらの隣近所のつながりが薄れ、地域行事への参加率も低下しており、世代や立場を超えて住民が協力し合う機会が減少しています。
地域活性化イベントを開催して、住民が一体となって準備・運営に携わることで、自然と交流が生まれます。共同作業を通じて、日常生活では生まれにくい新たなつながりや連帯感が芽生えるきっかけとなり、地域の絆を再構築することが可能です。
地域活性化イベントを開催するメリット

地域活性化イベントの開催には多くの準備や労力が必要ですが、適切に準備・運営すれば、大きなメリットを地域は享受できます。ここでは、主な3つのメリットを紹介します。
- 地域経済を活性化できる
- 地域の認知度を向上できる
- 定住人口や関係人口が増加する
地域経済を活性化できる
地域活性化イベントの開催は、地域外から多くの人を呼び込むきっかけになります。来場者は宿泊施設の利用や、食事、交通機関の利用、お土産の購入など、さまざまな場面でお金を使うため、経済効果が生まれます。また、イベントで販売される特産品やオリジナル商品の売上も、地域経済を潤す要素です。
このように、地域活性化イベントは地域内での経済循環を促進する手段として有効です。
地域の認知度を向上できる
話題性のある面白いイベントは、テレビや新聞、Webサイトなどのメディアで取り上げられる機会が増えます。さらに、来場者がSNSなどでイベントの様子や感想を発信することで、情報が自然に広がります。
それにより、これまでその地域を知らなかった人々にも、地域の名前や魅力が届くようになるでしょう。イベントが成功すれば、「〇〇(名物)といえばこの地域」というようなブランドイメージが定着し、開催時期以外にも観光客を呼び込める継続的なPR効果が見込めます。
定住人口や関係人口が増加する
関係人口とは、一度だけ観光に来た交流人口とは異なり、継続的に地域と関わりを持つ人々のことです。たとえば、毎年イベントにボランティアとして参加する人や、毎年欠かさず訪れる人などが該当します。
そうした人々が地域とのつながりを深めることで、地域に移住する定住人口や、地域課題を共に解決してくれる心強いパートナーが増加し、地域にとって大きな支えとなるでしょう。
地域活性化イベントを開催するデメリット

地域活性化イベントには多くのメリットがある一方、デメリットや注意すべき点も存在します。事前にリスクを把握し、対策を講じることが円滑な運営につながります。
ここでは、地域活性化イベントを開催するデメリットとして、以下のデメリットを紹介します。
- 環境に悪影響を及ぼす可能性がある
- 地域住民間で摩擦を生むことがある
環境に悪影響を及ぼす可能性がある
イベント開催に伴って多くの人が一斉に集まると、交通渋滞や騒音、ごみの増加など、周辺環境への負荷が大きくなることがあります。特に自然豊かな地域では、景観の損失や生態系への影響といった懸念も無視できません。
開催後の清掃やごみ処理が不十分であれば、住民や来訪者の満足度を損ねてしまうため、周辺環境に負荷をかけないための啓発活動を行い、開催後は清掃にもしっかり取り組みましょう。
地域住民間で摩擦を生むことがある
イベントの規模が大きくなるほど、地域住民の間に温度差が生まれやすくなります。「一部の人だけが恩恵を受けている」「準備にかかる負担が大きい」などの不満が蓄積すると、地域内の分断や対立を招きかねません。そうした摩擦を防ぐためには、初期段階から住民への丁寧な説明と合意形成を行い、役割分担や報酬の設定などにも配慮する必要があります。
地域活性化イベントの事例

ここでは、全国各地の地域活性化イベントの事例を紹介します。アート、食、伝統文化、自然を活かしたイベントなど、全国ではさまざまなイベントが実施されています。
瀬戸内国際芸術祭
瀬戸内国際芸術祭は、3年に1度、瀬戸内海の島々を舞台に開催される現代アートの祭典です。過疎化や高齢化といった課題を抱える島々の活性化を目的に、2010年から始まりました。
このイベントの大きな特徴は、アート作品が島の自然や文化と調和しながら展示されている点です。来訪者はアートを道しるべに島々を巡り、アーティストや住民、ボランティアサポーターと交流しながら、その土地ならではの景観や暮らし、文化などに触れることができます。
この仕組みが多くの人々の共感を呼び、世界の著名誌に取りあげられるようになりました。その結果、国内外から多数の観光客が訪れる、日本を代表する芸術祭へと発展しています。
B-1グランプリ
B-1グランプリは、ご当地グルメを通じて地域の魅力を発信する、まちおこしイベントです。2006年に青森県八戸市で10団体によって始まったイベントですが、2019年には全国から55地域の団体が出店するまでに規模が拡大しました。
このイベントの目的は自分たちのまちの魅力を来場者に伝え、「いつか○○(地域名)に行きたい」と思ってもらうことにあります 。単なる料理のおいしさを競うのではなく、おもてなしや地域PRの工夫なども含めて、まちおこし団体そのものを表彰するのが最大の特徴です。
郡上おどり
郡上おどりは、岐阜県郡上市八幡町で400年以上受け継がれてきた、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている盆踊りです。毎年7月中旬から9月上旬にかけて、30夜以上にわたって開催されることから、日本一ロングランの盆踊りとしても知られています。
この盆踊りの特徴は、観光客もその地域の人も区別なく参加できる「踊るための踊り」である点です。 江戸時代に城主が士農工商の融和を図るため、誰もが無礼講で踊ることを奨励した歴史的背景から、観光客も地域の人も一体となって踊りの輪に参加できます。
よさこい祭り
よさこい祭りは、1954年に高知県で誕生した踊りの祭典です。戦後の不況で沈む地域を元気づけようと始まり、いまでは全国に広がるよさこい系祭りの原点となっています。
本番は毎年8月10日・11日に開催され、高知市内17か所の競演場や演舞場では、約190チーム、2万人の踊り子が個性豊かな演舞を披露します。衣装、音楽、振り付けには、各チームの創意工夫が凝らされており、街中が熱気に包まれます。
8月9日には前夜祭と土佐学生よさこい大会、12日には後夜祭とよさこい全国大会が開催され、4日間にわたって高知市がよさこい一色に染まります。地域住民はもちろん、全国からの参加者や観光客も一体となって楽しめるこの祭りは、高知の文化と活力を象徴する代表的なイベントです。
めがねフェス
福井県鯖江市で開催されるめがねフェスは、国産めがねフレームの約9割を生産する“めがねのまち”の魅力を発信するイベントです。めがねの廃材を使ったワークショップや、めがねをかけたアーティストによるライブなど、めがねづくしのプログラムが展開されます。
めがねの作り手と使い手が直接交流できる機会を設けることで、ものづくりの背景や作り手の想いを伝えることに成功しました、産地のめがねの価値が伝わり、ファンの獲得にもつながっています。
山鹿灯籠まつり
山鹿灯籠まつりは、和紙と糊だけで作られる伝統工芸品「山鹿灯籠」を主役にした夏祭りです。その起源は室町時代にまで遡るとされ、長い歴史を持っています。
祭りのみどころは、頭に金灯籠を載せた浴衣姿の女性たちが優雅に舞う「千人灯籠踊り」です。幻想的な灯りがゆらめくなかで披露される優雅な踊りは、見る者を魅了します。
地域の歴史や文化、伝統工芸の美しさを伝えるこの祭りは、夏の風物詩として多くの観光客を集めています。
真夏の雪まつり
福島県檜枝岐村では、冬に降り積もった大量の雪を夏まで保存し、「真夏の雪まつり」を開催しています。日本有数の豪雪地帯という地理的特性を活かした、面白いイベントです。
雪の滑り台でソリ滑りをしたり、雪上ビアガーデンを楽しんだりと、真夏とは思えない体験ができます。
「夏なのに雪がある」という非日常的な演出が話題を呼び、観光資源としての新たな魅力を創出しています。
しもかわアイスキャンドルミュージアム
北海道下川町で毎年冬に開催される「しもかわアイスキャンドルミュージアム」では、町民が手作りした無数のアイスキャンドルが町全体を温かい光で包み込むイベントです。地域の気候という弱みを強みに変えたイベントで、町民一体となって幻想的な空間を創り出しています。
アイスキャンドルとは、氷の器にキャンドルを入れて灯すもので、寒さを活かした地域ならではの灯りです。1986年に青年町おこし団体がフィンランドの風習からヒントを得て始めたもので、今では町民が自宅や店舗の前でキャンドルを灯す文化として根付いています。
長崎ランタンフェスティバル
長崎ランタンフェスティバルは、中国の旧正月を祝う「春節祭」から発展した、長崎の冬の一大風物詩です。平成6年(1994年)に、長崎新地中華街の人々が地域の活性化を目的として、春節祭を「長崎ランタンフェスティバル」として大規模に展開したのが始まりです。
期間中は、長崎市中心部を約1万5,000個もの中国ランタンが彩り、街全体が幻想的な光に包まれます。なかには高さ10メートルを超える大型のランタンオブジェも登場し、訪れた人々を圧倒します。また、皇帝パレードや龍踊りなど、伝統文化を再現した催しも行われ、多くの観光客が訪れる大規模イベントへと成長しました。
1万人のエイサー踊り隊
一万人のエイサー踊り隊は、沖縄・那覇市の国際通りを舞台に開催される大規模な伝統芸能イベントです。伝統的なエイサーだけでなく、空手の型を取り入れた創作エイサーも披露され、活気あふれる演舞が街を彩ります。
一万人のエイサー踊り隊は、「もう一度地元の人々が集う賑やかな国際通りを取り戻したい」という若手経営者たちの想いから始まったイベントです。沖縄の伝統芸能であるエイサーを通じて、住民や商店街が結束したことで、地域内外から多くの人々が集う一大イベントへと成長しました。
eスポーツ酒場
eスポーツ酒場は、群馬県庁前の県民広場などで開催されている、eスポーツと飲食を組み合わせたイベントです。昭和庁舎の壁面にゲームの映像を投影して対戦を行うほか、キッチンカーによる飲食の提供も行っており、子どもから大人まで幅広い世代が気軽に楽しめます。
デジタル技術とリアルな交流を組み合わせた地域活性化の取り組みとして、注目を集めています。
地域活性化イベントにおすすめの企画例

地域活性化イベントを成功に導くには、来場者が「また来たい」と感じるような魅力的な体験の提供が欠かせません。ここでは、地域の特徴や資源を活かしやすく、幅広い年齢層でも参加しやすい企画例を紹介します。
- チャンバラ合戦
- ご当地グルメフェス
- 伝統文化体験イベント
- 地域産品のマルシェ
- 地域の自然を生かしたスポーツ大会
- スタンプラリー
- 謎解きイベント
- eスポーツ大会
それぞれの概要や特徴を説明していくため、地域活性化イベントの企画を検討する際の参考にしてください。
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀を使って、命に見立てたボールを落としあうアクティビティです。年齢や性別、運動能力にかかわらず誰もが楽しめる簡単なルールでありながら、チームでの戦略が勝敗を分ける奥深さも持ち合わせています。
戦う前には、チームで作戦を練る「軍議」の時間が設けられており、自然とチームワークが生まれます。地域の歴史や文化を組み込むことも可能で、参加者は楽しみながら地域について学ぶことができ、地域活性化イベントに最適な企画です。
ご当地グルメフェス
ご当地グルメフェスは、地元の飲食店や食品生産者が集まり、自慢の料理や特産品を提供する企画です。来場者は地域ならではの味を一度に楽しめるだけでなく、作り手の顔が見えることで、食材への関心や地域への親しみを深めることができます。
地域内の経済循環を促す効果も高く、グルメを通じた地域PRとして非常に有効です。
伝統文化体験イベント
伝統文化体験イベントは、その地域ならではの祭りや踊り、工芸品づくりといった伝統文化を、来場者が体験できる企画です。例えば、染め物や陶芸のワークショップ、楽器の演奏体験などが挙げられます。
見て楽しむだけでなく、実際に参加することで深い感動と満足感を得られるでしょう。思い出に残る体験となり、再訪のきっかけにもつながります。
地域産品のマルシェ
地域産品のマルシェは、地元の農家や漁師、職人などが集まり、採れたての食材や手作りの商品を販売する市場型イベントです。消費者と生産者が直接対話できるのが大きな魅力で、商品の背景にあるストーリーやこだわりが伝わり、ファンの獲得にもつながります。
地域の自然を生かしたスポーツ大会
美しい海岸線や山々、川など、地域の自然環境を活用したスポーツイベントも、地域活性化イベントにおすすめです。マラソンやサイクリング、トレイルランニングなどは、健康志向の高い層に人気があります。
コース上に地域の絶景や名所を組み込むことで、参加者はスポーツをしながらその土地の魅力を体感することが可能です。SNSなどでの発信も促しやすく、話題作りにも適しています。
スタンプラリー
スタンプラリーは、地域内の複数の名所や店舗を巡ってもらう企画です。歴史的な名所や商店街、絶景ポイントなどをつなぐコースを設定することで、来場者の滞在時間が延びて、地域をより深く知ってもらうきっかけになります。
最近ではスマートフォンを活用したデジタル形式のスタンプラリーも人気で、取得したデータを次の施策に活かすことも可能です。
謎解きイベント
謎解きイベントは、参加者が物語の主人公となり、地域に隠された謎や暗号を解きながらゴールを目指す企画です。地域の歴史や文化をストーリーに組み込むことで、参加者は楽しみながら自然と地域の魅力に触れることになります。友人や家族と協力して謎を解き、ゴールに辿り着いたときの達成感は、地域での忘れられない思い出となるでしょう。
eスポーツ大会
eスポーツ大会は、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として行う企画です。eスポーツは、特に若者世代に絶大な人気を誇っており、イベントの目玉として開催することで、これまで地域のイベントに興味のなかった新しい層を呼び込むことができます。飲食ブースや他の催しと組み合わせれば、ゲームのファン以外も楽しめる空間となるでしょう。
地域活性化イベントを成功させるためのポイント

地域活性化イベントで大きな効果を得るためには、企画を用意するだけでは不十分です。地域の特色を活かしながら、参加者と地域住民の双方が満足できる運営を目指す必要があります。ここでは、特に意識したい3つのポイントを紹介します。
- 地域資源を明確にする
- 地域住民や関係者との連携体制を築く
- 継続的な仕組みづくりを意識する
地域資源を明確にする
地域活性化イベントを計画する際は、まずその地域が持つ資源をしっかりと把握しましょう。たとえば、豊かな自然景観や歴史ある建造物、伝統的な祭り、特産品、地域に根付いた工芸品など、地域ならではの魅力を丁寧に洗い出していきます。
気候の厳しさや交通の便の悪さといった一見悪く見える要素も、発想を転換すれば「この地域でしか味わえない体験」として訴求できることがあります。具体的には、寒冷地ならではの氷や雪を活かしたイベントなどが良い例です。
そうした地域の資源や課題を多角的に捉え、それらをうまく組み合わせることで、企画に独自性が生まれ、参加者にとっても記憶に残るイベントを実現できます。
地域住民や関係者との連携体制を築く
地域活性化イベントを成功に導くには、一部の主催者だけでなく、地域全体の協力が不可欠です。行政はもちろん、地域のことを最もよく知る住民、経済活動を担う商店街や会社など、様々な関係者を計画の初期段階から巻き込みましょう。
それぞれの立場から出される意見やアイデアを積極的に取り入れることで、企画は多角的で魅力的なものになります。そのようにして地域全体でイベントを「自分ごと」として捉える意識が芽生えれば、継続的な協力体制の構築や一体感の醸成にもつながります。
継続的な仕組みづくりを意識する
地域活性化イベントを一過性のもので終わらせず、地域の持続的な活性化につなげるために、長期的な視点を持ちましょう。毎年あるいは数年ごとに定期開催する仕組みを整えることで、イベントは地域の風物詩として定着し、観光客やリピーターの獲得を期待できます。
さらに、新しい商品やサービスが生まれたり、イベントをきっかけに生まれた交流やつながりから、その地域の会社や人材による新たな取り組みが生まれたりすることもあります。イベントの開催をゴールとして考えるのでなく、それが未来の地域づくりにどう活かされるかを考える視点を持つことが大切です。
まとめ

地域活性化イベントは、地域の魅力を再発見し、外部とのつながりを増やす貴重な機会です。成功へと導くためには、地域資源を活かした魅力ある企画の実施が求められます。また、地域内外の人々との連携や、継続的な取り組みとしての位置づける視点も欠かせません。
本記事では、地域活性化イベントの概要から注目されている背景、開催するメリット・デメリット、具体的な事例、開催を成功させるポイントまでを網羅的に紹介しました。
今後イベントの開催を検討される方は、地域ならではの魅力や課題を見つめ直しながら、参加者にとっても地域にとっても有意義と思える企画づくりを目指してみてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る