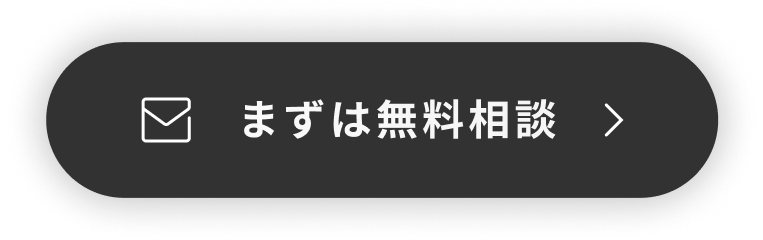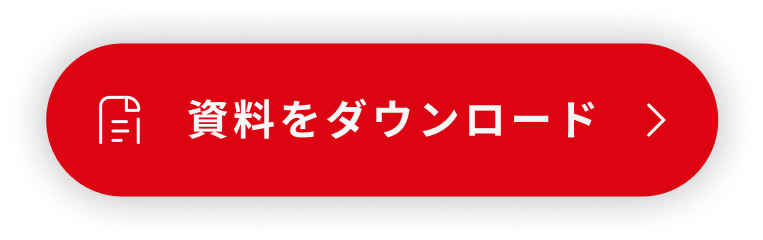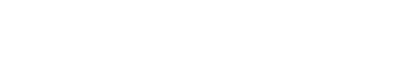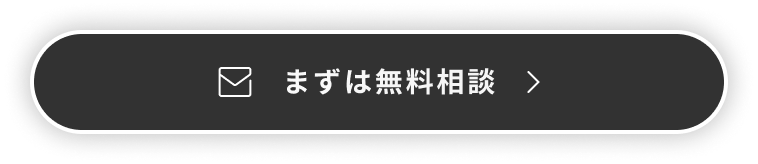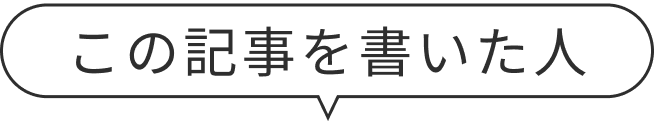防災ワークショップの企画アイデア30選
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月1日



目次
防災ワークショップとは、あらゆる災害を想定し、知識や対応力を身につけることを目的としたワークショップのことです。実際に体を動かす訓練や、身の回りのものを使った備えの工夫など、知識・情報・スキルが得られる内容が多いでしょう。
本記事では、手づくりの防災グッズのアイデアと、火災・地震・水害・避難生活を想定した防災ワークショップの企画アイデアを30選紹介いたします。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
手づくり防災グッズのワークショップ企画アイデア13選

ここからは、手作り防災グッズのワークショップの企画アイデアを13選紹介します。
新聞紙スリッパ作り
新聞紙スリッパづくりは、避難所生活などで役立つ簡易スリッパを新聞紙で作るワークショップです。シンプルな工程で、紙のサイズを変えれば小学生から大人まで応用でき、紙を2枚重ねればより丈夫なスリッパができます。少人数でも短時間で開催でき、材料費もほとんどかからないため導入しやすい内容です。
簡易トイレづくり
簡易トイレづくりは、災害時に役立つ簡易トイレを身近な素材で手づくりするワークショップです。簡易トイレには下記のようにさまざまな種類があり、使う人や状況に応じた内容で実施できます。
- レジ袋トイレ
- ポリ容器トイレ
- 段ボールトイレ
- キッズ用段ボールトイレ
- 紙箱トイレ
家庭や地域での備えを見直すきっかけにもなる、実用性の高い防災ワークショップでしょう。
レインコートづくり
レインコートづくりは、ゴミ袋を使って雨風をしのぐ簡易的なレインコートを作るワークショップです。少ない材料と手軽な工程でできるため、小学生から参加しやすい内容です。レインコートを応用すると防寒具にもでき、ゴミ袋を使う手づくり防災グッズワークショップとしてあわせて紹介すれば、より充実した内容になるでしょう。
アルミホイルの反射板ライトづくり
アルミホイルの反射板ライトは、懐中電灯の光を効率よく広げるための反射板ライトを作るワークショップです。作り方としては、牛乳パックなどの台紙にアルミホイルを貼るだけで、使う際は反射板として懐中電灯の背後に設置します。作り方や材料、使い方も手軽で停電時の備えとしても実用的な内容です。
ペットボトルランタンづくり
ペットボトルランタンは、懐中電灯の光を柔らかく広げる簡易的な照明を作るワークショップです。コップの中に入れた懐中電灯の上に、水を入れたペットボトルを乗せて光を底から当てると、水にあたる光が拡散し、懐中電灯よりも広い範囲を照らせます。
ペットボトルにシールや紙を使って装飾することで楽しみながら防災について触れられるのが魅力です。
参考:警視庁|安全な暮らし|災害に備える|災害対策課ベストツイート集|住まい|ライフライン|ペットボトルで簡単ランタン
マスクづくり
マスクづくりは、布やキッチンペーパー、輪ゴム2本、ホチキスなど身近な素材を使って、災害時に役立つ簡易マスクを作るワークショップです。作り方としては、下記の通りシンプルなため、誰でも簡単に作れます。
- マスク本体に当たる布やキッチンペーパーを蛇腹に折りたたむ
- 両端に輪ゴムをそれぞれ当てる
- 輪ゴムと布・キッチンペーパーをホチキスで留める
簡易的ではありますが粉じんや感染症対策として活用でき、実用性が高いのが魅力です。
ホイッスルづくり
ホイッスルづくりは、災害時に自分の居場所を知らせるための簡易ホイッスルをストローで作るワークショップです。ストローの先端を潰して三角にカットし、カットした側を吹くだけで音が鳴る仕組みで、子どもでも安全に作れます。いざというときに声が出せない状況でも役立つため、防災教育としても実用的です。
材料費が安く準備も簡単なので、手軽に開催できる防災ワークショップの1つでしょう。
水タンクづくり
水タンクづくりは、身近なポリ袋や段ボール・紙袋などを使って、水を保管する容器がない場合に役立つ簡易水タンクを作るワークショップです。45リットルの袋を二重にして段ボールに入れることで、10リットル前後の水を安全に保管できます。下記の方法で、タンクから直接水を少しずつ使用できます。
- 段ボール底側の1つの角を切って中から袋の角を出す
- 出した袋の角を切る
- 切った袋の口を輪ゴムで縛る
- 水を使いたい時は輪ゴムを緩める
洗剤づくり
洗剤づくりは、簡単な工程で、すすぎ不要の節水洗剤を作るワークショップです。500mlペットボトルに水・重曹(大さじ1)・塩(小さじ1)を入れて振ると洗剤が作れます。衣類の汚れに塩・重曹が働きかけ、すすぎが要らないため、断水時や災害時の節水対策として優れた実用性があります。
材料が安価で手に入りやすく日常での活用シーンも多い材料なので、備蓄しておいても無駄になりにくいのが特長です。
ペットボトルライフジャケットづくり
ペットボトルライフジャケットづくりは、1L~2Lのペットボトルを使った簡易ライフジャケットを作るワークショップです。リュックサックに空のペットボトルを2本差し込み、胸部分に紐で固定するだけで浮力を確保でき、大人用は2ℓ×4本、子ども用は軽量化して作れます。
知識を得ることで、日常で出るゴミを非常時の備えに変えることができる内容です。
紙食器づくり
紙食器づくりは、A4程度の紙を使い折り紙の要領で食器を折って、皿やコップなどを作るワークショップです。作った紙食器にラップを敷いたり袋を被せたりして使い、使用後にラップ・袋を取り替えれば洗う必要なく、使い回せます。災害時の衛生管理や洗い物の削減に役立つでしょう。
シェルターづくり
シェルターづくりは、毛布や机、段ボールなど身近なものを使い、安全に身を守る方法を参加者自身が考え、形にするワークショップです。考えて実践する体験を通して、何があれば安全か・どう工夫するかを考えるきっかけになるため、子どもから大人まで防災意識を高めやすいワークショップです。
防災ポーチづくり
防災ポーチづくりでは、好みのサイズのポーチに、ホイッスル・マスク・絆創膏・ミニライトなどを選んで詰め、いつもの外出でも持ち歩ける防災セットを作ります。自分にとって本当に必要なものを考えるプロセスが楽しいワークショップです。
実施の際はシールやイラストで模擬的に実施することも可能です。実際に作る場合は、中身も自分で選べるので個人の防災意識を高める企画としておすすめです。
避難生活を想定したワークショップ企画アイデア6選

ここからは、避難生活を想定したワークショップの企画アイデアを6選紹介します。
避難所運営ワークショップ
避難所運営ワークショップは、清掃・衛生管理・ルール決定といった避難所の運営に必要な業務を体感するワークショップです。参加者は5~20名程度の小~中規模チームに分かれ、トイレ設営や清掃スケジュール、掲示物の作成など役割分担をしながら模擬的に避難所の運営に挑戦します。
運営の体験を通じて、身をもって今この場に何が必要か気づき、避難下というナーバスな状況で周囲に働きかける方法や伝え方、役割分担の重要性を学べるため、地域や職場でのコミュニティ形成にも効果的でしょう。
在宅避難ワークショップ
在宅避難ワークショップは、自宅での避難生活を想定し、安全な場所の確保や寝る時の備えを考えるプログラムです。参加者は5~20名程度のグループに分かれ、セーフティゾーン(室内の安全な場所)の設定や寝具の配置、非常持ち出し品の見直しを行います。
ワークショップを通じ、家具転倒防止の対策や備蓄品の整理など、日常の地続きにある災害に備える工夫と判断力を育みます。在宅避難について考えることで災害時の選択肢が広がり、限られた環境の中でどう備えるかを見直すきっかけにもなり得るでしょう。
段ボールベッド組立ワークショップ
段ボールベッド組み立てワークショップでは、避難所で実際に配布される可能性のある段ボール製ベッドやパーティションを組み立てます。グループで行えば連携や役割分担が自然に生まれ、実際の避難所で、周囲の人をフォローするきっかけになり得るでしょう。
災害時の調理体験
災害時の調理体験ワークショップは、電気が使えない状況を想定し、身近な道具と食材で調理を体験するプログラムです。カセットコンロを使い、耐熱ポリ袋で材料を湯煎するパック調理や、インスタントラーメンに常温の水や豆乳を入れて60分放置する火を使わない調理など、洗い物が少なく衛生的な方法を学べます。
お風呂の代替ケア体験
お風呂の代替ケア体験では、災害時に入浴できない状況でも体を清潔に保つ方法を学びます。市販の体拭きシートや自衛隊・自治体による入浴支援サービスの紹介や食用重曹・ベビーパウダーを活用する方法、清拭の方法などを共有します。
非常時でも清潔を保てる方法を知ることで衛生面での不安を軽減できるでしょう。実施する際は、肌に負担をかけない素材の選び方・使い方、使い捨て用品の管理方法にも言及できると、充実した内容になることが期待できます。
火おこし体験
火おこし体験は、新聞紙・牛乳パック・ティッシュ・割り箸・輪切りの木など身近な素材を使い、火おこしを体験するワークショップです。火をおこすには、材料に着火する前に適した場所を見つけ、燃えやすいものを片付けるなど周囲の環境を整える必要があります。
着火して材料を燃やすことだけにとどまらない情報や必要な工程を学ぶことで、災害時に安全かつ効率的に火を扱うための理解や判断力を養う機会になるでしょう。
水害を想定した防災ワークショップの企画アイデア4選

以下では、水害を想定した防災のワークショップの企画アイデアを4選紹介します。
簡易土のうづくり・設置ワークショップ
簡易土のうづくり・設置ワークショップは、水害対策としてロープや資材に頼らず、水を入れたゴミ袋を段ボールで補強する簡易土のうを作って、玄関や出入口に設置するワークショップです。土砂不要で水を含むと膨らむ吸水式簡易土のうといった市販の防災グッズを紹介したり、使い方を練習したりするのも良いでしょう。段ボールでの補強や重ね方を工夫しながら、家庭でもできる実践的な備えを学べる内容です。
町の浸水リスクマップづくりワークショップ
街の浸水リスクマップづくりは、地域内で想定される水害リスクを可視化するワークショップです。グループごとで、白地図に浸水域や避難所、危険箇所を記入します。地域住民参加型で行うことで、防災意識を深め、情報交換する機会や近所の人同士で協力関係を醸成できる機会になることが期待できるでしょう。
浸水後の掃除・消毒ワークショップ
浸水後の掃除・消毒ワークショップは、水害後に実践すべき掃除・消毒方法を学ぶワークショップです。たとえば、泥を洗い流し、換気・乾燥した後、次亜塩素酸や逆性石けんで拭き取り消毒といった段階を実施します。
自治体によっては、消毒液配布や・手動噴射機の貸出も行っているため、あわせて紹介することで、地域の支援制度を活用する選択肢も提示しながら、無理のない復旧につなげられるでしょう。
トイレの逆流対策ワークショップ
トイレの逆流対策ワークショップでは、水のうを利用してトイレの下水を逆流させないための対策を学びます。まずビニール袋に水を入れる水のうの作り方を紹介し、参加者には水のうを作るところから実際に設置するまでを体験してもらいましょう。
また、洗濯機やキッチン、お風呂などの排水口にも有効なのであわせて説明すると充実した内容になるでしょう。実施の際は、逆流による感染症リスクや衛生面の説明も行うと、逆流対策の必要性がより伝えられることが期待できます。
地震を想定した防災ワークショップの企画アイデア3選

ここからは、地震を想定した防災ワークショップの企画アイデアを3選紹介します。
家具の固定体験
地震を想定した家具の固定体験ワークショップは、ミニチュア家具や実物の家具を使って転倒防止対策を体験するプログラムです。ビス・金具での固定、耐震ラッチや滑り止めシートの活用、収納物の重心調整など具体的な家具の固定方法を実践できます。
実施の際は、地震発生時の家具類の転倒防止対策の有無による被害の違いを比較できる内容にすることで、身近なリスクに気づき、家庭での備えに取り組むきっかけにつながるでしょう。
被災状況トークワークショップ
被災状況トークワークショップは、地震が発生した場合の具体的な状況を想定して、現場での行動を参加者で話し合うプログラムです。5名程度のグループに分かれ、安全確保・情報共有・避難の判断などをロールプレイします。
具体的な状況を想定することで、さまざまな状況を考慮して判断を下す必要性が生まれるため、現状を把握したうえで分析する臨機応変な対応力が養われることが期待できるでしょう。たとえば、具体的な状況例として下記のような例が挙げられます。
- 深夜1時に震度6の地震が発生する。停電もあり、家族は別室にいる状況
- 昼の12時に震度7の地震が発生する。家には自分1人でいて、家族は仕事や学校に行っている状況
過去の地震情報を調べるワークショップ
過去の地震情報を調べるワークショップでは、過去の地震の記録や被害状況を調べます。身近な地域や家族が住む地域など1つの地域を選び、過去の地震の記録や被害状況を調べて発生頻度や震度分布を分析しながら、災害の傾向と備えを考えるワークショップです。
地域特有のリスクに気づくきっかけになったり、防災意識や情報を活用する力を高められたりするのが特長です。実施の際は、5人程度のグループを組んで行うと一人ひとりの役割が充実し、調査を通じて主体的に学び、考える機会になるでしょう。
参考:気象庁|震度データベース
火災を想定した防災ワークショップの企画アイデア4選

ここからは、火災を想定した防災ワークショップの企画アイデアを4選紹介します。
初期消火訓練ワークショップ
初期消火訓練ワークショップは、火災発生直後の初期消火対応で取るべき行動を実践的に学べるプログラムです。屋外スペースを活用し、水道と繋いで使える訓練用の消火器や訓練用の模擬火災装置を使って消火動作を実践します。
消火器の使い方だけでなく、安全な立ち位置や通報の優先順位などもあわせたプログラムにすることで、実践力と判断力の向上に役立つでしょう。
消化器の正しい使い方ワークショップ
消火器の正しい使い方ワークショップは、屋内外での初期消火に役立つ消化器の正しい使い方を学べるプログラムです。下記のように消化器の使い方を説明し代表者が実演した後、参加者一人ひとりが実践します。
- 障害物にぶつけないように注意して、火災の起きている場所から7〜8m手前を目安に消化器を運ぶ
- 黄色の安全ピンを引き抜き、ホースを外す
- ホースの先端を持って火元に向ける。ホースの途中を持つと圧力の影響で狙いが定まらず、的確に放射できないので注意する
- レバーを強く握って放射する。消化器が重い場合は、消化器を置いたまま放射することも可能。
- 薬剤を浴びないよう風上煮立ち、火の根本を狙い、手前から薬剤を放射する。
燃える順番のシミュレーション
燃える順番のシミュレーションワークショップは、家の中のものに引火し延焼する様子を視覚的に体験するプログラムです。カーテンや衣服、家具など日常的に使われる素材が火災にどう影響するかを実験と解説を通じて学びます。
何に火が燃え移りやすいか、何を優先して避けるべきかなど、火災発生時に迅速に判断する力を養える内容です。
低温発火実験ワークショップ
低温発火とは、通常の発火温度より低い温度であっても、長時間に渡り加熱されることによって発火が起こることです。低温発火実験ワークショップでは、家庭内で実際に低温発火が起こりやすい場所の温度変化を、模型などで安全に体験します。
低温で発火するメカニズムを理解し、たとえば長時間の煮込み料理をする場合はキッチンの壁から離して調理する、ストーブの近くに木の素材の家具を置かないなど、熱源と燃えやすいものの距離感を考える意識が生まれることが期待できるでしょう。
まとめ
ここまで、手づくり防災グッズのワークショップアイデアや、火災・地震・水害・避難生活を想定した防災ワークショップの企画アイデアについて紹介しました。開催規模や対象者、実施する環境に応じて内容を工夫することで目的にあった防災ワークショップになるでしょう。本記事を参考に、実践的かつ参加者の記憶に残る防災ワークショップを企画してみてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る