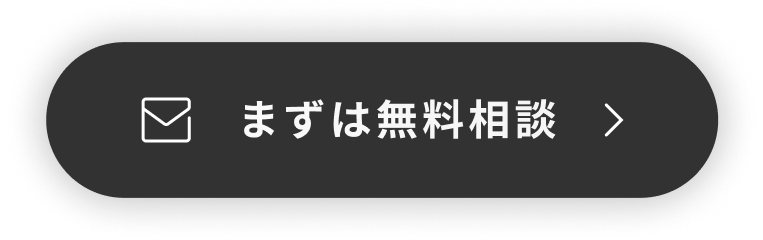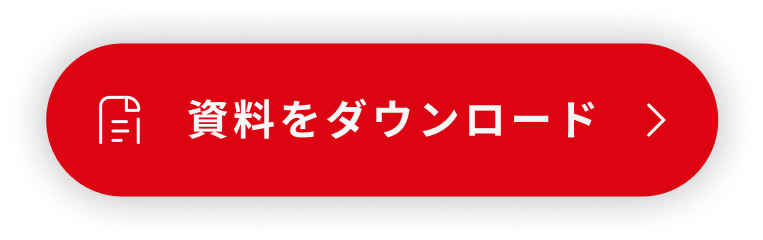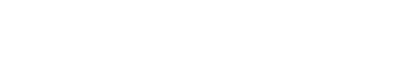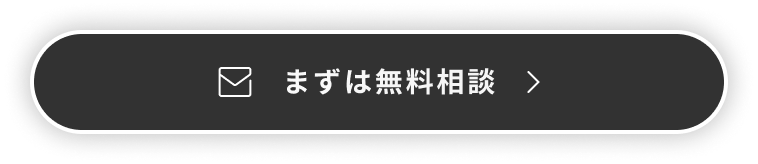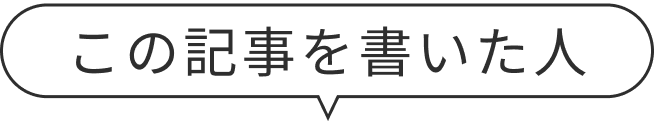式辞とは?書き方やポイント、例文を紹介
更新日:2025年7月14日



「式辞」とは、式典のなかで述べられる挨拶の一つです。式辞の他にも、「祝辞」や「謝辞」「送辞」など、「〇辞」という名称の挨拶は多々ありますが、何が違うのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では、式辞とは何か、式辞と似ている「〇辞」の意味も含めて、わかりやすく解説します。そして、式辞の書き方やポイント、式辞があるようなフォーマルな式典におすすめの会場として、「IKUSA ARENA」を紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
式辞とは
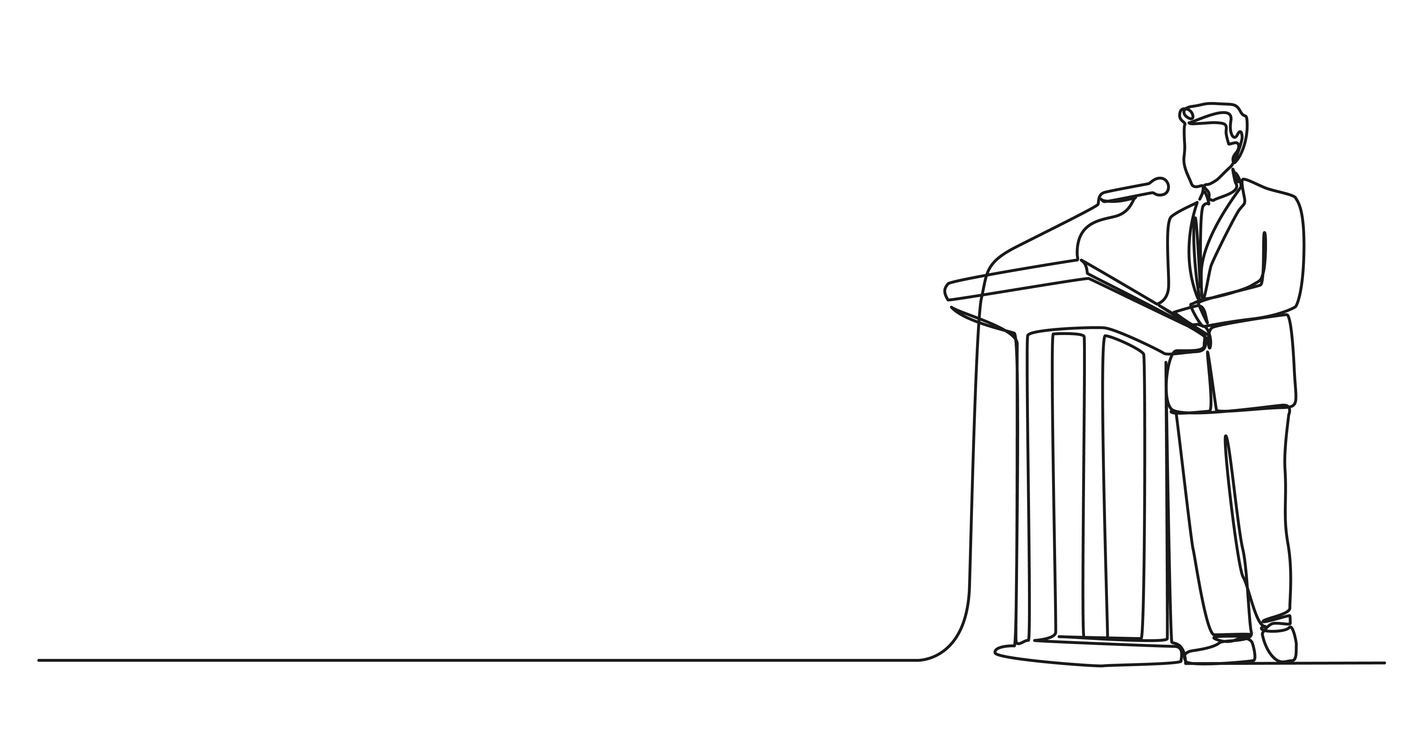
式辞(しきじ)とは、式典の場で主催者が述べる挨拶のことをいいます。
多くの式典には主催者の挨拶がありますが、式典のなかでも改まった式典では、「主催者の挨拶」ではなく「式辞」として述べられることが多いです。具体的には、学校であれば入学式や卒業式、会社であれば入社式や表彰式、周年記念式典、社葬などが挙げられます。
式辞を述べるのは、その式典の主催者側の代表者です。入学式や卒業式であれば学校長、会社の入社式や周年記念式典であれば社長が一般的で、社葬であれば葬儀委員長が担当することが多いでしょう。
式辞は、式典のなかで最初に述べられる挨拶です。以下は、学校の卒業式の一般的な式次第(式の順序が記載された進行表のこと)です。他に「祝辞」や「送辞」「答辞」「謝辞」といった挨拶もありますが、式辞はそれらよりも前に述べられます。
【卒業式の一般的な式次第】
-
卒業生入場
-
開式の言葉
-
国歌斉唱
-
卒業証書授与
-
学校長式辞
-
来賓祝辞
-
祝電の披露
-
送辞・答辞
-
校歌斉唱
-
閉式の言葉
-
卒業生退場
式辞と混同しやすい「〇辞」

先ほど学校の卒業式の一般的な式次第を例として挙げました。それを見ていただいてもわかるように、式辞以外にも、「〇辞」という挨拶は複数あります。ここで、それぞれの読み方と意味を整理してみます。
- 祝辞(しゅくじ)……式典の場で述べられるお祝いの言葉やスピーチです。来賓が述べるものだけでなく、式典の内容によっては主催者の挨拶も「式辞」ではなく「祝辞」とされることがあります。
- 謝辞(しゃじ)……謝辞には、「感謝の気持ちを表す言葉」と「非をおわびする言葉」という2つの意味があります。式典での謝辞は、感謝の気持ちを伝える挨拶やスピーチを指します。
- 送辞(そうじ)……式典の場で述べられる別れの言葉や、感謝を伝える挨拶のことです。特に、学校の卒業式で在校生から卒業生へ贈られる言葉を指します。
- 答辞(とうじ)……祝辞や送辞に対する返答の言葉です。学校の卒業式では、在校生からの送辞のあとに、卒業生の答辞が述べられます。
- 告辞(こくじ)……式典の場で、組織の管理者が述べる卒業生や保護者へのお祝いの挨拶です。組織の管理者とは、たとえば学校の卒業式であれば教育委員会などが考えられます。
- 弔辞(ちょうじ)……葬儀や告別式で、故人に贈られる言葉です。故人への感謝や亡くなってしまったことを悲しむ気持ち、思い出などを手紙のようにまとめ、読み上げます。
- 訓辞(くんじ)……立場が上の人が下の人に教え示すことを意味する言葉です。入社式などでは、経営層から新入社員に会社の目標や考え方、価値観などを「訓辞」として伝えることがあります。
式辞との違いを整理するために「〇辞」の意味を紹介しましたが、上記のようなさまざまな挨拶やスピーチをまとめて「式辞」とすることもあるようです。
式辞の書き方

式辞は、その場で頭に浮かんだことをアドリブで話すのではなく、あらかじめ用意しておいた文章を壇上で読み上げるものです。ここからは、式辞の書き方を解説してきます。
式辞用紙と封筒を用意する
まずは、式辞を書く紙と、それを入れる封筒を用意しましょう。
式辞は、専用の用紙に書くのが一般的です。式辞用紙は、文房具店やオンラインショップなどで販売されていますので、探してみてください。式辞用紙に文章を書くときは、毛筆や万年筆で手書きします。いきなり書くのではなく、文章を考えて、下書きをしてから清書するようにしましょう。または、最近はプリンタに対応している式辞用紙もありますので、パソコンで作成するのも一つの方法です。ただ、手書きのほうが丁寧ではあります。式典の内容や雰囲気に合わせて、最適な方法で作成しましょう。
封筒は、白無地の和封筒が基本です。封筒を選ぶ際は、ある程度厚みがある封筒を選ぶことをおすすめします。薄いと、中の用紙が透けて見えたり、破れてしまったりする可能性があります。封筒の表には、「式辞」や「祝辞」と書くのが基本的なマナーです。
式辞の内容
式辞の内容は、どのような式典なのかによって異なります。ただ、基本的な構成は「導入・本題・まとめ」ですので、これに当てはめて考えるとよいでしょう。
- 導入……式典に参加してくれたことへの感謝、時候の挨拶、式典の趣旨などを伝えて、会場の雰囲気を作ります。
- 本題……伝えたいメッセージを述べます(たとえば周年記念式典なら、会社のこれまでの歩み、現在力を入れて取り組んでいること、未来への展望などが考えられます)。
- まとめ……最後にもう一度感謝を述べて、式辞を締めくくります。
のちほど式辞の例文を紹介していますので、そちらも参考にしてください。
式辞を書くときのポイント
次に、式辞を書くときのポイントを紹介します。
「誰に向けた挨拶なのか」を意識する
誰にメッセージを届けるのかによって、内容や適した言葉も変わってきます。式辞を書くときは、「誰に向けた挨拶なのか」を意識しながら書くことが重要です。形式的な文章ではなく、心のこもった文章になるように心がけましょう。
また、式典の目的や雰囲気、参加者の年齢層などに合う表現となるよう、工夫しましょう。
丁寧な言葉を使う
「式典の目的や雰囲気、参加者の年齢層などに合う表現を」とお伝えしましたが、丁寧な言葉を使うというのが大前提です。カジュアルな言葉づかい、ネガティブな表現は式辞にはふさわしくありません。
また、いくら丁寧でも、同じ言葉や、「~でございます」ばかりが続くと、聞いている人に単調な印象を与えてしまいます。言葉を言い換えたり、文末の表現を変えたりして、リズムのある文章にすることも意識することが大切です。
長さは3~5分程度に収める
式典の内容にもよりますが、式辞の長さは3分程度が目安です。長くても5分以内に収めるようにしましょう。1分間のスピーチを原稿にすると、300文字程度になるといわれています。原稿用紙1枚が400文字なので、ボリュームとしては原稿用紙3枚程度を目安にするとよいでしょう。
読みやすさを意識する
当日は、式辞用紙に書いた原稿を読み上げますので、読みやすく書くというのも重要なポイントです。
具体的には、紙いっぱいに文字を詰めて書かないようにすること。折り畳み式の式辞用紙なら、用紙のサイズにもよりますが、一つの折り目に3~5行程度が目安です。適度に改行したり、一行空けたりして余白を作ると読みやすくなります。
パソコンで作成するなら、フォントは明朝体とし、文字サイズや行間も読みやすく調整しましょう。印刷前には、誤字脱字がないかチェックするのも忘れないでください。
また、式辞は自分さえ読みやすければよいというわけでもありません。基本的に式辞は持ち帰らない(学校や会社で保管される)ものなので、丁寧に書くことも大切です。
プロに依頼するのも一つの方法
「丁寧に手書きをしたいけれど、文字に自信がない」「時間がとれない」という場合は、筆耕に依頼する方法もあります。1週間程度で納品してくれるところが多いですが、納期を確認し、間に合うように依頼しましょう。
なお、依頼できるのは式辞を「書く」ことですので、文章はこちらで用意する必要があります。
式辞の例文

ここからは、入社式、辞令交付式、表彰式、周年記念式典の式辞の例文を紹介します。
入社式
会社の入社式は、まず司会者が入社式の開会を宣言し、そのあとに社長から挨拶を述べるという流れが一般的です。式次第では「式辞」ではなく「社長挨拶」や「社長祝辞」とされることが多いかもしれません。
入社式の式辞では、まず導入として、新入社員を祝福・歓迎する言葉や、自社に入社してくれたことへの感謝を述べます。そして、会社として伝えたいメッセージを述べたあとに、激励の言葉で締めくくります。
文章は、式辞を述べる社長自身が作成することが多いですが、人事部が作成するケースもあります。
【例文】
皆さん、入社おめでとうございます。株式会社〇〇〇〇社長の、△△△△と申します。本日、新入社員の皆さんを迎えることができたこと、大変うれしく思っています。また、数ある会社のなかから当社を選んでいただいたことに、心より感謝申し上げます。社を代表して、私から挨拶をさせていただきます。
(~中略~ ※ここで会社の歴史や大切にしている考え方、会社の方針、社会人として・自社の一員としての心構えなどを伝えます。)
皆さん、改めて入社おめでとうございます。本日新たな一歩を踏み出した皆さんが、各職場で活躍されることを期待しています。これから共に、明るい未来に向かって進んでいきましょう。どうぞ、よろしくお願いします。
本日は誠におめでとうございます。
辞令交付式
辞令交付式とは、企業や組織が辞令(異動や配置転換、昇進・昇格などを通知する文書)を交付する際に行う式典のことです。年度初めに入社式と同時に行うことが多いですが、年度の途中に入社した社員・職員を対象に個別で行われることもあります。
なお、辞令交付式は必ず行わなければならないものではありません。中小企業などでは、社長や上司から口頭で伝えるだけというケースもあります。
辞令交付式の流れや内容は会社によって異なりますが、入社式同様に司会者が開会を宣言したあと、社長または役員から挨拶を述べ、辞令交付と続くのが一般的です。
【例文】
株式会社〇〇〇〇社長の、△△△△と申します。本日採用辞令を交付し、皆さんをお迎えすることができました。多数の会社のなかから当社を選んでいただき、誠にありがとうございます。本日新たな一歩を踏み出された皆さんに、心よりお祝いを申し上げます。
(~中略~ ※ここで会社の歴史や大切にしている考え方、会社の方針、期待することなどを伝えます。)
今日から新しい職場での仕事が始まります。皆さんがそれぞれの持ち場で活躍されることを期待して、私の挨拶とさせていただきます。これから一緒にがんばっていきましょう。
本日は誠におめでとうございます。
表彰式
会社が行う表彰式とは、優秀な業績を上げた社員や、他の社員の模範となるような行動をとった社員を、会社が独自に表彰するイベントのことです。社員のモチベーションの向上や、企業理念の浸透、自社の取り組みや成果を社内外にアピールすることなどが、開催の主な目的です。
表彰式は、まず司会が開会を宣言し、代表者が挨拶(式辞)を述べ、表彰状の授与と続く流れが一般的です。どのような賞を贈る表彰式なのかによって挨拶の内容も変わりますが、ここでは永年勤続表彰の際に使える例文を紹介します。
【例文】
株式会社〇〇〇〇社長の、△△△△でございます。本日は、永年勤続□□年の×名の皆さんを表彰する機会として、この場を設けさせていただきました。永年勤続□□年を迎えられた皆さん、改めまして、受賞おめでとうございます。心よりお祝いと、感謝を申し上げます。
(~中略~ ※ここで会社の歴史や、受賞者がどれほど会社に貢献してくれたのか、受賞者とその家族に対する感謝、これからも力を貸してほしいことなどを伝えます。)
改めて、今回受賞された皆さん、おめでとうございます。今後も健康には十分ご留意いただきながら、まずますのご活躍を期待しております。引き続きどうぞ、よろしくお願いいたします。
本日は誠におめでとうございます。
周年記念式典
会社が実施する周年記念式典とは、会社の大きな節目をお祝いするための式典のことです。周年記念式典を開催する目的としては、社員や社外の関係者に感謝を伝える、喜びを分かち合う、未来のビジョンを共有し組織としての一体感を高めるなどが挙げられます。
内容は会社によって異なりますが、やはり冒頭では、会社の代表者である社長から式辞を述べるのが一般的です。周年記念式典の式辞は、まず導入として、会社が大きな節目を迎えることができたことに対する感謝を述べます。そして、過去から現在までを振り返り、未来のビジョンを共有して、最後にもう一度感謝を述べて締めくくるとよいでしょう。
【例文】
本日はご多忙中にもかかわらず、当社の創立××周年記念式典にご臨席賜り、誠にありがとうございます。来る×月×日をもちまして、株式会社〇〇〇〇は創立××周年を迎えます。このような大きな節目を迎えることができましたのは、これまで支えてくださった皆様のおかげでございます。心より、感謝申し上げます。
(~中略~ ※ここで過去の振り返り、現状の確認、未来への展望を述べます。)
これまでに培ってきたものを活かし、今後も目指すビジョンの実現に向けて邁進してまいります。最後になりましたが、本日ご臨席の皆様、支えてくださった関係者の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げ、私の式辞とさせていただきます。
本日はご臨席賜り、誠にありがとうございました。
式辞があるようなフォーマルな式典なら「IKUSA ARENA」がおすすめ
式辞があるようなフォーマルな式典を開催するなら、会場選びも重要です。東京都内で式典の会場を探しているなら、「IKUSA ARENA」もぜひご検討ください。
「IKUSA ARENA」は、2024年6月にオープンした大規模イベントスペースです。運動会のような身体を動かす社内イベントから、研修、懇親会、式辞があるようなフォーマルな式典まで、幅広く対応しています。
式典の会場選びで重視するべきポイントの一つに、「アクセスのしやすさ」があります。「IKUSA ARENA」は東武練馬駅から徒歩10分と、新宿や池袋からのアクセスも良好です。
メインフロアの広さは約700㎡、横14.6m×縦4.2mの大型ステージと、中央には吊り下げ式の130インチスクリーンも完備しています。式典の雰囲気に合わせたレイアウトや演出も提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
また、参加者同士の交流を促す目的で、式典と合わせて懇親会が開催されることもあります。「IKUSA ARENA」は飲食(酒類も含む)OKなので、食事を伴う形での開催も可能です。ケータリングプランもございます。
まとめ
式辞は、専用の用紙に書き、封筒に入れて、当日は読み上げたあと持ち帰らないのが基本マナーです。保管される文書ですので、自分が読みやすいだけでなく、丁寧に作成することを心がけましょう。
また、本記事でも式辞の例文を紹介しましたが、過去に開催した式典で述べた式辞を、ホームページで公開している学校や会社、自治体などもあります。文章を考える際は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る