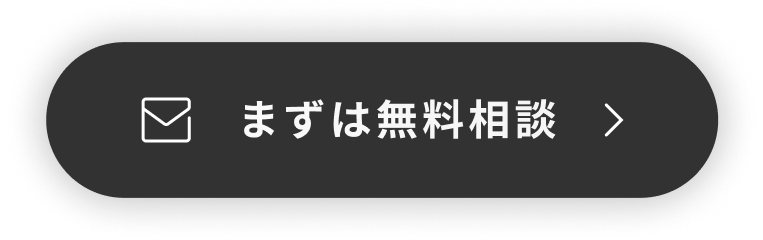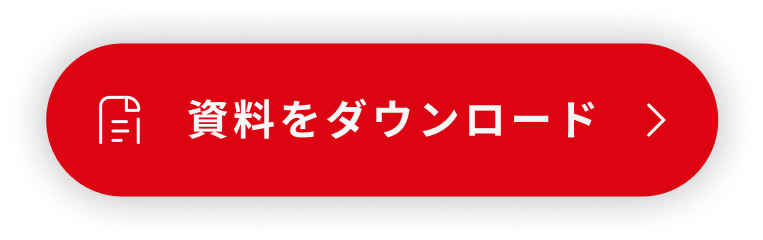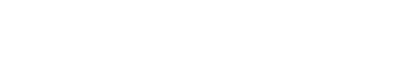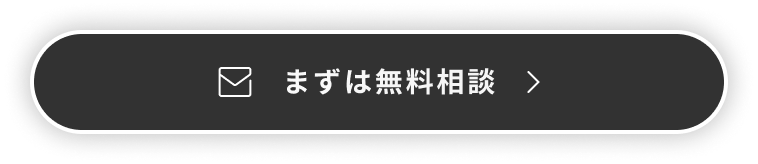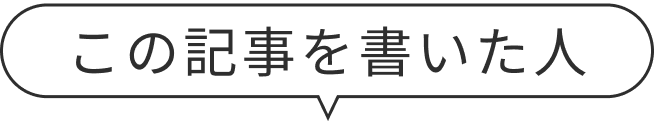異業種交流会とは?一般的な流れや準備・盛り上がる企画を紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月23日



目次
「新しい事業のヒントが欲しい」「社員にもっと広い視野を持ってほしい」など、会社の成長や組織の活性化を目指す人事・総務担当者様にとって、そのような課題は常につきまとうものでしょう。そこで注目されているのが、異なる業種業界の人々が集まり、情報交換や人脈形成を行う「異業種交流会」です。
本記事では、異業種交流会の概要から、会社が主催するメリット、具体的な準備や当日の流れ、そして参加者の満足度を高める企画まで、網羅的に解説します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
異業種交流会とは

異業種交流会とは、その名の通り、普段は関わることの少ないさまざまな業種・業界の人々が集まり、情報交換や人脈形成を行うための会のことです。名刺交換だけにとどまらず、新たな知識の習得やビジネスパートナーの発掘、新しいアイデアの創出など、多岐にわたる目的で開催されます。
一方的に情報を受け取る「セミナー」や、特定のテーマを深く学ぶ「勉強会」とは異なり、参加者同士で情報を共有し合う点が特徴です。その双方向のコミュニケーションから、自社だけでは得られなかった気づきを得られることもあります。
異業種交流会の種類

異業種交流会は、参加者の対象によって「社内向け」と「社外向け」の2種類に大別できます。それぞれの目的や特徴は大きく異なるため、自社の課題に合った種類を選びましょう。
社内向け
社内向けは、自社内の異なる部署や事業部、あるいはグループ会社の社員同士が集まって交流する形式です。一見すると異業種ではないように思えますが、専門分野や業務内容が違えば、社内の異業種と言えます。
主な目的は、組織や情報が孤立しているサイロ化の解消や、組織全体の一体感の醸成、そして部門を横断した知識の共有による新しいアイデアの創出です。普段関わりのない社員同士が交流することで、業務連携が円滑になる効果も期待できます。
社外向け
社外向けは、自社以外のさまざまな会社や業界から参加者を募って開催する、一般的な形式です。
新たなビジネスパートナーや顧客の開拓、業界の最新トレンドや他社の取り組みに関する情報の収集、自社の製品やサービスの認知度向上など、対外的なビジネス機会の創出を主な目的としています。社内では得られない知識や技術などに触れることで、自社の成長を加速させるきっかけにもなるでしょう。
異業種交流会を開催するメリット

会社が主体となって異業種交流会を開催することには、多くのメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。
- 生きた情報を収集できる
- 新しい発想が生まれやすい
- 新しいビジネス機会の獲得につながる
生きた情報を収集できる
今の時代、インターネットで検索すればあらゆる情報が手に入ります。しかし、対話の中でしか得られない生きた情報も少なくありません。
異業種交流会では、他社の成功事例や失敗談、業界の最新トレンド、顧客のリアルなニーズなど、ネットの検索では出てこない情報を直接聞くことができます。自社の常識が他社の非常識であることに気づかされたり、異なる業界の取り組みが自社の課題解決につながるヒントになったりすることもあるでしょう。
新しい発想が生まれやすい
同じ業界の人だけで集まっていると、どうしても考え方が固定化されがちです。そこに、異なる価値観や専門知識を持つ異業種の視点が加わることで、これまで思いもよらなかった新しいアイデアや事業戦略が生まれることがあります。
例えば、「製造業の品質管理手法をITサービスの開発に活かす」「飲食店のサブスクリプションモデルを教育業界に取り入れる」といった、業界の垣根を越えた発想の転換も期待できます。
新しいビジネス機会の獲得につながる
異業種交流会は、新たなビジネス機会を獲得する場としても有効です。参加者との対話を通じて、以下のような可能性が生まれることがあります。
- 新規顧客の獲得
- 新たな販売代理店やパートナーの開拓
- 商品やサービスの共同開発
- 業務提携やM&Aのきっかけ
さらに、自社が主催者となることで、会社の認知度向上やブランディング強化にも繋がります。「面白い取り組みをしている会社」「開かれた社風の会社」という良い印象は、採用活動においても有利に働くでしょう。
異業種交流会を開催するデメリット

異業種交流会の開催には多くのメリットがある一方で、担当者が事前に理解しておくべきデメリットや注意点もあります。対策を講じて異業種交流会を成功させるためにも、ここで異業種交流会を開催するデメリットについて確認しておきましょう。
- コストや手間がかかる
- 期待した成果に繋がらない可能性がある
- 参加者の満足度に差が生まれやすい
コストや手間がかかる
異業種交流会の開催には、金銭的・時間的なコストがかかります。リアル開催の場合、会場費、飲食費、備品代などが発生し、規模によっては大きな予算を確保しなければなりません。オンライン開催の場合でも、ツールの利用料や配信機材の準備が必要になります。
また、企画の立案から集客、当日の運営、開催後のフォローに至るまで、多くの工程があり、担当者にかかる負担は軽くありません。他の業務と並行して準備を進めるのであれば、しっかりとスケジュール管理を行いましょう。
期待した成果に繋がらない可能性がある
入念に準備をしても、成果に結びつかないことがあります。例えば、開催目的が曖昧だったり、集客した参加者の層がテーマと合っていなかったりすると、十分な交流が生まれず、単なる名刺交換の場で終わってしまうことがあります。
「新しいビジネスの機会を得られなかった」「社員の刺激にならなかった」といった結果になれば、費やした費用や時間が無駄になってしまうでしょう。そうした事態を避けるためには、あらかじめ目的を明確にし、それに沿った企画の準備や集客を行うことが重要です。
参加者の満足度に差が生まれやすい
多様な背景を持つ人々が集まるからこそ、「積極的に人脈を広げたい」「特定の情報を得たい」など、参加者一人ひとりの目的や期待することもさまざまです。内容によっては、一部の人だけが盛り上がり、他の人は疎外感を感じてしまうなど、参加者の満足度に大きな差が生まれることがあります。
全ての参加者が満足できるように、交流を促す工夫や配慮が運営側には求められます。
異業種交流会の一般的な流れ

ここでは、会社が主催する異業種交流会の当日の流れを6つの段階に分けて解説します。円滑な運営のためのポイントもあわせて確認しましょう。
- 受付を行う
- 当日の流れを説明する
- 全員に自己紹介をしてもらう
- グループで交流を深める
- 名刺交換・フリートークの時間を設ける
- アンケートを実施する
1.受付を行う
受付では、来場者の氏名と参加者一覧の情報を照合しながら、会社名・氏名が記載された名札や、当日の予定が書かれたパンフレット、配布資料などを手渡します。
その際に大切なのは、単なる事務作業で終わらせないことです。受付は、参加者が会場に到着して最初に訪れる場所であり、交流会全体の第一印象を左右する場所です。スタッフが笑顔で「本日はご参加いただきありがとうございます」「〇〇様ですね、お待ちしておりました」などの歓迎の言葉をかけることで、参加者の緊張を和らげられます。
2.当日の流れを説明する
定刻になったら、司会者から開会の挨拶を行い、当日の流れや交流会の目的などを伝えます。「本日の交流会は、『〇〇』というテーマのもと、皆様が新たなビジネスのヒントを発見し、価値ある人脈を築くことを目的としています」といったように目的を明確に共有することで、参加者全員の意識が統一され、より積極的に交流に参加してくれるようになります。
写真撮影の可否やSNS投稿に関するルールなども、あわせて案内しておきましょう。
3.全員に自己紹介をしてもらう
参加者同士がお互いのことを知るために、まずは全員に簡単な自己紹介をしてもらう時間を設けます。参加人数にもよりますが、1人あたり30秒〜1分程度を目安に、以下の内容を簡潔に話してもらうとよいでしょう。
- 会社名
- 氏名
- 主な業務内容
- 本日の参加目的・話してみたいこと
タイムキーパーがベルなどで経過時間を知らせると、自己紹介をテンポ良く進行できます。その時間があることで、参加者は「どのような人が来ているのか」がある程度わかり、その後のフリートークで「先ほど〇〇とおっしゃっていましたね」と、会話を始めるきっかけが掴みやすくなります。
4.グループで交流を深める
全体での自己紹介の後は、4〜6名ほどの小グループに分かれて、より深く交流する時間を設けます。
ただ「ご自由にどうぞ」とするのではなく、「最近注目している技術について」「仕事における最近の挑戦」など、主催者側で具体的な話題を用意しておくことがおすすめです。自然と会話が弾み、参加者同士の交流が活発になります。
途中でグループを入れ替えることで、より多くの参加者と話す機会が生まれ、イベント全体の満足度向上につながります。各グループに運営スタッフが進行役として加わり、議論を活性化させるのもよいでしょう。
5.名刺交換・フリートークの時間を設ける
グループで交流を深めたら、次は交流会のメインである名刺交換・フリートークの時間です。参加者が会場内を自由に移動し、興味のある相手と個別に交流できるようにします。軽食や飲み物を用意した立食形式にしたり、心地よいBGMを流したりすることで、場の雰囲気が和らぎ、話しかけやすい空気となります。
スタッフは会場全体を見渡し、交流がうまく進んでいない様子に気づいたら声をかけるようにしましょう。例えば、一人でいる参加者がいれば、「もしよければ、あちらのテーブルをご紹介しますね」といった形で、他のグループに自然に入れるようサポートします。また、会話が途切れているグループがあれば「〇〇さんはIT業界の方ですが、皆さんから何かご質問はありますか?」など、会話のきっかけを提供しましょう。
6.アンケートを実施する
交流会の最後には、今後の改善に向けたアンケートを実施します。満足度だけでなく、以下のような点についても、具体的な意見を求めましょう。
- どの企画が印象に残ったか
- どのような人とつながれたか
- 改善してほしい点
アンケート用紙の回収には手間と時間がかかるため、QRコードをスクリーンに表示し、スマートフォンから手軽に回答できるWebフォームを活用するのがおすすめです。「ご回答いただいた方には、本日の登壇資料を後日メールでお送りします」といった特典を用意すると、回答率を高めることができます。
集まった参加者の意見や要望は、必ず次回の運営に活かしましょう。
異業種交流会の開催形式

異業種交流会の開催形式には、リアル形式、オンライン形式、ハイブリッド形式という3つの種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、目的やターゲットに合わせて最適な形式を選びましょう。
リアル形式
リアル形式は、参加者が指定の会場に集まって交流する、最も一般的な形式です。
この形式の大きなメリットは、同じ空間を共有することで生まれる一体感にあります。表情や身振り・手振りといった非言語情報が伝わりやすく、信頼関係が構築しやすくなっています。
その反面、会場費や飲食費などの費用がかさむ点は無視できません。また、参加者は物理的に移動する必要があるため、遠方に住む人の参加が難しく、集客エリアが限定されるというデメリットもあります。
オンライン形式
オンライン形式は、ZoomなどのWeb会議システムを使用し、参加者がそれぞれの場所からPCやスマートフォンなどで参加する形式です。
遠隔地や海外からの参加も可能であり、幅広い層にアプローチできるのは大きな強みです。会場費がかからず費用を大幅に削減できる点も、主催者にとっては嬉しいポイントでしょう。
一方で、画面越しのやり取りではリアル形式ほどの一体感の醸成は難しく、雑談などからの偶発的な出会いが生まれにくいという課題があります。参加者の通信環境によっては、体験の質が落ちる点にも注意が必要です。
ハイブリッド形式
ハイブリッド形式は、リアル会場とオンライン配信で同時に開催する形式です。会場にカメラやマイクを設置し、その様子をオンライン参加者にもリアルタイムで届けることで、現地に来られない人にも遠方から参加してもらえます。
ハイブリッド形式の特徴、リアル形式とオンライン形式のメリットを両立できることです。会場に集まった参加者同士は、その場の空気感や熱量を共有しながら一体感を育むことができ、一方で、地理的な制約がある人もオンラインで参加できるため、より多くの方にイベントを届けられます。
ただし、リアル形式とオンライン形式の両方の準備が必要になるため、準備や運営の負担が大きいというデメリットもあります。さらに、リアル参加者の熱気をオンライン参加者にどう届けるか、オンライン参加者が疎外感を感じないようにどう交流を促すかなど、両者間に温度差や情報格差が生まれないよう、プログラムや進行に工夫が求められます。
異業種交流会の開催に向けた準備

異業種交流会を実りあるものにするために、入念に準備を行いましょう。ここでは、担当者が押さえておきたい準備を6つの段階に分けて解説します。
- 目的とテーマを決める
- 開催形式を選ぶ
- 日時と会場を決める
- 当日の流れを決める
- 運営メンバーを確保する
- ターゲットに告知する
1.目的とテーマを決める
まずは「なぜ交流会を開催するのか」という目標を明確にしましょう。例えば、「新規事業のアイデアを集めたい」「若手社員の視野を広げたい」など、具体的な目標を設定することで、最適なテーマも自ずと決まります。
2.開催形式を選ぶ
目的やテーマ、ターゲット、予算、運営リソースなどを考慮して、リアル形式・オンライン形式・ハイブリッド形式の中から最適な開催形式を選んでいきます。
| おすすめのケース | |
| リアル形式 |
|
| オンライン形式 |
|
| ハイブリッド形式 |
|
3.日時と会場を決める
より多くの人が参加できるように、参加者が集まりやすい日時を設定します。一般的には、平日の業務終了後や金曜日の午後などがよく選ばれます。
また、会場を選ぶ際は、以下の点を確認しておくことがおすすめです。
- アクセスの良さ(最寄り駅からの距離、交通手段の充実など)
- 収容人数(参加予定人数に対して十分な広さがあるか)
- 設備の充実度(プロジェクター、音響、Wi-Fi環境など)
- 雰囲気や内装(テーマに合った空間づくりができるか)
4.当日の流れを決める
当日の進行が円滑になるように、具体的なプログラムとタイムスケジュールを作成します。歓談や企画、休憩の時間などをバランスよく配置し、参加者が飽きずに集中できる構成を目指しましょう。
5.運営メンバーを確保する
司会、受付、会場案内、タイムキーパー、機材の管理など、必要な役割を洗い出し、それぞれに適任者を配置します。誰が何を担当するのかを明確にした運営マニュアルを作成し、事前に共有しておくことで、当日の連携がうまくいきやすくなります。
6.ターゲットに告知する
開催の1~2ヶ月前から、ターゲットとなる層へ告知を開始します。社内ポータルやメール配信のほか、会社の公式サイトやSNS、取引先への案内など、複数のチャネルを活用すると効果的です。
異業種交流会が盛り上がる企画

参加者の満足度を高め、交流を活性化させるために、面白い企画を取り入れましょう。ここでは、異業種交流会におすすめの企画を5つご紹介します。
ビンゴ大会
ルールが簡単で誰もが気軽に参加できるビンゴ大会は、異業種交流会におすすめの企画のひとつです。番号が読み上げられるたびに「リーチです」「もうすぐビンゴです」といった声があがり、隣同士で自然と会話が始まります。初対面の人ともやり取りが生まれやすく、場の雰囲気も柔らかくなります。
参加者のモチベーションを高めるために、景品を用意しておくのもおすすめです。さまざまな景品を用意すれば、最後までワクワク感が続くでしょう。
クイズ大会
クイズ大会は、参加者同士の交流を促進する企画として効果的です。共通の問題に取り組むという体験を通して、参加者同士の距離は縮まり、会場に一体感が生まれます。
出題内容は、一般常識や時事問題、業界にまつわるトリビア、最新のビジネストレンドなど多岐にわたります。問題によっては意外な人が活躍して、それが会話のきっかけとなることもあるでしょう。
進行形式は、チーム対抗と個人戦のどちらでも実施可能です。チーム戦の場合は、答えを導く過程で意見交換や協力が必要になるため、初対面でも関係性を築きやすくなっています。一方、個人戦では参加者それぞれの個性や専門性が表れやすく、その後の会話が弾みやすくなります。
BBQ
BBQは、屋外の開放的な空間で、参加者が協力しながら食事の準備から行う企画です。火起こしや調理といった共同作業を通じて、自然と関係が深まっていきます。オフィスや会議室とは異なるリラックスした雰囲気は、参加者の緊張を和らげ、心理的な壁を取り払ってくれるでしょう。
役職や年齢、業種の違いを意識することなく、フラットに接しやすいのも、この企画の大きな魅力です。「〇〇会社の部長」ではなく「〇〇さん」として関わるため、親近感が生まれやすく、その後の関係にもよい影響をもたらすでしょう。
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀を使い、命に見立てたボールを落とし合うチーム対抗のアクティビティです。勝利という同じ目標に向かってチームメンバーと力を合わせることで、初対面でも自然と会話が生まれ、参加者同士の距離がぐっと縮まります。
いきなり戦うのではなく、まずチームで戦術を立てる「軍議」の時間があり、話し合った戦術をもとに協力して勝利を目指します。勝敗を分けるのは体力や運動能力ではなく、チームワークや戦術の巧みさです。そのため、運動が得意でない方でも十分に楽しめます。
謎パ
謎パは、参加者全員が一つのチームとなり、バラバラに配られた謎のかけらを共有し、ゲームクリアを目指すアクティビティです。かけらを集めて謎を解き、それによって発令されたミッションをすべてクリアした後、最後に用意された最終問題に正解することでゲームクリアとなります。
クリアするためには、他の参加者との情報共有が不可欠であり、自然と会話が生まれる点が特徴です。業種や役職に関係なく、誰もがチームの一員として動く必要があります。共通の目標に向かって協力し、ゲームをクリアした時の大きな達成感は、参加者に強い連帯感をもたらすでしょう。
まとめ

異業種交流会は、業界や職種の枠を超えた出会いを通じて、新たな視点や発想を得られる機会です。社内のサイロ化を防げるだけではなく、社外との接点を持つことで、新しいビジネス機会を獲得できる可能性もあります。
ただし、「開催すること」そのものを目的にしては、大きな効果を得られません。なぜ交流会を開くのかという目的を明確にし、ターゲットに合った形式や日時・会場を設定したうえで、参加者の行動や会話を自然に引き出せるような構成を設計することが重要です。特に、交流のきっかけとなる企画選びは慎重に行いましょう。
ぜひ本記事の内容を参考に、実りのある異業種交流会の開催を成功させてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る