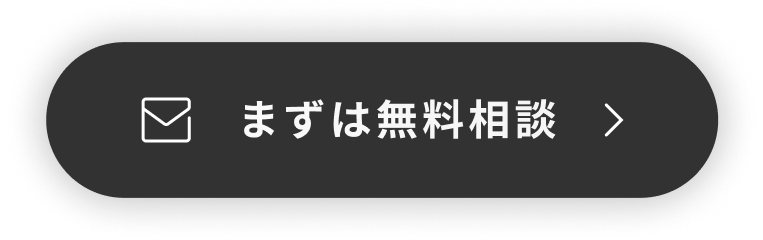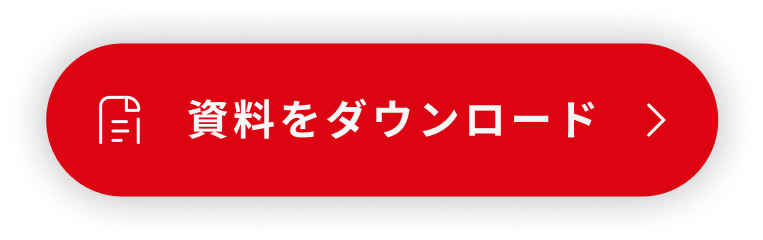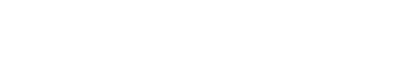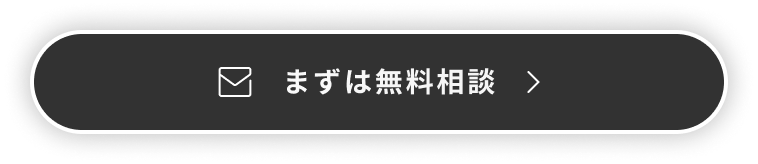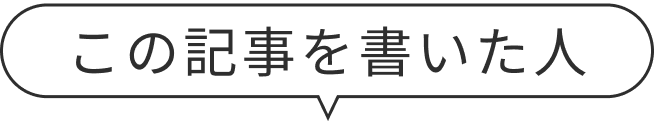式次第とは?書式や作成方法・すぐ活用できるテンプレートを紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月30日



会社の創立記念式典や入社式、祝賀会、株主総会など、フォーマルなイベントを円滑に進行させるうえで欠かせないのが「式次第」です。
しかし、いざ自分で作成するとなると「プログラムとどう違うのか?」「どのような内容を、どのような順序で書けばいいのか?」など、戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、式次第の概要や種類、作成方法、作成に役立つテンプレート、司会進行の例文までわかりやすく解説していきます。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
式次第とは

式次第とは、式典や催し事の流れを、箇条書きで記載した文書のことです。式典の進行を明確にし、主催者・参加者・登壇者といった関係者全員が流れを把握することを目的としています。
式次第を作成することにより、主催者側は計画通りに式を進行でき、参加者側は次に何が行われるのかを理解して安心して式典に参加できます。特に、格式の高い式典においては、厳粛で円滑な進行が求められるため、式次第の役割は非常に重要です。
【式次第を使用する場面の例】
- 創立記念式典・周年記念式典
- 祝賀会
- 入社式・内定式
- 退任式・就任式
- 株主総会
- 竣工式・落成式
- 地鎮祭
- 結婚式、披露宴
- 告別式
プログラムとの違い
式次第とよく似た言葉に「プログラム」がありますが、使われる場面や内容に違いがあります。
まず「式次第」は、入社式や周年式典、株主総会など、儀礼や格式が重視される式典で使用される言葉です。記載内容は、登壇者の順番や進行の流れだけをまとめた、シンプルかつ厳粛な構成が基本です。
一方、「プログラム」は、演劇・音楽ライブ・発表会など、娯楽性のあるイベントでよく使われます。出演者の紹介や演目の解説、プロフィールなどが記載されることが多く、読み物としての要素を含むのが特徴です。
式次第の種類

式次第には、「掲示用」と「配布用」という2つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、式典の規模や目的に応じて使い分けましょう。
掲示用
掲示用の式次第は、会場の入口や壇上の脇、ステージの背面など、視認性の高い場所に設置される大型の式次第です。奉書紙や模造紙などに、毛筆やマーカーで大きく手書き、または印刷します。
【掲示用のメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
|
|
配布用
配布用の式次第は、参加者一人ひとりに配布する、A4やB5サイズなどの用紙に印刷する式次第です。式典の受付で渡したり、各席にあらかじめ設置しておいたりします。三つ折りにして席札と兼用にするといった使い方も可能です。
【配布用のメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
|
|
式次第の書式

式次第には、主に縦書きと横書きという2つの形式があります。また、式の格式に合わせて用紙やフォントを選ぶことも重要です。
縦書き・横書き
式次第の形式には縦書きと横書きがあり、それぞれ書き方のルールが異なります。ここで、形式ごとのポイントを詳しく見ていきましょう。
縦書きの場合
式次第を縦書きで作成する場合は、以下のポイントを意識しましょう。
- 中央上部に「〇〇式典 式次第」のように表題を大きく書く。
- 進行項目を右側から順に記載する。
- 各項目の頭には「一、」(漢数字のいち)を付ける。一つという意味合いで、すべての項目に「一、」と書く。例:「一、開会の辞」「一、社長挨拶」
横書きの場合
式次第を横書きで作成する場合のポイントは、以下の通りです。
- 上部中央に表題を大きく書く。
- 進行項目は上から順に記載する。
- 項目のナンバリングは、縦書きと同様に「一、」とするのが丁寧だが、「1.」「2.」といった算用数字で振っても問題ない。特に、時間を記載する場合は算用数字の方が見やすい。
用紙やフォントの選び方
式次第の印象は、使用する用紙やフォントによっても大きく変わります。
用紙を選ぶ際は、次のような点を意識しましょう。
- 式典の雰囲気や格調に合っているか
- 掲示用か配布用か
- 費用
たとえば、歴史ある会社の式典には奉書紙や和紙が向いていますが、費用を抑えたい場合には上質紙がよく選ばれます。
【用紙の種類】
| 用紙の種類 | 概要 |
| 奉書紙・和紙 | 伝統的で格式高い印象を与えます。特に掲示用の式次第や、歴史のある会社の式典などにおすすめです。 |
| マットコート紙 | 光沢が抑えられたしっとりとした質感で、落ち着いた高級感を演出できます。配布用の式次第でよく採用される用紙のひとつです。 |
| 上質紙 | コピー用紙に近い質感ですが、より厚手でしっかりしています。シンプルで読みやすく、費用を抑えたい場合に適しています。 |
また、フォントを選ぶ際は、「伝統的な式典か、現代的なイベントか」「掲示用か配布用か」などを意識しましょう。
【フォントの選び方】
| フォントの種類 | 概要 |
| 明朝体 | 線の太さに強弱があり、知的で格調高い印象を与えます。厳粛な式典や伝統的な行事におすすめです。 |
| ゴシック体 | 線の太さが均一で、視認性が高く力強い印象です。モダンでわかりやすい紙面にしたい場合に適しています。 |
| 毛筆フォント | 手書きのような温かみと力強さを表現でき、格式を重んじる式典の表題などに使うと効果的です。 |
式次第の作成方法

式次第の作成方法には、大きく分けて次の3つがあります。
- 手書きで作成する
- 自社で印刷する
- 業者に依頼する
それぞれにメリット・デメリットがあるため、予算や式典の規模、かけられる時間などを考慮して最適な方法を選びましょう。
| メリット | デメリット | |
| 手書きで作成 |
|
|
| 印刷で作成 |
|
|
| 業者に作成を依頼 |
|
|
手書きで作成する
手書きによる作成は、掲示用の大きな式次第や、少人数のアットホームな会などで用いられる方法です。費用を抑えながらも、温かみや手作り感のある印象を与えたい場合に向いています。特に、奉書紙や和紙に毛筆で書くと、より一層厳かな雰囲気に仕上がります。
ただし、作成には一定の手間と時間がかかるため、大量作成には不向きです。書き直しが難しく、事前に鉛筆で下書きをする、練習を重ねるなどの準備をしておきましょう。
印刷で作成する
印刷による作成は、WordやPowerPointなどのソフトを使って作成する方法です。
インターネット上には無料のテンプレートが多数公開されているため、誰でも比較的簡単に作成できます。手書きよりも見栄えがよく、業者に依頼する場合よりも費用を抑えられる点もメリットです。
一方、プリンターや印刷用紙、インクなどが必要となり、一定のレイアウトの知識も求められます。印刷品質や用紙の質にも限界があるため、仕上がりにこだわりたい場合は注意が必要です。
業者に依頼する
業者への依頼は、デザインから加工までを業者に一貫して任せられる作成方法です。
担当者の負担が大幅に減るだけでなく、厚手の高級紙や箔押しといったプロならではの高品質な式次第が手に入るというメリットもあります。デザインの提案から任せられるため、初めて式次第を作成する場合でも安心です。
一方で、作成方法の中でもっとも費用がかかる点はデメリットと言えます。また、発注から納品までに時間がかかるため、依頼する際は業者との打ち合わせや修正対応も含めて、スケジュールに十分な余裕を持たせましょう。
なお、業者によって、費用やサービス内容は異なります。後悔しないためにも、必ず複数の業者から見積もりを取り、サービス内容とあわせて慎重に選びましょう。
式次第のテンプレート

ここでは、式次第の作成にすぐに使えるテンプレートを2種類ご紹介します。
テンプレート1:時間なし
以下は、各項目の開始時間を記載しないシンプルな形式のテンプレートです。厳粛な式典や、時間に縛られず柔軟に進行したい場合に適しています。
〇〇式典 式次第
一、開会の辞
一、主催者挨拶
一、〇〇〇〇
一、〇〇〇〇
一、閉会の辞
テンプレート2:時間あり
以下は、各項目の開始時刻を記載する形式のテンプレートです。参加者に進行スケジュールを明確に伝えたい場合や、時間管理が重要なイベントでの採用におすすめです。
〇〇の会 次第
10:00~ 開会の辞
10:05~ 主催者挨拶
10:15~ 〇〇〇〇
10:45~ 〇〇〇〇
11:30~ 閉会の辞
式次第の例文

ここでは、代表的なケースを挙げて、式次第の例文を紹介していきます。開催する式典に応じてフォーマルさや項目数も変化するため、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。
新年会・忘年会
新年会・忘年会は、一年の始まりや締めくくりに、社員の労をねぎらい、親睦を深めるための会です。比較的カジュアルですが、式次第を用意することで会全体が引き締まります。
【例文】
令和〇〇年度 株式会社〇〇 忘年会 次第
開会の言葉
社長挨拶
乾杯(発声:〇〇本部長)
食事・歓談
余興(〇〇部有志)
年間MVP表彰
中締めの挨拶(〇〇専務)
閉会の言葉
入社式
入社式は、新入社員を歓迎し、社会人としての自覚を促す式典です。社会人としての第一歩を踏み出す場としてふさわしくなるように、式次第を用意します。
【例文】
令和〇〇年度 株式会社〇〇 入社式 式次第
一、開式の辞
一、国歌斉唱
一、社是・経営理念唱和
一、社長訓示
一、役員紹介
一、辞令交付
代表 〇〇 〇〇
一、新入社員代表 誓いの言葉
新入社員代表 〇〇 〇〇
一、歓迎の言葉
先輩社員代表 〇〇 〇〇
一、閉式の辞
株主総会
株主総会は、事業年度の業績報告や重要事項の決議を行う会議です。会社法にて、会社の規模に関わらず、毎年開催するように定められています。
【例文】
第〇期 定時株主総会 式次第
一、開会宣言
一、議長挨拶
一、監査報告
常勤監査役 〇〇 〇〇
一、事業報告
代表取締役社長 〇〇 〇〇
一、決議事項
第一号議案:剰余金処分の件
第二号議案:取締役〇名選任の件
第三号議案:監査役〇名選任の件
一、質疑応答
一、議案採決
一、閉会宣言
周年記念式典
周年記念式典は、会社の節目を祝い、関係者への感謝を伝える式典です。
【例文】
創立50周年記念式典 式次第
一、開会の辞
一、国歌斉唱
一、社長式辞
一、来賓祝辞
〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇 様
一、祝電披露
一、社員表彰
一、謝辞
取締役 〇〇 〇〇
一、閉会の辞
式次第に沿った司会進行の例文

ここでは、創立記念祝賀会を例に、式次第に沿った司会進行の具体的な例文を紹介します。当日の進行台本を作成する際の参考にしてください。
開会宣言
開会宣言では、式典が始まることを宣言します。会場の空気を引き締め、参加者の注目を集める重要な段階です。参加者の意識を式典へと集中させるために、はっきりとした口調で宣言するのがポイントです。
【司会進行の例文】
「皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、『株式会社〇〇 創立30周年記念式典』を執り行います。
本日、司会進行を務めさせていただきます総務部の〇〇と申します。閉式までどうぞよろしくお願い申し上げます。」
開会の挨拶
開会の挨拶では、主催者の代表として社長が登壇し、式典開催にあたっての想いや感謝を述べます。紹介する際は、敬意を払い、丁寧な言葉づかいを心がけましょう。
【司会進行の例文】
「はじめに、主催者を代表いたしまして、弊社代表取締役社長、〇〇 〇〇より、皆様にご挨拶を申し上げます。社長、どうぞよろしくお願いいたします。」
(社長挨拶後)
「〇〇社長、ありがとうございました。皆様、今一度、盛大な拍手をお願いいたします。」
来賓祝辞
来賓を招いている場合は、お祝いの言葉をいただきます。相手の会社名、役職、氏名などの間違いは失礼にあたるため、間違えないように事前に何度も確認しましょう。
【司会進行の例文】
「続きまして、ご来賓の皆様を代表し、〇〇市長、〇〇 〇〇様よりご祝辞を賜りたく存じます。〇〇様、よろしくお願い申し上げます。」
(祝辞後)
「〇〇様、心温まるお祝いのお言葉、誠にありがとうございました。」
祝電披露
欠席した関係者などから寄せられた祝電を紹介します。すべては読み上げず、お名前だけを紹介し、代表的な祝電を数通読み上げるのが一般的です。
司会進行の例文:
「続きまして、本日ご臨席賜ることが叶いませんでした皆様より、多数の祝電を頂戴しております。誠にありがとうございます。
時間の都合により、まことに恐縮ではございますが、お名前のみご紹介させていただきます。
(会社名・氏名を数名読み上げる)
この他にも、多数の祝電を頂戴しております。会場後方に掲示しておりますので、後ほどご覧くださいませ。
それでは、いただきました祝電の中から、〇〇株式会社 代表取締役 〇〇様からのメッセージを代読させていただきます。」
乾杯
祝賀会の始まりを告げるために、全員で乾杯を行います。発声者を紹介し、参加者全員にグラスをかかげてもらうように促しましょう。
【司会進行の例文】
「皆様、お待たせいたしました。これより祝賀会に移らせていただきます。乾杯の音頭は、〇〇様にお願いしたく存じます。皆様、お手元のグラスのご用意をお願いいたします。それでは、〇〇様、よろしくお願いいたします。」
(乾杯後)
「〇〇様、ありがとうございました。それでは皆様、どうぞごゆっくりお食事とご歓談をお楽しみください。」
中締めの挨拶
中締めは、宴会の途中でいったん締めくくるための挨拶です。参加者が各々のタイミングで退席しやすくなるように、という配慮から行われます。用意した企画はここで終了しますが、参加者はすぐには退席せず、その後もしばらく歓談を続けられるのが一般的です。
【司会進行の例文】
「皆様、ご歓談中まことに恐縮ですが、宴もたけなわではございますが、ここで一旦、中締めとさせていただきたく存じます。締めの音頭は、弊社の常務取締役、〇〇にお願いいたします。
皆様、お席の周りでご起立の上、お手を拝借と存じます。それでは、〇〇常務、よろしくお願いいたします。」
(一本締めなどの後)
「ありがとうございました。これをもちまして中締めとさせていただきます。お飲み物やお料理はまだございますので、お時間の許す限りごゆっくりおくつろぎください。」
閉会の挨拶
閉会の挨拶では、宴会や式典が完全に終了することを伝えます。感謝の言葉と共に、忘れ物がないかの注意喚起や、今後の案内などを伝えましょう。
【司会進行の例文】
「なお、お帰りの際は、お忘れ物などなさいませんよう、今一度お手回り品をご確認ください。出口にてささやかではございますが、記念品をご用意しておりますので、どうぞお持ち帰りください。本日は誠にありがとうございました。」
式次第を作成する際の注意点

当者として信頼される式典を実現するためには、ただ項目を並べるだけでなく、細部にまで配慮することが求められます。ここでは、式次第を作成するうえで、特に注意すべき点を3つご紹介します。これらを押さえることで、ミスを防ぎ、より質の高い式次第が完成します。
誤字脱字がないか複数人で確認する
誤字脱字は些細なようでいて、式典の品位を損なうだけでなく、会社の信用問題にもつながりかねない重大なミスです。作成者一人の確認ではどうしても見落としが発生しやすいため、複数人で確認を行いましょう。
確認作業を行う際のポイントは、以下のとおりです。
- 印刷や配布の前には担当チームの複数人で声に出して読み合わせる
- 式典の準備に直接関わっていない第三者に確認してもらう
- 式典の最終責任者である部長や役員に内容を確認してもらう
まず、印刷や配布の前に複数人で声に出して読み合わせましょう。それに加えて、式典の準備に直接関わっていない第三者に確認してもらうことで、担当者だけでは気づきにくい間違いやわかりにくい表現などを客観的に発見できます。最後は、式典の最終責任者である部長や役員に内容を確認してもらい承認を得ることで、ミスを限りなく無くせるでしょう。
読みやすさを意識する
式次第は「読む」ものではなく「一目で把握する」ためのものです。デザインを優先するあまり、文字が読みにくくなってしまっては本末転倒であるため、誰にとっても視認性の高いデザインを心がけましょう。
【読みやすくするためのポイント】
- 明朝体やゴシック体などの基本的なフォントを使用する
- 文字サイズは小さすぎず、行間や全体の余白をゆったりと設ける
- 背景と文字には明確なコントラストをつける
- コーポレートカラーなどはアクセントとして上品に使う
時間配分に無理がないか確認する
時間配分をきちんと行えていない場合、式が冗長になって間延びしたり、逆に時間が足りなくなって慌ただしく終わったりしてしまいます。参加者全員が心地よく過ごせるよう、時間配分は慎重に確認しましょう。
確認する際は、スピーチなどの主要な時間だけでなく、登壇者の移動や準備、司会者の紹介といった、数分単位の「隠れた時間」も含めることが重要です。また、予期せぬ遅延に備えて、「予備の時間」の確保も忘れてはなりません。プログラムを詰め込みすぎず、要所に5分程度の余裕を持たせておきましょう。
式次第に関するよくある質問

最後に、式次第について寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
Q.式次第とは?
A.式典やイベントの進行順序を箇条書きで記した文書のことです。参加者や運営関係者全員が、式の流れを把握するためのもので、円滑な進行に欠かせません。
Q.式次第とプログラムの違いは?
A.一般的に「式次第」は、創立記念式典や入社式など、格式が求められる式典で使われます。一方、「プログラム」は、コンサートや発表会など、娯楽性の高いイベントで使われることが多いという違いがあります。
Q.式次第はどのように作成するの?
A.式次第の作成方法は、式典の規模や目的、予算に応じて次の3つの方法から選ばれるのが一般的です。
- 手書き:掲示用や少人数の会で、費用を抑えたい場合におすすめ
- PCで作成・印刷:WordやPowerPointなどのソフトを活用して作成する方法。テンプレートを活用することで、自社で手軽に作成できる
- 専門業者に依頼:高品質な式次第を作成したい場合に最適
まとめ

本記事では、式次第の概要や種類、作成方法、テンプレート、シーン別の例文、司会進行例、作成時の注意点に至るまで、わかりやすく解説しました。
式次第は、単なる進行表ではなく、式典の品質や印象を左右する重要な要素です。参加者への配慮を忘れず、細部までこだわって作成することで、厳粛で心に残る式典を実現できるでしょう。ご紹介したテンプレートや例文、注意点などを、ぜひ式典の運営にお役立てください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る