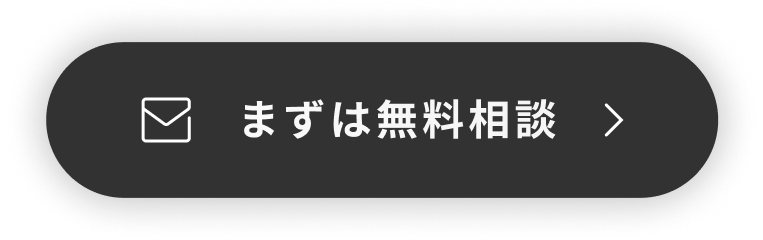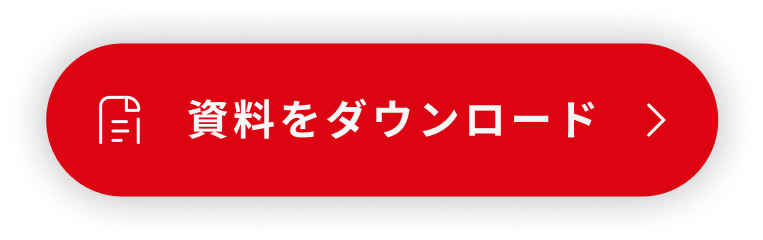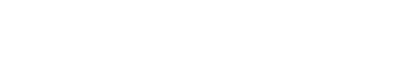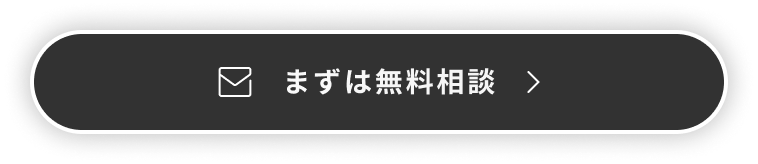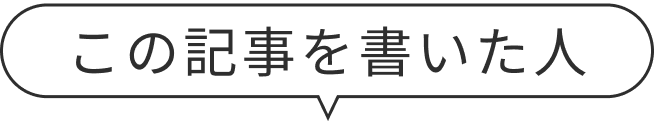スポーツフェスとは?メリットや開催手順・おすすめの企画を解説
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月31日



目次
「社員同士の団結力を高めたい」「地域の交流を活性化したい」「子どもたちに協力する楽しさを伝えたい」など、そのような思いを抱えている企業や自治体、学校関係者の方も多いのではないでしょうか。
そのような課題を解決する手段として、注目されているのが「スポーツフェス」の開催です。
この記事では、スポーツフェスの概要から、開催するメリット・デメリット、準備の流れ、おすすめの企画までをわかりやすく解説します。
スポーツフェスとは

スポーツフェスとは、勝敗を競うことよりも「楽しむこと」を重視した、フェス形式のスポーツイベントです。年齢や性別、運動経験の有無に関わらず、誰でも気軽に参加できます。
会社の社内イベントとしてはもちろん、地域のレクリエーションや学校行事としても幅広く活用されています。「参加者の一体感を高めたい」「健康への関心を促したい」「世代を超えたつながりを生み出したい」といったさまざまな目的に対応できる柔軟なイベントです。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
スポーツフェスを開催するメリット
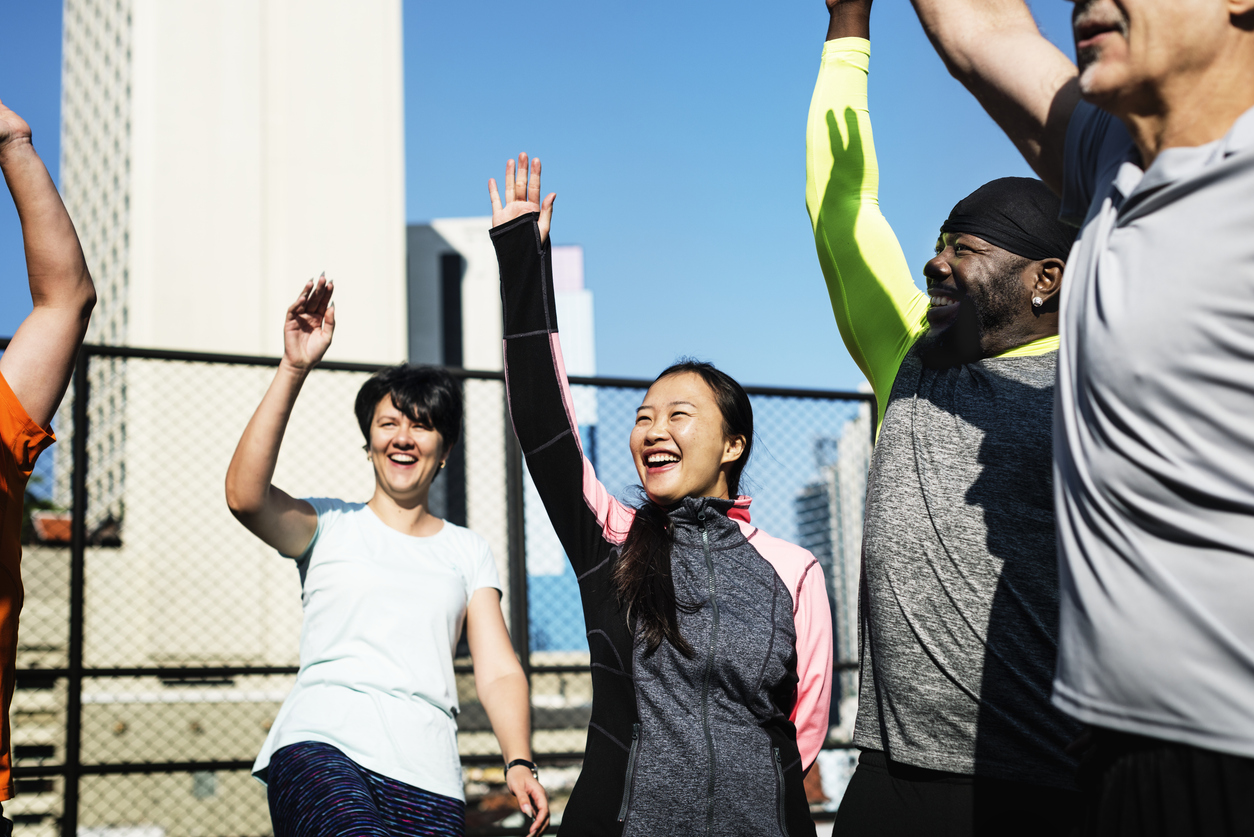
スポーツフェスは、参加者に楽しいひとときを提供するだけでなく、主催する会社や自治体、教育機関にとっても、多くのメリットがあります。
ここでは、特に期待される3つのメリットをご紹介します。
- 参加者同士の一体感を高められる
- コミュニケーションの促進につながる
- 健康促進やリフレッシュの機会を提供できる
参加者同士の一体感を高められる
スポーツフェスは、日常とは異なる“非日常”な空間で、共通の目標に向かって体を動かすという特別な体験を共有する機会です。競技中に声をかけあったり、応援したりすることで、勝敗の喜びや悔しさを分かち合えて、参加者同士の心の距離が一気に縮まります。
たとえば、チーム対抗リレーや全員参加型のゲームでは、立場や年齢に関係なく自然に助け合う雰囲気が生まれます。チームで役割を決めたり、作戦を考えたりする時間を設けることで、ただ一緒に参加するだけよりも深い関わりが生まれるため、イベント終了後関係づくりにもつながります。
また、「同じ目標を達成した」という感覚は、会社であれば社員同士の結束力を、学校であれば学級の団結力を、地域であれば住民間のつながりを、より強固なものにしてくれるでしょう。
コミュニケーションの促進につながる
スポーツという共通のテーマがあることで、立場や世代を超えて、会話のきっかけが生まれやすくなります。初対面同士でも「どの競技に出ますか?」「ナイスプレーでしたね」といった声掛けから交流が始まり、すぐに打ち解けられるのもスポーツフェスならではの魅力です。
会社では部署や役職の垣根を超えた関係づくりが、学校では学年やクラスを超えたつながりが、地域では年齢や生活背景の異なる住民同士の理解が深まることが期待できます。
そのようにして生まれたつながりは、日常の仕事や学習・地域活動にもよい影響をもたらし、「相談しやすい」「頼り合える」といった関係性の土台を築くことにもつながります。
健康促進やリフレッシュの機会を提供できる
スポーツフェスでは、楽しみながら体を動かせるため、健康づくりやリフレッシュの機会として大きな効果があります。会社では社員の運動不足やストレスの軽減に、学校では運動の楽しさや協調性を学ぶきっかけに、地域では健康意識の向上や医療費の抑制などにつながるでしょう。
特に、日頃なかなか運動する機会がない人にとって、スポーツフェスは体を動かす喜びを再発見する機会です。「またやってみよう」と思える体験は、継続的な健康習慣を身につけるきっかけにもなります。
なお、運動が得意でない人や高齢の方、小さな子どもでも参加できるように、遊びの要素を取り入れた種目を組み込むことがおすすめです。
スポーツフェスを開催するデメリット

スポーツフェスの開催には多くのメリットがありますが、その反面、主催者が押さえておくべきデメリットもあります。
ここでは、事前に把握しておきたい2つのデメリットをご紹介します。
- 準備に手間と時間がかかる
- 怪我や事故のリスクがある
準備に手間と時間がかかる
スポーツフェスを成功させるには、企画の検討から当日の運営まで、多くの準備が必要です。特に初めて開催する場合は、何から進めればよいか迷うこともあるでしょう。
企画の決定や予算の調整、会場や備品の手配、タイムスケジュールの作成、役割分担の調整など、やるべきことは多岐にわたります。参加者が多ければ多いほど、連絡や調整などにも手間がかかります。
担当者一人に負担が偏らないよう、協力メンバーを募り、チームで役割を分担することが大切です。地域イベントや学校行事であれば、保護者や町会・PTAなど外部との連携体制を整えることで、より円滑に準備を進められます。無理のない予定を立て、余裕を持って準備を進めましょう。
怪我や事故のリスクがある
スポーツフェスでは、転倒や衝突、無理な動作による怪我など、想定外のアクシデントが起こる可能性があります。リスクをできるだけ抑えるためには、事前にしっかりと対策を講じておくことが欠かせません。
たとえば、準備運動の時間を設ける、年齢や体力に配慮した種目構成にする、競技ごとの注意事項をしっかり説明するなどの工夫を行いましょう。
また、救護スタッフの配置や応急処置キットの準備、近隣の医療機関の連絡先の把握も、忘れずに行います。万が一に備えて、イベント保険への加入も検討しておくと安心です。
スポーツフェスを開催する流れ

ここでは、目的の決定から当日の運営まで、主催者が押さえておきたいスポーツフェスの開催手順をご紹介します。
- 目的を決める
- 日時と会場を決める
- 企画を選ぶ
- 告知する
- 備品を用意する
- 当日はチームで運営する
1.目的を決める
まず「このイベントの開催で何を実現したいのか」という目的を明確にします。目的を言語化することで、企画の内容・対象者・進行の方針などが自然と定まり、ブレのないイベント設計につながります。
以下に、主催者ごとの目的の例をまとめました。
| 主催者 | 目的の例 |
| 会社 |
|
| 学校 |
|
| 地域 |
|
2.日時と会場を決める
多くの人に参加してもらうためには、適切な日時設定と、それに見合った会場選びが欠かせません。
まず日時は、参加者にとって集まりやすい日程を選びます。会社の場合は平日の午後、地域イベントや学校行事の場合は週末や祝日が定番です。季節によって気温や天候も変わるため、屋外開催であれば気候面の配慮も必要です。
会場に関しては、目的や参加人数、実施する企画に応じて候補を絞っていきます。人気の施設はすぐに予約が埋まるため、遅くとも2〜3か月前には手配を進めましょう。
会場を選ぶ際のポイントは、以下の通りです。
- 競技に適した広さがあるか
- トイレ・更衣室・電源などの基本設備が整っているか
- 公共交通機関での来場が可能か
- 十分な広さの駐車場はあるか
- 滑りやすい場所や段差がないか
- 高齢者や車椅子利用者への配慮があるか
こうした条件を事前に確認しておくことで、当日の混乱やトラブルを避け、参加者にとって快適なイベント環境を提供できます。
3.企画を選ぶ
参加者にどのような体験をしてもらいたいかをもとに、競技やアクティビティなどの企画を選びます。
体力差や年齢差があっても楽しめる企画を取り入れることで、全員が“自分ごと”として参加しやすくなります。
プログラムを検討する際は、団体戦、個人戦、レクリエーション系などの企画をバランスよく組み合わせるのがポイントです。また、進行にメリハリをつけるために、競技ごとの所要時間や休憩のタイミングを含めたタイムスケジュールも併せて作成しておくと、当日も円滑に運営できます。
4.告知する
イベントの内容が決まったら、対象者に向けてわかりやすく情報を発信しましょう。
会社なら社内メールや掲示板、学校ならお便りや配布プリント、地域イベントならチラシや自治体の広報紙、SNSなど、対象者に合わせて適切な告知手段を選びます。
タイトルやビジュアルを工夫すると、注目を集めやすく、参加率の向上が期待できます。申し込み方法や締切日、持ち物などの必要情報は忘れずに明記し、問い合わせ対応の準備も整えておきましょう。
5.備品を用意する
企画や会場が決まったら、開催に必要な道具と設備を洗い出し、手配します。
| 必要な備品の例 | 概要 |
| スポーツ用具 | 競技やアクティビティを行うために必要なボール、縄跳び、ラケットなどの道具 |
| ビブス(ゼッケン) | チームや参加者を区別するためのユニフォーム代わりの目印 |
| 得点ボード | 各チームや個人の得点を表示し、進行状況をわかりやすく伝えるためのもの |
| 音響機器 | 会場全体に音楽やアナウンスを届けるためのスピーカーやアンプ |
| マイク | 司会進行や競技の説明をする際に使用するもの |
| テント | 屋外会場での受付、休憩所、雨天対策として活用するもの |
| 救護用品 | 転倒や怪我があった際に応急処置をするための包帯や消毒液など |
| 参加賞・景品 | 参加者のモチベーションを高めるための記念品、競技の上位入賞者への賞品など |
効率的に準備を進めるには、備品リストを作成して、チーム内で担当を割り振るのが効果的です。自治体の貸し出しや、レンタル業者の活用も視野に入れて、費用や工数を抑える工夫をしておきましょう。
6.当日はチームで運営する
当日は、運営チーム全員で協力して運営を行います。受付、司会、進行管理、審判、備品管理、誘導、救護対応、写真・動画撮影など、それぞれの担当で責任を持って対応できる体制が理想です。急なトラブルにも柔軟に対応できるよう、トランシーバーやグループチャットなど、スタッフ間の連絡手段を用意しておくと安心です。
イベントが終了したら、片付けと清掃を丁寧に行います。きれいな状態に戻すことで、会場の管理者や貸出元からの信頼を得られ、次回の会場や備品の手配がしやすくなるでしょう。
スポーツフェスにおすすめの企画

ここでは、スポーツフェスが盛り上がるおすすめの企画をご紹介します。年齢や体力に関係なく楽しめる企画を中心に選んでいるため、イベントの目的や参加者に合わせて取り入れてください。
| おすすめの企画 | おすすめの理由 |
| チャンバラ合戦 | スポンジ製の刀で相手が腕につけているボールを落とすアクティビティ |
| 水合戦 | 水鉄砲で相手チームのワッペンを濡らして退場させる夏限定の企画 |
| ドッヂビー | 柔らかいフライングディスクを使ったドッジボール風のアクティビティ |
| バブルボール相撲 | 大きなバブルボールに入ってぶつかり合い、相手をリングから押し出す競技 |
| ダブルダッチ | 2本の縄を交互に回し、その中でリズムよく跳ぶ競技 |
| 卓球バレー | 卓球台の周りに椅子を配置し、1チーム6名で行うバレーボール形式の競技 |
| 玉入れ | 制限時間内にチーム全員で協力して、より多くの玉をカゴに入れることを目指す競技 |
| スポーツクライミング | 人工の壁を登り、ゴールを目指す競技 |
| 体力測定会 | 握力や反復横跳びなどの測定で体力や健康状態を数値化できる企画 |
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀を使い、腕につけたボールを落とし合うチーム対抗型のアクティビティです。敵のチームを全滅させるか、あるいは制限時間内に相手チームのボールをより多く落としたチームが勝ちとなります。
ゲームの前には「軍議」と呼ばれる作戦会議の時間があり、戦略を立てたり役割を分担したりすることで、チーム内のコミュニケーションが活発になる点が魅力です。使用する道具は柔らかい素材で安全性が高く、子どもから大人まで誰でも楽しめます。
さらに、オリジナルの陣羽織や甲冑の貸し出しも可能です。戦国風の演出や衣装を取り入れることで、イベントの非日常感を一層高められます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 作戦会議や役割分担を通じて自然にチームワークが育まれる
- 安全性が高く、子どもから大人まで幅広く楽しめる
水合戦
水合戦は、火縄銃型の水鉄砲を使って、相手チームの胸元につけたワッペンを狙う、夏季限定のアクティビティです。魂に見立てたワッペンが濡れた時点でそのプレイヤーは退場となり、制限時間内により多くの相手を倒す、または相手チームを全滅させたチームが勝利となります。
チャンバラ合戦と同様に、戦いの前には作戦会議の時間が設けられています。チームメンバーで戦略を練り、協力して相手チームの全滅を目指す過程で、自然と距離が縮まるでしょう。
水を使ったアクティビティならではの涼しさや爽快感があり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 夏らしい爽快感があり、盛り上がりやすい
- 戦略を立てて協力し合うため参加者同士の交流が深まる
ドッヂビー
ドッヂビーは、ウレタン製の柔らかいフライングディスクを使った、ドッジボール風のアクティビティです。ルールはドッジボールとほとんど同じで、ディスクが当たったプレイヤーは外野に出て、外野から当て返すことで内野に復帰できます。
接触がないため、小さな子どもから高齢者まで安心して参加できます。また、フライングディスクは軌道が不規則で予測しづらく、予想外の展開が多く生まれる点もおすすめのポイントです。運動が苦手な人でも、パスやキャッチでチームに貢献できるため、誰でも楽しめます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 接触がなく安全で、年齢を問わず誰でも参加できる
- ディスクの動きが予測できず、意外性があって盛り上がる
バブルボール相撲
バブルボール相撲は、大きなビニール製のバブルボールに体を入れてぶつかり合い、相手をリングの外に押し出す対戦型のアクティビティです。参加者はバブルボールの反発力を利用してぶつかり合うため、運動経験や年齢に関係なく、誰にでも勝つチャンスはあります。
転倒してもバブルがクッションになるため、安全に楽しめるのが特徴です。また、見た目のインパクトや面白い動きにより、参加者だけでなく観客も楽しめます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 見た目のインパクトが大きく、観客も楽しめる
- 転倒しても安全で、体力差があっても勝負がしやすい
ダブルダッチ
ダブルダッチとは、2本の縄を交互に回し、その中でリズムよく跳ぶ縄跳び競技です。2人がロープを回し、1人以上がその中で縄に引っかからないようにジャンプを続けるのが基本ルールとなります。
縄に引っかからずに飛び続けるためには、縄を回す人と飛ぶ人が息を合わせる必要があり、自然とチームワークが生まれます。初心者でもインストラクターの指導があれば、短時間でコツを掴めるため、子どもから大人まで幅広い世代が気軽に楽しめます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 息を合わせる必要があり、チームワークの向上につながる
- 初心者でも短時間でコツをつかめるため参加しやすい
卓球バレー
卓球バレーは、卓球台の周りに、1チーム6名が椅子に座って行う、バレーボール形式のスポーツです。ラケットでピン球を転がし、ネットを挟んで相手コートへ3打以内で返すというのが基本ルールです。1セット15点、3セットマッチで2セットを先に取ると、勝利となります。
体力差や障がいの有無を問わず、誰でも参加できる点が魅力です。卓球台とその周りに椅子を置く広さがあれば、広さが限られた会場でも実施できるため、さまざまな規模のスポーツフェスに取り入れられています。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 限られたスペースでも開催できるため取り入れやすい
- 年齢や体力差に関係なく一緒に楽しめる
玉入れ
玉入れは、制限時間内にできるだけ多くの玉を、カゴに投げ入れて得点を競う競技です。ルールは簡単で、カゴに多くの玉を入れたチームが勝利となります。カゴを移動式にしたり、玉の色ごと得点を設定したりすることで、戦略性が高まって楽しさも増すでしょう。
誰でも理解しやすいルールのため、小さな子どもから高齢者まで幅広い層の人が参加できるのが特徴です。また、限られた時間の中でチーム全員が協力して玉を入れる必要があり、自然と一体感が生まれます。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 準備が簡単で、道具が少なくても実施できる
- 制限時間内に協力し合うことで一体感が生まれやすい
スポーツクライミング
スポーツクライミングは、安全装置を身につけて人工の壁を登り、上部のゴールを目指す競技です。
クライミングのルートにはさまざまな難易度があり、ルートを選ぶことで、初心者から上級者まで自分のレベルに合わせて挑戦できます。制限時間を設けたり、到達地点で得点をつけたりするルールを加えることで、ゲーム性が増してより盛り上がります。
高所にゴールに向かって挑む緊張感や、登りきったときの達成感は、参加者の記憶に強く残るでしょう。自然と声援が集まりやすく、会場全体が活気づくのも魅力です。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- ゴール到達の達成感が大きく、会場全体が盛り上がる
- 観客の応援が自然と生まれやすく、一体感を作りやすい
体力測定会
体力測定会は、参加者が自分の体力や健康状態を数値として把握できる企画です。代表的な測定項目には、握力や垂直跳び、長座体前屈、反復横跳びなどが挙げられます。
参加者に測定結果を記載した記録カードを配布すれば、健康維持へのモチベーション向上につながるでしょう。競技性よりも個人の変化や成長を重視する内容のため、運動が得意でない方でも参加できます。社員の健康づくりや地域の健康促進イベントとしても取り入れやすいです。
【スポーツフェスにおすすめの理由】
- 個人の成長や変化を数値で実感でき、健康意識向上につながる
- 運動が苦手な人でも参加しやすい
スポーツフェスを開催する際の注意点

スポーツフェスを計画通りに進めることは、主催者にとって大きな課題の一つです。しかし、当日は受付が混雑したり、企画の開始が予定より遅れたりするなど、予期せぬことで時間が押してしまうことも少なくありません。
タイムスケジュールは詰め込みすぎず、各プログラムの間に予備の時間を設けておくと、焦らずに進行できます。また、屋外で開催する場合は、雨天時の中止や延期の基準を設定し、代替日や連絡方法などもあわせて参加者に周知しておきましょう。それにより、天候による混乱や不安を最小限に抑えられます。
スポーツフェスに関するよくある質問

ここでは、スポーツフェスについて寄せられることの多い質問とその回答をご紹介します。
スポーツフェスとは何ですか?
スポーツフェスとは、勝ち負けよりも「楽しむこと」を目的としたスポーツイベントです。年齢や性別、運動経験を問わず、誰でも気軽に参加できます。
スポーツフェスを開催するメリットは?
スポーツフェスの開催によって、主に以下の3つのメリットが期待できます。
- 参加者の一体感を高められる
- コミュニケーションの促進につながる
- 参加者に健康促進やリフレッシュの機会を提供できる
スポーツフェスを開催するデメリットは?
スポーツフェスを開催する主なデメリットは、以下の2つです。
- 準備に手間と時間がかかる
- 参加者の転倒や衝突といった怪我や事故のリスクがある
まとめ

スポーツフェスは、参加者同士の一体感を育み、世代や立場を超えた交流を生み出し、さらには健康意識の向上にもつながるイベントです。準備や運営には時間と手間がかかりますが、それ以上に得られるものは大きく、参加者にとっても主催者にとっても、忘れられない一日となるでしょう。
本記事を参考に、ぜひ自分たちの目的や参加者に合わせたスポーツフェスを運営してみてください。
IKUSAは、年間1,000件以上の面白いイベントや研修を支援している会社です。90種類以上のイベント・研修サービスからお客様のニーズに合わせてご提案させていただき、ご要望に応じてカスタマイズも行います。社内イベントや地域イベントなどでスポーツフェスの開催を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る