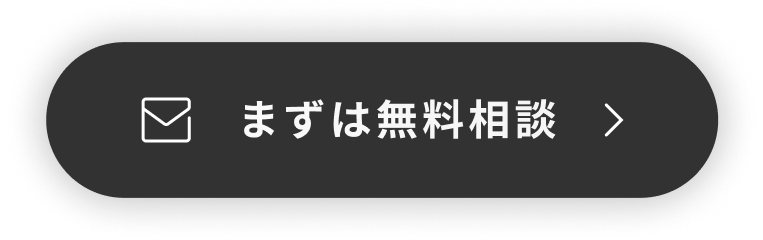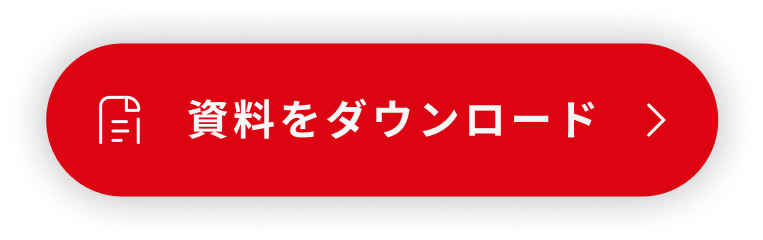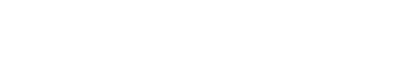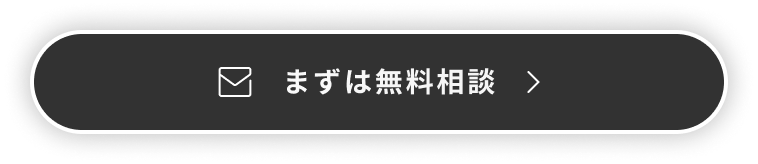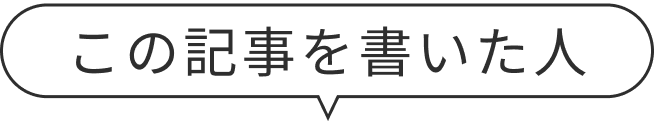鏡開きとは?酒樽を開くやり方や祝賀会におすすめの企画を紹介
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年7月31日



目次
新年会や周年記念式典、竣工式など、会社のお祝いの席で「鏡開き」が行われるのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。鏡開きは、会場の雰囲気を華やかにし、参加者の一体感を高める伝統的な儀式です。
しかし、いざ自社で実施するとなると、「そもそも鏡開きとは?」「どのような準備が必要なの?」など、わからないことが出てくるかもしれません。
本記事では、鏡開きの意味や由来といった基礎知識から、実施するメリット、具体的な準備や当日の流れ、さらには祝賀会を盛り上げるおすすめの企画まで、幅広く解説します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
鏡開きとは

鏡開き(かがみびらき)とは、日本酒の入った酒樽の蓋を木槌で勢いよく開けて、そのお酒を参加者に振る舞う儀式のことです。丸い樽の蓋を「鏡」に見立て、「未来を切り開く」という願いが込められています。
単なる演出ではなく、「健康」や「幸福」を祈願する日本の伝統的な文化です。参加者同士でその思いを分かち合えることから、今もさまざまな場面で行われています。
鏡開きの由来
諸説ありますが、鏡開きはもともと武家社会の儀式に由来するとされています。かつて武将たちは、戦いの前に勝利を祈り、酒樽の蓋を開けて仲間と酒を酌み交わしていました。このような風習は次第に広まり、やがて祝いの席で樽酒を開く儀式として定着し、現在の鏡開きへとつながっています。
酒蓋を開けることが鏡開きと呼ばれる理由
酒樽の丸蓋の形が、神様が宿るとされる「神鏡(しんきょう)」に似ていることから、「鏡」に見立てられています。そのため、蓋を開ける行為には、神様からの福を授かり、無病息災や家内安全、そしてこれからの発展を願うという意味が込められています
なお、祝いの席では「割る」や「切る」といった言葉は縁起が悪いとされるため、「鏡を割る」ではなく「鏡を開く」と表現されます。そうした言葉選びにも、鏡開きに込められた前向きな願いや思いが表れています。
ビジネスシーンで鏡開きを行うタイミング

家庭で鏡餅を食べる鏡開きは、一般的に1月11日に行われます。しかし、会社のイベントで酒樽の鏡開きを行う場合は、この日付にこだわる必要はありません。会社の新たな門出や節目を祝うタイミングで、年間を通じて自由に実施されています。
ここでは、ビジネスシーンにおける鏡開きの代表的なタイミングをご紹介します。
新年会
新年会は、新しい年を迎えたことを祝い、社員の士気を高めるイベントです。鏡開きは、「今年一年の成功と発展を切り開く」という願いを込めた演出として適しています。
役員や管理職が力強く樽を開き、社員全員で乾杯することで、会社全体の一体感が生まれます。年頭の挨拶とあわせて鏡開きを行えば、社員の記憶に残る、華やかな新年会となるでしょう。
周年記念式典
会社の創立記念や節目の年を祝う周年記念式典は、会社の歴史を振り返り、社員や関係者に感謝を伝える機会です。周年記念式典で鏡開きを行えば、会社の「末広がりな未来」への願いを式典に込められます。
創業当時から会社を支えてきた功労者や、長年の取引先などを招いて鏡開きを行えば、感謝の気持ちを形にして伝えることが可能です。これまでの歩みと、これからの希望を共有できる感動的な演出となるでしょう。
竣工式
新社屋や新工場の完成を祝う竣工式でも、鏡開きは定番の演出です。建物の無事な完成を祝い、今後の事業の安全と繁栄を祈る意味があります。
工事に携わった関係者を招待し、ともに鏡開きを行うことで、プロジェクトの成功を共有し、感謝の気持ちを伝えられます。会社の新たな門出を力強く印象づける、晴れやかな式典にふさわしい企画です。
会社が鏡開きを行うメリット

鏡開きは、伝統的な儀式にとどまらず、会社に多くのメリットをもたらします。ここでは、会社が鏡開きを行う主なメリットを説明します。
- 社員の士気を高められる
- 会社への帰属意識が高まる
- ブランディングにつながる
社員の士気を高められる
鏡開きは、日常とは異なる体験として、会場に特別感をもたらします。役員や社員が声をあわせて「よいしょ、よいしょ、よいしょー!」という威勢のよい掛け声とともに木槌を振り下ろす瞬間は、会場に一体感と高揚感を生み出します。
そのような体験を共有することで、社員同士の結束力が高まり、「この会社の一員でよかった」という誇りや前向きな気持ちが芽生えるきっかけになります。結果として、仕事へのモチベーション向上にもつながるでしょう。
会社への帰属意識が高まる
周年記念式典など、重要な節目の式典で鏡開きを取り入れることで、社員は「この大切な場に自分も立ち会っている」という実感を持ちやすくなります。
鏡開きは、会社の代表者が中心となって行う儀式ですが、その瞬間を参加者全員で見守り、喜びを分かち合うことで、会場に一体感が生まれます。社員一人ひとりに「自分も会社を支えている」という意識が芽生え、帰属意識の醸成につながります。
そうした体験は、式典に参加するだけでは得にくい一体感や誇りを育み、会社への愛着や貢献意欲の向上にもつながるでしょう。
ブランディングにつながる
鏡開きは、日本らしい格式ある伝統的な演出です。式典の様子を写真や動画に収めて、プレスリリースや自社のWebサイト、公式SNSなどで発信すれば、社外に対して効果的なブランディングを行うことができます。
例えば、取引先や顧客に対しては「伝統を重視する信頼できる会社」というイメージを、求職者には「社員の一体感を大切にする活気のある会社」というイメージを与えられます。
会社が鏡開きを行うデメリット

鏡開きは多くのメリットがある一方で、覚えておきたいデメリットもあります。ここでは、会社が鏡開きを行うデメリットを2つ紹介します。
- 費用がかかる
- 準備と片付けに手間がかかる
費用がかかる
鏡開きを行うには、ある程度の費用がかかります。主な内訳は、以下の通りです。
- 酒樽本体のレンタル料・購入費
- 中に入れる日本酒の代金
- 木槌のレンタル料・購入費
- 柄杓のレンタル料・購入費
- 参加者に振る舞うための枡のレンタル料・購入費
参加人数が多かったり、本格的な菰樽(こもだる)を使用したりする場合は、数十万円もの費用が発生することもあります。複数の業者から見積もりを取り、予算内で収まるように計画を立てましょう。
準備と片付けに手間がかかる
円滑に鏡開きを行うには、本番で蓋がうまく開くように調整したり、会場を設営したりといった準備が必要です。また、式典後には、酒樽の撤収や、こぼれたお酒の清掃、使用した枡の洗浄・返却など、後片付けにも相応の手間と時間がかかります。
鏡開きを取り入れた式典の準備
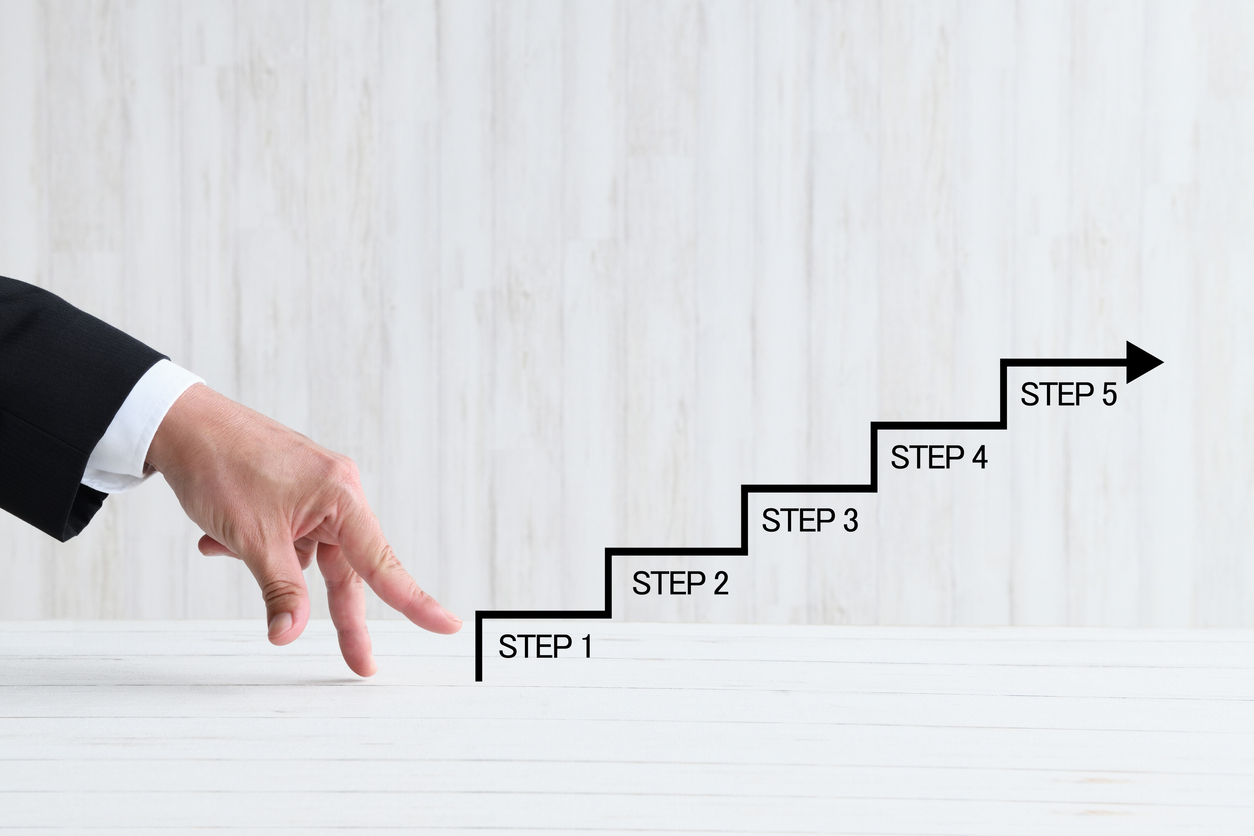
鏡開きを取り入れた式典を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。段取りを怠ると、当日の進行が滞るなど、せっかくのお祝いの式典が台無しになりかねません。
ここでは、担当者が行うべき準備を、5つの段階に分けて解説します。
- 目的を明らかにする
- 会場を選ぶ
- 酒樽や備品を用意する
- 当日の役割分担を行う
- 酒樽を開封する
1.目的を明らかにする
まずは、式典そのものを開催する目的をはっきりさせましょう。「誰に、何を伝え、どう感じてもらいたいのか」を具体的に考えることで、企画の方向性が定まります。
例えば、「社員の一体感を高めたい」「取引先への感謝を形にしたい」など、目的によって招待する人や演出の仕方が変わってきます。目的を明確にしたうえで、開催日時や会場、おおよその参加人数、予算などを盛り込んだ基本計画を立てましょう。
2.会場を選ぶ
鏡開きを行うには、酒樽を置ける十分な広さが必要です。ホテルの宴会場やイベントスペース、あるいは自社の敷地内などから、目的や規模に合った最適な会場を選びましょう。
会場を選ぶ際に確認しておきたいポイントは、以下の通りです。
- 酒樽(四斗樽で直径約60cm)の周りを参加者が囲める広さがあるか
- 床が汚れても清掃しやすいか、または養生シートなどを敷けるか
- 予定される参加人数が収容できる広さか
- 駅からのアクセスはよいか
- 駐車場はあるか
3.酒樽や備品を用意する
鏡開きに必要な酒樽や備品は、基本的には酒屋やイベント会社に依頼して手配します。酒樽には、菰(こも)が巻かれた本格的なものから、樽の形をしたステンレス容器に瓶の酒を入れる簡易的なものまでさまざまな種類があります。
また、酒樽の大きさは、参加人数や規模に合わせて選びましょう。目安を以下にまとめました。
| 酒樽の大きさ | 概要 |
| 一斗樽(いっとだる) | 内容量18L(一升瓶10本分)。50名以下の小規模な会におすすめ |
| 二斗樽(にとだる) | 内容量36L(一升瓶20本分)。50〜100名程度の中規模な会におすすめ |
| 四斗樽(よんとだる) | 内容量72L(一升瓶40本分)。100名以上の大規模な会におすすめ |
その他、木槌、柄杓、枡などの備品も忘れずに用意しましょう。これらは酒樽とセットでレンタルできる場合が多く、依頼の際にまとめて確認しておくと安心です。
4.当日の役割分担を行う
当日の運営を円滑に進めるために、あらかじめ役割を分担しておきましょう。主な役割には、以下のものがあります。
| 役割 | 概要 |
| 司会進行役 | 式典全体の進行を担当する |
| 鏡開きを行う人(登壇者) | 役員や主賓など、複数名にお願いする |
| 音頭を取る人 | 「よいしょ!」の掛け声で会場を盛り上げる。司会者が兼任することも可能 |
| お酒を振る舞う人 | 開いた樽から枡にお酒を注ぎ、参加者に配布する |
5.酒樽を開封する
酒樽は、木槌で叩くだけでは簡単には開きません。多くの酒樽は輸送中に中身が漏れないよう厳重に締められているため、鏡開きを円滑に行うには下準備が必要です。
- カッターや木槌、バール、タオル、ほうきなどを用意する。
- 樽の上部にある細い縄や太い縄をカッターで切って取り外す。
- 樽を覆っている菰(こも)を、内側にきれいに折り込む。
- 樽の側面を締めている竹の輪「タガ」を、木槌で叩いて少し下にずらし、蓋を開きやすくする。ただし、落としすぎると樽が分解してしまうので注意が必要。
- 蓋の縁にバールを差し込み、木槌で叩いて少しずつこじ開ける。この時点である程度蓋を浮かせておき、本番では軽く叩くだけで開くように調整しておく。
- 蓋を元に戻し、ホコリや虫が入るのを防ぐために、ラップなどをかけておく。
これらの準備は、酒屋やイベント会社のスタッフが行ってくれる場合もあるため、手配の際に確認しておきましょう。
基本的な鏡開きのやり方

ここでは、鏡開きのやり方を4つの段階に分けてご紹介します。
- 司会者が鏡開きを行うことを伝える
- 司会者が鏡開きの音頭を取る
- お酒を振る舞う
- 乾杯する
当日の進行に役立つ、司会者のアナウンス例もあわせて紹介するため、ぜひ参考にしてください。
1.司会者が鏡開きを行うことを伝える
祝賀会が始まり、主催者の挨拶や来賓の祝辞が終わったら、司会者が鏡開きを行うことを知らせます。これは、厳かな雰囲気から祝宴の華やかな雰囲気へ切り替える合図にもなります。
【アナウンス例】
「皆さま、お待たせいたしました。これより、〇〇株式会社の未来の発展を祈念いたしまして、鏡開きを執り行います。鏡開きを行っていただく皆さまは、どうぞステージへお上がりください。」
2.司会者が鏡開きの音頭を取る
登壇者が木槌を手にしたら、司会者が会場を盛り上げるための掛け声の練習を行います。このひと手間が、会場の一体感を生み出すため、掛け声の練習を挟むことがおすすめです。その後、参加者全員で鏡開きの音頭を取ります。
【アナウンス例】
「準備はよろしいでしょうか。皆さま、ご唱和をお願いいたします。せーの、『よいしょ、よいしょ、よいしょー!』」
登壇者は、掛け声に合わせて木槌を振り下ろし、酒樽の蓋を開きます。
3.お酒を振る舞う
無事に蓋が開いたら、振る舞い役のスタッフが柄杓で樽からお酒を汲み、参加者の枡に注いで回ります。お酒が飲めない方のために、お酒の代わりのソフトドリンクを用意しておくと親切です。
4.乾杯する
参加者全員にお酒やドリンクが行き渡ったら、代表者が乾杯の音頭を取り、乾杯の発声とともに祝宴が始まります。
【アナウンス例】
「それでは、〇〇株式会社のさらなる発展と、ご列席の皆様のご健勝を祈念いたしまして、乾杯!」
鏡開きの際の立ち位置の決め方

鏡開きを美しく、そして礼儀正しく行うには、登壇者の立ち位置について理解しておく必要があります。
基本的に、最も役職の高い主催者や主賓が、観客から見て中央に立ち、その左右に序列順に並びます。中央の右隣が2番目、左隣が3番目、と外側に向かって交互に並ぶのが一般的です。
また、バランスよく見えるように、酒樽一つに対して5〜6名程度で囲みましょう。参加者やカメラの位置から見やすいように、酒樽の正面は開け、半円を描くように囲んで立つことがおすすめです。
当日、写真や動画の撮影がある場合は、登壇者の目線や照明の当たり方なども確認しておきましょう。記念撮影のタイミングや目線を向ける方向などを事前に司会者や登壇者、カメラマンと共有しておくことで、素晴らしい写真や動画を円滑に残すことができます。
鏡開きで使用する酒樽の賞味期限

酒樽に入っているお酒は、生ものです。品質を保つために、賞味期限には注意が必要です。
未開封の場合、一般的に酒樽が到着してから2〜3週間程度が目安です。蔵元から出荷された時点から風味が落ちていくため、なるべく早く使用するのが望ましいでしょう。
一方、一度開封した樽酒は空気に触れて劣化しやすいため、できればその日のうちに、遅くとも1週間以内には飲み切るようにしてください。イベント後に残ったお酒は瓶などに移し替えて参加者に持ち帰ってもらうと、参加者にも喜ばれ、残ったお酒も有効に活用できます。
鏡開きを行う際の注意点

鏡開きを行う際は、参加者全員が気持ちよく参加できるよう、いくつかの点に配慮することが大切です。ここでは、主催者として押さえておきたい注意点を2つご紹介します。
- 「開く」という前向きな言葉を使用する
- 無理に飲酒を勧めない
「開く」という前向きな言葉を使用する
鏡開きはお祝いの席で行われるため、「割る」「切る」といった言葉は避け、「運を切り開く」「未来を開く」といった意味を込めて「(鏡を)開く」と表現しましょう。司会進行の際や、社内での案内においても同様です。細やかな配慮が式典全体の印象を良くします。
無理に飲酒を勧めない
鏡開きでは日本酒が振る舞われますが、参加者の中にはお酒が苦手な方や、健康上の理由、あるいは車で来場しているなどの理由で飲酒を控えている方もいます。
近年、飲酒を強要する「アルコールハラスメント」への社会的な意識が高まっています。お祝いの席だからといって飲酒を勧め過ぎると、会社の信頼を損ねることになりかねません。
お酒が飲めない方でも楽しめるよう、乾杯用にノンアルコール飲料やソフトドリンクを用意しましょう。お酒を注いで回る際も、「お酒でよろしいですか?」と一言添えるなどの配慮が大切です。
鏡開き以外で祝賀会におすすめの企画

鏡開きに加えて、会場をさらに盛り上げる企画を取り入れるのもおすすめです。ここでは、会社の祝賀会で人気のある企画を4つご紹介します。
| おすすめの企画 | 概要 |
| オール社員感謝祭 | 自社の歴史や理念、社員のエピソードなどを題材にしたオリジナルのクイズ大会 |
| ビンゴ大会 | 年齢や役職に関係なく誰でも楽しめる定番企画 |
| 格付けバトル | 牛肉や紅茶、絵画、俳句など多彩なカテゴリーで「一流の品」を見極めるクイズ型アクティビティ |
| 記念ムービーの上映 | 会社の設立からの歩みや周年事業の裏側、社員メッセージをまとめた映像を上映する企画 |
オール社員感謝祭
オール社員感謝祭は、自社の歴史や理念、社員にまつわる裏話などを題材にした、オリジナルのクイズ大会です。プロの司会者がテレビ番組のように進行を盛り上げ、参加者はスマートフォンで回答します。
会社の歴史や理念を楽しく学びながら、社員が主役になれる企画として、祝賀会にぴったりです。さらに、準備から当日の運営まで専門の会社に任せられるため、担当者の負担が少ないのも嬉しいポイントです。
個人戦として実施することも可能ですが、部署や役職を超えた交流を生みたい場合には、チーム対抗戦にするとよいでしょう。クイズの答えについて相談しあう中で、自然と会話が生まれ、一体感が生まれます。
ビンゴ大会
ビンゴ大会は、年齢や役職に関係なく、誰でも気軽に楽しめる定番の企画です。ルールが簡単でわかりやすく、番号が読み上げられるたびに会場のあちこちで歓声が上がり、会場全体が盛り上がります。
景品には旅行券や最新の家電といった豪華なものや、自社製品、社長賞など面白いものを用意すると、参加者の期待感が高まり、最後まで盛り上がりが持続します。
格付けバトル
格付けバトルとは、牛肉、紅茶、絵画、俳句などのさまざまなカテゴリーで、参加者が五感を使って「一流の品」と「そうでない品」を見極めるアクティビティです。参加者はテレビ番組のゲストになったような気分で楽しめます。
回答はスマートフォンやPCから専用のシステムを使って行い、その場でリアルタイムに集計されます。得点の変動がすぐにわかるため、最後の発表まで会場全体が一体となって盛り上がります。
また、既存のカテゴリー以外にも、事前に相談することで自社オリジナルの問題を出題することも可能です。自社製品や業界にまつわる内容を取り入れれば、より特別感のある企画に仕上がります。
記念ムービーの上映
会社の設立からの歩みや、周年記念事業の裏側、社員からのメッセージなどをまとめた記念ムービーを上映するのも、祝賀会におすすめです。プロジェクトの苦労や成功の喜びを映像で共有することで、社員の会社への愛着がより一層深まります。また、取引先などの社外関係者にも、会社の歴史や文化について知ってもらうよい機会となるでしょう。
鏡開きに関するよくある質問

ここでは、鏡開きについて寄せられることの多い質問とその回答をご紹介します。
酒樽を割ることを鏡開きと呼ぶのはなぜ?
酒樽の丸い蓋が、神様が宿るとされる「鏡」に見立てられているためです。また、お祝いの席で「割る」という言葉は縁起が悪いとされるため、「未来を切り開く」という意味を込めて「開く」という言葉が使われます。
鏡開きはどのような場合に行う?
新年会、周年記念式典、竣工式など、会社の新たな門出や節目を祝うおめでたい席で行われるのが一般的です。
会社が鏡開きを行うメリットは?
鏡開きの実施には、主に以下の3つのメリットがあります。
- 参加者の一体感が高まり、社員の士気が向上する
- 社員の帰属意識が高まる
- 会社のブランディング強化につながる
残ったお酒はどうすればよいですか?
事前に瓶やペットボトルなどの容器を準備しておき、参加者に持ち帰ってもらうことがおすすめです。開封後は風味が変わりやすいため、早めに飲み切るようアナウンスしましょう。
まとめ

鏡開きは、会社の新たな門出や節目を祝い、参加者の一体感を高められる儀式です。社員の士気や帰属意識を高められるほか、日本の文化を感じられる華やかな演出として会社のイメージ向上にもつながります。
本記事でご紹介した式典の準備や鏡開きの流れを参考にすれば、人事・総務担当者として、自信を持って鏡開きを運営できるはずです。さらに、クイズ大会や記念ムービーの上映といった他の企画と組み合わせることで、参加者の記憶に深く残る、より素晴らしい祝賀会をつくり上げることができるでしょう。
ぜひ本記事の内容を参考に、鏡開きを成功させてください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る