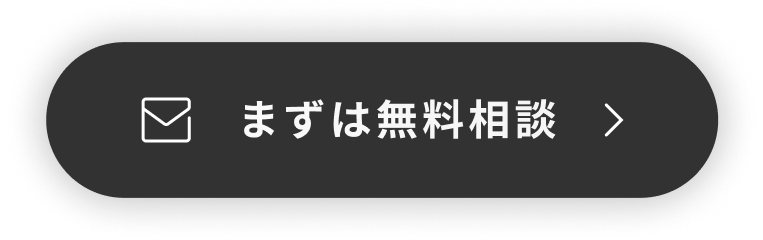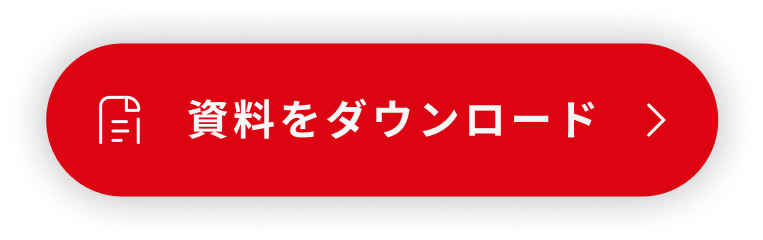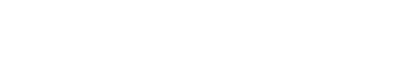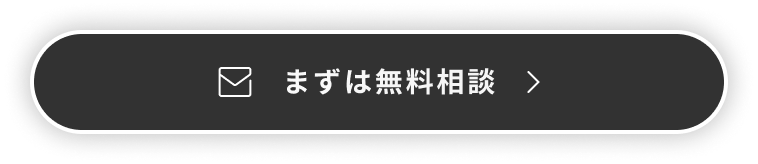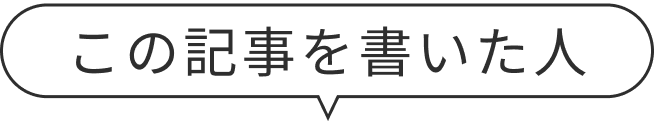社内イベントにおすすめの出し物40選
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年8月1日



目次
出し物とは、場を盛り上げたり、参加者同士の交流を促したりすることを目的に披露される企画や演目のことです。
本記事では、社内イベントにおすすめの出し物を実演型・鑑賞型・体験型・表彰型に分類して30選紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
【実演型】社内イベントにおすすめの出し物11選

ここからは、社内イベントにおすすめの実演型の出し物を11選紹介します。
楽器パフォーマンス
楽器パフォーマンスは、社員バンドによる生演奏で会場を盛り上げる実演型の出し物です。生演奏ならではの迫力や臨場感が参加者の印象に残りやすく、普段見られない社員に一面を知ることで、距離感が縮まるきっかけになることも期待できます。
実施する際は、会場の音響設備を確認し、演奏者との綿密な打ち合わせが不可欠です。
ダンスパフォーマンス
ダンスパフォーマンスは、有志で集まった社員によるダンス披露を通じて会場を盛り上げる実演型の出し物です。観客も自然と手拍子をするなど参加意識が高まることで一体感が生まれやすくなるでしょう。出演した社員への声かけによる交流促進が期待できます。
お笑い
お笑いは、大喜利やフリップ芸、漫才、コントなどを取り入れた実演型の出し物です。有志の社員でネタを披露したりする形式も考えられます。ユーモアを通じて会場の空気が和みやすく、笑いを共有することでコミュニケーションの活性化も期待されます。
実施の際は内容が特定の個人や価値観を揶揄するものにならないよう、事前に台本確認や趣旨の共有を行いましょう。
劇
社員による劇の発表は、脚本から演出、当日の発表までを自分たちで手がける実演型の出し物です。業務にちなんだパロディや会社の歴史を題材にすると、共感や笑いが生まれやすくなります。また、オリジナルで一から制作する方法もありますが、発表までの日数によってはオマージュ作品も選択肢に入れてはいかがでしょうか。
協力して作り上げることでチームの結束力が高まることが期待されますが、セリフ量や演出が負担にならないよう配慮し、参加者全員が楽しめる無理のない構成を心がけましょう。
プレゼンテーション
社員によるプレゼンテーションは、新規事業のアイデアや業務改善提案などを発表する実演型の出し物です。発表者にとっては思考を整理したり、伝える力を磨いたりする機会となるだけでなく、聴く側の業務への関心を高める双方向的な効果が期待されます。
実施にあたって、プレゼン内容を上司や関係者と方向性をすり合わせておくことで、プレゼン内容の質が高まるでしょう。また、周囲に相談することで、多くの視点が入り内容がより具体的になり、分かりやすく伝えられる可能性も期待できます。
タイムアタック
タイムアタック企画は、社員がルービックキューブやフラッシュ暗算などのクリアタイムを競う実演型の出し物です。集中力や瞬発力が試される緊張感は観客にも伝わり、会場の注目を集めやすいでしょう。挑戦内容が観客にもルールが伝わるよう工夫することが大切です。
何人かで並んで競う形にすることで、勝敗の行方に一層注目が集まり、盛り上がりが期待できるでしょう。
似顔絵パフォーマンス
似顔絵パフォーマンスは、社員がその場で希望者の似顔絵を即興で描く実演型の出し物です。特徴を捉えてながらもユーモアを交えた似顔絵は、描き手のセンスが光るでしょう。描き手とモデルの間でやり取りが生まれることで空気が和らぎ、似顔絵をきっかけに周囲の人とのコミュニケーションのきっかけにもつながることが期待できます。
また、描いている時間は見ている人にとって待ちの時間になるため、BGMを用意したり、過去に描いた作品を紹介したりすることでテンポが崩れない構成にすることも検討してみてください。
リフティングチャレンジ
リフティングチャレンジは、社員が交代でボールのリフティング回数に挑戦する実演型の出し物です。シンプルなルールながら、集中力やバランス感覚が求められ、見守る側も応援に熱が入りやすい企画です。運動が得意でない人も応援や司会などで関わることができ、社内に軽やかな一体感や健やかな笑いを生むきっかけになります。
実施の際は服装やスペースに配慮し、転倒や周囲との接触が起きにくい環境を整えることが大切です。
スポーツスタッキング
スポーツスタッキングは、12個の専用カップを決められた形に素早く積み上げたり崩したりするスピード競技です。動きはシンプルながら、高い集中力と反射神経が求められ、観客も思わず見入ってしまう場面が生まれるかもしれません。
実施の際は、机の安定性やカップの滑り具合に配慮し、練習時間を設けて無理のない進行を心がけましょう。
スプレーアートパフォーマンス
スプレーアートパフォーマンスは、社員がスプレーを使って即興で絵を描く出し物です。音楽に合わせてダイナミックに制作が進む様子は観客を惹きつけ、ライブ感のある出し物のため会場の雰囲気を盛り上げる演出としても活用できます。
スプレーは屋外や換気の良い場所で使用し、安全対策や衣服の汚れ対策は事前に共有しておくと安心です。
成功体験コンテスト
成功体験コンテストは、社員が自身やチームの業務における成果・改善事例をプレゼンし、投票で最優秀賞などを決定する企画です。人数が多い場合は予選を設けたり、失敗体験をテーマに学びを共有したりするアレンジも可能です。
また、プレゼンを通じて成果に至るまでの背景や工夫が共有されると、部署や立場を超えて社員同士の相互理解が深まることが期待できます。日々の取り組みが社内で広く共有・評価されることで、モチベーション向上や組織全体の活性化につながることも期待できるでしょう。
【鑑賞型】社内イベントにおすすめの出し物6選

以下では、社内イベントの鑑賞型の出し物を6選紹介します。
マジックショー
マジックショーは、プロマジシャンによるマジックやイリュージョンを楽しむ鑑賞型の出し物です。間近で見る演出や参加型のマジックを取り入れることで、参加者との一体感も生まれやすくなります。非日常的な驚きや笑いを共有することで、リフレッシュにもつながるアクティビティとして活用できます。
会場の広さや照明・音響などの環境が演出に影響する可能性があるため、事前の調整が重要です。
サイエンスショー
サイエンスショーは、身近な科学現象を使った実験や演出を披露する鑑賞型出し物です。液体窒素や静電気、光の仕組みなどを使い、驚きや笑いを交えながら科学の面白さを伝える内容が多く、ファミリーデーなど子どもが参加する社内イベントにもおすすめです。
視覚的なインパクトのある知的好奇心をくすぐる時間が場の雰囲気をやわらげ、社員間の会話のきっかけになることも期待できます。
書道パフォーマンス
書道パフォーマンスは、音楽や照明の演出を加えながら即興で大きな紙に書を書く出し物です。力強い筆使いや所作の美しさが伝わり、芸術の奥深さを体感できる企画として注目されています。静と動が融合したパフォーマンスは、参加者の感性を刺激し、いつもとは違う非日常の空気を社内にもたらすきっかけとなるかもしれません。
書道には墨や水を使用するため、床や周囲の保護、飛沫への配慮が必要です。
アイドルライブ
アイドルライブは、外部のアイドルグループを招き、歌やダンスのパフォーマンスを鑑賞する出し物です。明るく華やかなステージが会場を盛り上げ、日常とは違う刺激になることが期待できます。世代や興味の違いに配慮し、複数ジャンルの出演や事前アンケートを実施するとより満足度の高いイベントになるでしょう。交流の話題づくりにもつながります。
音響設備や演出面での事前調整、観覧エリアの安全確保が必要です。
社員の1日Vlog
社員の1日Vlogは、特定の社員の1日に密着し、業務の様子や日常を動画で紹介する企画です。業務内容や働き方の違いを可視化することで、部門間の理解促進や親近感の醸成が期待されます。Vlogを通して他部署の仕事や関わったことのない社員の人柄を知ることで、社内の横のつながりを感じられる映像にもなり得ます。
また撮影は事前許可を得た上で、個人情報や社外秘情報の映り込みに十分配慮する必要があります。
社長密着映像
社長密着映像は、社長の1日に密着し、会議や移動、社内外でのやり取りなどをVlog形式で紹介する企画です。普段見えづらい業務の裏側を知ることで、社員にとっては会社の方向性や経営層の考え方への理解が深まる機会となり得ます。
また、映像は真面目さに加え、親しみやすい編集を意識することで、社内の距離感を縮めるコンテンツとして活用できます。撮影にあたってはプライバシーや機密情報への十分な配慮が必要です。
【体験型】社内イベントにおすすめの出し物9選

以下では、社内イベントにおすすめの体験型出し物を9選紹介します。
謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームは、参加者がチームを組み、制限時間内に謎を解いて脱出を目指す体験型企画です。ゲームを通して協力や会話が生まれるため、チームビルディング効果も期待でき、社員同士の関係構築や、普段とは異なる一面の発見を促すことで、チームワークの強化や相互理解を図る場として、取り入れやすい企画です。
会場の安全確保はもちろんのこと謎の難易度調整も行い、チームの様子を見ながらフォローを入れる運営面での工夫が必要となります。
⇒謎解き脱出ゲームが実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
社内運動会
社内運動会は、チーム対抗のリレーや玉入れ、大縄跳びなどの種目を取り入れ、社員同士が体を動かしながら交流できる体験型イベントです。普段は関わりの少ない社員同士が協力し合うことで、部署を越えた連携や一体感が生まれやすく、社内の雰囲気づくりやモチベーション向上にも寄与する可能性があります。
けが防止のための準備運動はもちろんのこと、年齢層や体力差を考慮して競技内容を調整し、無理のない範囲で行い、休憩時間も必ず設けましょう。
⇒社内運動会が実施できる「トータルイベントプロデュース資料」を無料で受け取る
ワークショップ
ワークショップは、外部講師を招いて手芸やキャンドルづくり、グラスガーデンなどの制作体験を行う企画です。ワークショップという共通の体験をすることで交流のきっかけにもなり、社員同士の関係性を深める場としても活用しやすいコンテンツです。また、普段の業務とは異なる創造的な体験を通じてリフレッシュにもつながるでしょう。
実施にあたって道具や素材の準備、作業スペースの確保が必要で、火や刃物を扱う場合は安全面への配慮が欠かせません。
座禅体験
座禅体験は、講師の指導のもと静かに姿勢と呼吸を整える時間を設け、心身を落ち着かせることを目的とした企画です。日常の喧騒から一歩離れ、内省の時間を持つことで、集中力の向上やストレス軽減を感じる人もいる内容でのため、業務の切り替えや、穏やかな交流のきっかけとしても活用できるのではないでしょうか。
無理のない姿勢で座れる環境や、静寂を保てる会場設定が必要となります。実施にあたって、事前に参加者の体調への配慮も欠かせません。
社内フリーマーケット
社内フリーマーケットは、社員が持ち寄った品物を出店・買取し合う参加型の企画です。普段見えない同僚の趣味に触れられることで、会話のきっかけが生まれたり、部署を越えた交流が促進されたりすることもあるでしょう。また、サスティナブルな活動としてもおすすめです。
実施にあたっては私物の管理や金銭のやり取りについて事前にルールを明確にし、場合によっては物々交換のみにするなどトラブル防止に努めることが大切です。強制参加ではなく、気軽に楽しめる雰囲気づくりもポイントとなります。
企業アーカイブVR体験会
企業アーカイブVR体験会は、創業当時のオフィスや街並みを再現した仮想空間で社員が擬似体験する企画です。映像や音声を交えることで臨場感を高め、企業の歩みや歴史に親しむきっかけとなるでしょう。新人からベテランまで、自社への理解や愛着を深める機会として活用でき、世代を越えたコミュニケーションも期待されます。
実施には十分な数のVR機材と安全なスペースの確保が必要で、時間によって違うパターンの内容を用意し、短時間の内容を体験してもらうなど酔いやすい人への配慮も求められます。
新商品・サービス体験会
新商品・サービス体験会は、現在検討中の新商品やサービスを社員に実際に体験してもらい、感想や意見をフィードバックとして集める社内イベントです。ユーザー視点の気づきを得られるだけでなく、社員が企画に関与することで当事者意識が高まる可能性があります。
体験後の意見交換やアンケートを組み合わせると、より有意義な場になるでしょう。対象や体験方法を明確にし、試作品の場合は安全面への配慮も必要です。
1日業務見学・体験会
1日業務見学・体験会は、社員が他部署の業務を実際に見学・体験することで、社内の業務理解を深めることを目的とした企画です。普段関わりの少ない業務に触れる機会をつくることで、部門間の相互理解や視野の拡大が期待され、チームワークや業務改善の糸口となる可能性もあります。
実施にあたっては、スケジュールを事前に組んでおき、対応する人を順番に回して負担が集中しないようにするなど受け入れ側の負担を軽減する工夫や、守秘情報の取り扱いに配慮しましょう。
開発ワークショップ
開発ワークショップは、商品やサービスのアイデアを社員同士で出し合い、企画のたたき台をつくる体験型の企画です。部門を超えて意見を交わすことで、多様な視点や発想が交差し、柔軟なアイデアが生まれやすくなります。社内の創造性を引き出し、開発への当事者意識を高める場としても活用できます。
実施にあたっては、参加者の経験や職種による知識差を意識し、進行役がサポートしながら進めることが重要です。
【展示型】社内イベントにおすすめの出し物7選

ここからは、社内イベントにおすすめの展示型出し物を7選紹介します。
会社の歴史ボード展示
会社の歴史ボード展示は、創業から現在に至るまでの歩みを写真や年表、当時の資料などを用いて紹介する企画です。社史に触れる機会が少ない社員にも、企業の成り立ちや価値観を伝えることができ、帰属意識の醸成につながる可能性があります。
展示内容は事実に基づいて制作しましょう。実施にあたってはスペースや動線を考慮し、業務の妨げにならないよう配置することで、気軽に立ち寄れる場づくりが期待できます。
商品・サービスの変遷展示
商品・サービスの変遷展示は、これまでに手がけてきた商品やサービスの変化を、年代順やテーマ別に紹介する展示企画です。製品の進化や開発の背景に触れることで、社員に自社の強みや価値観を再認識してもらうきっかけになります。
また、視覚的にわかりやすく構成することで、多くの社員が立ち寄りやすくなり、社内コミュニケーション活性化にもつながります。
歴代の社内広報誌展示
歴代の社内広報誌展示は、これまでに発行された社内報を並べて紹介する展示企画です。過去の記事やデザイン、当時の社内トピックスなどを振り返ることで、会社の歩みや変化を身近に感じられる場になります。
また、共通の話題が生まれることで世代や部署を越えた交流の促進にもつながる可能性があります。
社員インタビュー展示
社員インタビュー展示は、社内のさまざまな社員へのインタビュー内容をパネルや映像で紹介する企画です。仕事内容ややりがい、個人のエピソードなどを通じて、普段見えにくい一人ひとりの魅力や考え方を伝えることができます。
実施にあたっては、内容の事前確認や掲載可否の同意を取ることが不可欠です。
部署紹介展示
部署紹介展示は、各部署の業務内容や役割、取り組みを紹介するブースによって、社員同士の理解を深める企画です。写真や資料、動画などを使って視覚的に伝えることで、普段関わりの少ない部署の仕事にも関心を持つきっかけになります。
また、部署の役割や業務内容・流れを知ることで相手の立場を理解できるきっかけになるため、社内の連携や協力意識の促進につながる効果が期待できます。
社員の趣味・特技ギャラリー
社員の趣味・特技ギャラリーは、写真、イラスト、手芸、書道など、社員の個性あふれる作品を展示する企画です。社員同士の新たな一面を知る機会となり、会話のきっかけや社内のつながりを生む場として活用できます。
また、職場以外の一面に触れることで心理的距離が縮まることで職場の雰囲気がやわらぎ、互いへの理解や尊重を促進する効果が期待できます。
社内フォトコンテスト
社内フォトコンテストは、社員が社内や出張先などで撮影した写真を集めて展示し、投票やコメントで楽しむ参加型の企画です。日常の中で見過ごしがちな風景や瞬間を共有することで、職場への愛着や社員同士の理解が深まり、社内コミュニケーションの活性化にもつながる可能性があります。
また、人物が写る場合は事前の許可を得るなど、プライバシーや掲載範囲に配慮しましょう。
【表彰型】社内イベントにおすすめの出し物7選

以下では、社内イベントにおすすめの表彰型出し物を7選紹介します。
ベストサポーター賞
ベストサポーター賞は、チームや後輩、上司、他部署などを陰ながら支えてくれた個人やチーム讃える称える表彰企画です。業績では見えづらい貢献にスポットを当てることで、可視化されづらい貢献や協力する姿勢にスポットを当てる機会となり、一人ひとりを認め合う文化づくりにつながることが期待できます。
また、表彰を通じて組織全体に温かい雰囲気が生まれ、日頃の連携への意識向上も期待できるでしょう。
ベストチャレンジ賞
ベストチャレンジ賞は、前例にとらわれない発想で新しいアイデアを提案した人や、未知の取り組みに積極的に挑戦した社員を称える表彰企画です。挑戦の過程や姿勢に注目することで、挑戦を歓迎する社風の醸成や、社員同士の刺激や学びにもつながる効果が期待されます。
選考にあたっては、チャレンジの背景や影響を公平に捉える基準を設けるとよいでしょう。
プロジェクト推進賞
プロジェクト推進賞は、一定期間内にプロジェクトをやり遂げたチームを表彰する企画です。業務への誇りや仲間意識の醸成につながり、次の挑戦への意欲を引き出す効果も期待されます。成果だけでなく、プロセスやチームワーク、困難への対応なども評価対象とすることで、公平性や納得感を高める工夫が求められます。
ベストリアクション賞
ベストリアクション賞は、業務中のやりとりやイベント時に、周囲を盛り上げる反応を見せてくれた社員を称える表彰企画です。リアクションの大きさだけでなく、場の空気を和らげたり、発表者への共感を示したりと、周囲への良い影響を重視することで、職場全体の雰囲気づくりや発信しやすい空気の醸成にもつながることが期待できます。
技術習得者賞
技術習得者賞は、資格の取得やスキルアップに継続的に取り組んだ社員を称える表彰企画です。業務に直結する技術だけでなく自主的な学びや挑戦も対象にすることで、努力する姿勢や挑戦を称える文化を可視化することも可能になり、学習意欲や社内の成長志向を刺激する効果が期待できます。
選考にあたって評価基準は事前に明示し、期間や成果の定義を明確にすると公平性が保てます。
ベストティーチャー賞
ベストティーチャー賞は、社内での育成や指導に尽力した社員を表彰する企画です。後輩の成長を支えたり、チームの学びを促進したりする姿勢を称えることで、日頃の貢献が可視化されます。評価は育成対象者の声や具体的なエピソードを参考に行うとよいでしょう。
地道な支えに光を当てる機会としても有効で、育成文化の醸成や、教えることへのモチベーション向上が期待できる表彰です。
ベストヘルスケア賞
ベストヘルスケア賞は、一定期間の睡眠時間や歩数などの健康管理状況を集計し、チームや個人の取り組みを表彰する企画です。健康意識の向上や、チームで取り組むきっかけづくりにもつながり、職場全体のウェルビーイング向上が期待できます。
選考にあたって、年齢やライフスタイルに応じた基準を設けることで、公平性のある評価が可能になるでしょう。また、参加者のプライバシーに配慮し、データの取扱いに注意し、関係者のみが閲覧できる状態にしておくと安心です。
まとめ
ここまで、社内イベントにおすすめの出し物を実演型・鑑賞型・表彰型などに分けて紹介しました。いずれの企画も、目的や参加者の特性に応じて工夫を加えることで、より効果的なイベント演出が可能になります。実施の際は、安全面や運営体制に十分配慮し、参加者が安心して楽しめる環境を整えましょう。ぜひ本記事を、周年記念イベントの企画立案にご活用ください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る