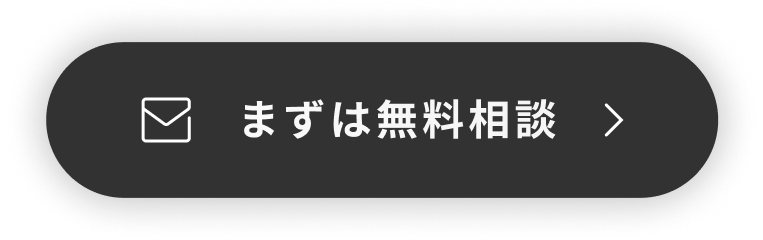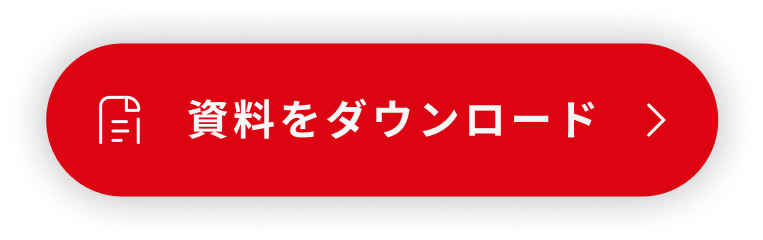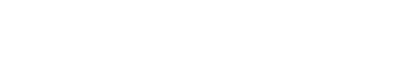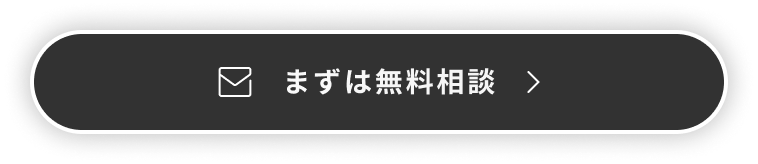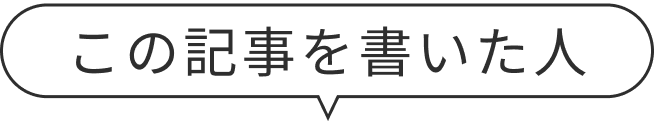懇親会が盛り上がる余興30選
- 幹事お役立ち情報
更新日:2025年9月2日



目次
懇親会とは、参加者同士が飲食や会話を通じて交流し、親睦を深めることを目的に行われる集まりです。関係を深めることで、理解や協力を促進することが期待できるでしょう。
本記事では、懇親会が盛り上がる余興を大人数・実演型・少人数など6つに分類し、計30選紹介します。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る
【大人数】懇親会が盛り上がる余興9選

ここからは、懇親会が盛り上がる大人数でできる余興を9選紹介します。
ビンゴゲーム
ビンゴゲームは、参加者に配られたビンゴカードのうち、司会者が番号を読み上げた番号のマスを埋めていくゲームです。マスが埋まっていく期待感や高揚感を他の人と共有することで盛り上がりやすくり、緊張を和らげて、会場の空気を活性化させる効果も期待できます。
また、コミュニケーションの促進や場の雰囲気づくりにも作用すると考えられるでしょう。
バースデーチェーン(バースデーライン)
バースデーチェーンは、参加者全員が言葉を使わず、誕生日(月と日)順に並ぶゲームです。開始の合図で静かにスタートし、ジェスチャーや身振り手振りで誕生日を教え合いながら列を作っていき、最後に答え合わせをして、正誤を確認します。
制限時間を設けることで緊張感が高まり、緊張と緩和の効果で距離が縮まりやすくなるでしょう。また言葉を使わないため、他の人の意図を汲み取ったり・きちんと伝えたりする工夫が必要になり、コミュニケーション力が養われる効果も期待できます。
ジェスチャーゲーム
ジェスチャーゲームは、言葉を使わず身振りのみでお題を伝え、他の参加者がお題を当てるゲームです。まず、お題を書いたカードを準備し、順番に1人ずつジェスチャーで表現します。他の人は制限時間内に答えを推測して声に出して伝えます。
出題者は声を使わない分、表情や身振りで感情を伝える必要があるため、非言語コミュニケーション力が培われる機会にもなるでしょう。
借り物・借り人競争
借り物・借り人競争は、司会が指定する「条件に合う物や人」を参加者が探して持ってくる・連れてくるゲームです。クリアした速さを競うため、競争心が刺激されて盛り上がりやすく、普段関わりの少ない人との交流を活性化させる効果が期待できます。
また、チーム対抗戦で行うことで協力や声かけを通じて場の雰囲気が活発になりやすく、コミュニケーションを促進したい場面でも効果的なゲームでしょう。
テーブルボール転がし
テーブルボール転がしは、テーブルの向こう側に点数を書いた箱を置き、参加者は箱を狙ってテーブルの上にボールを転がし、得点を競うゲームです。制限時間内に合計得点を争う形式が主流で、チーム対抗戦にすることで声をかけ合う場面が増え、懇親会の場を盛り上げる手段として特に適しています。
また、コミュニケーションが活性化したすいだけでなく、空間認識力や戦略性を引き出す効果も期待できるでしょう。
イントロドン
イントロドンは短い音楽の冒頭を聴いて曲名やアーティストを当てる音楽クイズです。司会がイントロを再生し、参加者は早押しや挙手制で回答を競います。世代を問わず親しみ深い曲を題材にしたり、世代を満遍なく網羅した選曲にしたりすることで、幅広い年代の参加者に楽しんでもらいやすいでしょう。
互いの回答を聞いて会話のきっかけが増えたり、好みを知って親近感を抱いたりするきっかけになるかもしれません。
NGワードゲーム
NGワードゲームは、事前に定めたNGワードを記載したカードをランダムで配布し、回ってきたカードを自分のNGワードとして見ないように額などに貼り、周囲から見えるようにします。自分のNGワードを言わないよう、周囲の反応から推理して回避しつつ、他の参加者がNGワードを言うように誘導する戦略が必要なゲームです。
推理や心理戦の要素と会話で展開していくゲームのため、笑いが生まれやすく場のコミュニケーションが活発になるでしょう。またゲームを通じて、普段関わりが少ない人との交流を促す効果も期待できます。
オリジナルすごろくゲーム
オリジナルすごろくゲームは、マスに書き込まれた指令をクリアして進行する懇親会向けの余興です。たとえば「好きな食べ物」「人生で一番緊張した場面」「一番近くのマスにいる人に伝えたいこと」といったエピソードトークを交えながら進行していきます。
参加者同士で人柄や経験を知るきっかけが生まれやすく、ゲームを発端に会話が広がれば、交流を深める効果も期待できるでしょう。
ミッションビンゴゲーム
ミッションビンゴゲームは、通常のビンゴに交流を促す課題を組み合わせた余興です。たとえば「柄物の靴下を履いた人と写真を撮る」「他部署の人と名刺交換をする」などといったマスを設定し、証拠として写真や物の交換で達成を確認します。実施の際は、マスをクリアしたことが分かる課題を設定するのがおすすめです。
ゲームを通じて多くの人と関わるきっかけが生まれ、交流が広がることが期待できます。
【実演型】懇親会が盛り上がる余興5選

以下では、懇親会が盛り上がる実演型の余興を5選紹介します。
二人羽織
2人羽織は、1人が羽織を着て顔だけを出し、背後のもう1人が後ろから腕を回し、前の人の手となって動作を行う余興です。後ろの人は見えない状態で食事やメイクなどの課題に挑戦します。実演する人は息を合わせて進める必要があるため協調性が求められるでしょう。
ピクトグラム再現パフォーマンス
ピクトグラムとは、文字を読めない人や年齢・国籍に関わらず、多くの人が直感的に理解できる絵やマークのことです。ピクトグラム再現パフォーマンスでは、身近な状況などを人間の動きで再現します。視覚的に笑いを誘いやすく、直感的に理解できるため場が明るくなることが期待できるでしょう。
たとえば社内でよくある一コマを題材に選び、参加者が体を使ってピクトグラムの形を演じると、笑いを誘いやすく、コミュニケーションのきっかけにもなり得ます。
プレゼンテーション
プレゼンテーションは、業務改善案や福利厚生案などをテーマに、参加者が自らの考えをプレゼンする企画です。業務に役立つ提案を共有できるだけでなく、発表者の思考や価値観を知る機会となり、聞いている人の刺激にもなれば、業務上においてより良い相乗効果が見込める可能性もあります。
実施する際は、主催側が事前に内容を確認・検討したうえで発表するのがいいでしょう。また人数が多い場合は、予選を設け、懇親会当日には最終選考のみを行う形式も可能です。
失敗体験コンテスト
失敗体験コンテストは、社員が個人やチームの業務で起こった失敗と失敗から導き出した改善事例をプレゼンする企画です。参加者が失敗体験・改善事例を発表し、参加者の投票で最優秀賞などを決定します。
失敗体験を共有されることで単なる余興に留まらず、失敗した時のマインドの保ち方を学ぶことにつながったり、社員同士が課題解決への姿勢を理解したりするきっかけになり得ます。
似顔絵パフォーマンス
似顔絵パフォーマンスは、参加者から希望を募り、即興で似顔絵を描き上げる企画です。ステージなどで描く様子を公開し、完成した作品を披露するといった流れで実施します。完成作品を共有することで話題のきっかけが生まれることが期待できるでしょう。
【少人数】懇親会が盛り上がる余興6選

ワードウルフゲーム
ワードウルフゲームは、参加者のうち多数派と異なるワードを割り当てられた人を探し出すゲームです。それぞれが自分のお題について話したり、周囲とやり取りしたりする中で覚えた発言の違和感や、反応をもとに投票で少数派のワードを与えられたウルフを決定します。
会話を通じて洞察力や表現力が養われやすく、少人数の会話で進行するため関わりが深まりやすい点でおすすめです。
以下の動画でも詳しく紹介しています。
カウントアップゲーム
カウントアップゲームは、順番に数字を言っていき、あらかじめNGと決められた数字を言ってしまった人が負けるゲームです。たとえばNGの数字が30の場合、1から順に、最大でも3つまでの数字を順に発言し、最後30と言わなくてはならなくなった人が負けます。
思考力や戦略が必要で緊張感が漂うゲームですが、少人数で行えるため交流を深める機会になるでしょう。
共通点ゲーム
共通点ゲームは、グループ内で互いに会話をしながら共通の特徴や経験を多く探し出すゲームです。たとえば「好きな食べ物」「旅行先」「趣味」などをテーマにして発見した共通点を発表し合います。短時間で相手のことが知れるため交流を深めやすく、普段の業務では知り得ない相手の一面を知るきっかけになるでしょう。
また、雑談に似た内容で気軽に盛り上がりながら相互理解が進むことが期待でき、信頼関係を築く助けにもなり得る企画です。
ヒット&ブロー
ヒット&ブローは相手が設定した数字の並びを当てるゲームです。参加者は順番に数字を予想し、位置と数が合えばヒット、数のみ合えばブローとして判定します(579を設定して、739と言われた場合は、1ヒット1ブロー)。
論理的思考やひらめきを活かしながら展開されるため、チームで意見を交わす過程で交流を深めることができるでしょう。また、駆け引きや戦略を楽しむことで、活気が生まれるため場を活性化したい時にもおすすめです。
子ども時代の写真あてゲーム
子ども時代の写真あてゲームは、参加者の幼少期の写真を用意し、誰の写真かを当てる企画です。写真を順に提示し、参加者が推理して答えていきます。答えを明かす際にエピソードを交えたり成長の変化が話題となったり、普段知ることのない人柄に触れることで、互いの距離を縮めることができるでしょう。
また、親近感や愛着を生む効果も期待できます。
ロゴ描きゲーム
ロゴ描きゲームは、有名な会社やブランドのロゴを、記憶を頼りに描く余興です。進行役がお題(会社名、ブランド名)を提示し、参加者は制限時間内に紙やホワイトボードに描きます。その後、実際のロゴと見比べて完成度を評価します。
身近なロゴや全世代に伝わる会社やブランドを題材にすることで誰でも参加しやすくなるでしょう。
【相互理解】懇親会が盛り上がる余興3選

ここからは、相互理解が促進され、懇親会が盛り上がる余興3選を紹介します。
私は誰でしょう
「私は誰でしょう」は、人や物の特徴について「私は〜です」と説明を重ね、最後に「私は誰でしょう」と問いかけて答えを当ててもらう余興です。出題者は段階的にヒントを出し、回答者は推理しながら答えます。お題となる人物を社員に絞ることで相互理解を深められ、話題の広がりや交流のきっかけを生み出せるでしょう。
人生グラフ(モチベーショングラフ)
人生グラフは、参加者が自身の人生をグラフ化し、転機となった出来事やその時感じたことを共有する企画です。これまでの経験を共有し合うことを通じて、互いの価値観や背景を理解するきっかけになることが期待できます。
業務上では知り得ない過去の話や見えにくい人柄、考え方に触れられるため、交流が深まったり相互理解が促されたりするでしょう。
自分クイズ
自分クイズは、参加者それぞれが自分に関する3択クイズを出題し、参加者に回答してもらう形式のゲームです。身近なエピソードを題材にした問題を通じて、互いの意外な一面を知ることができ、会話のきっかけが広がるでしょう。
1人ずつ出題することで個人について理解する流れが生まれやすく、参加者同士の関係性を築く効果が期待できます。
【体を動かす】懇親会が盛り上がる余興4選
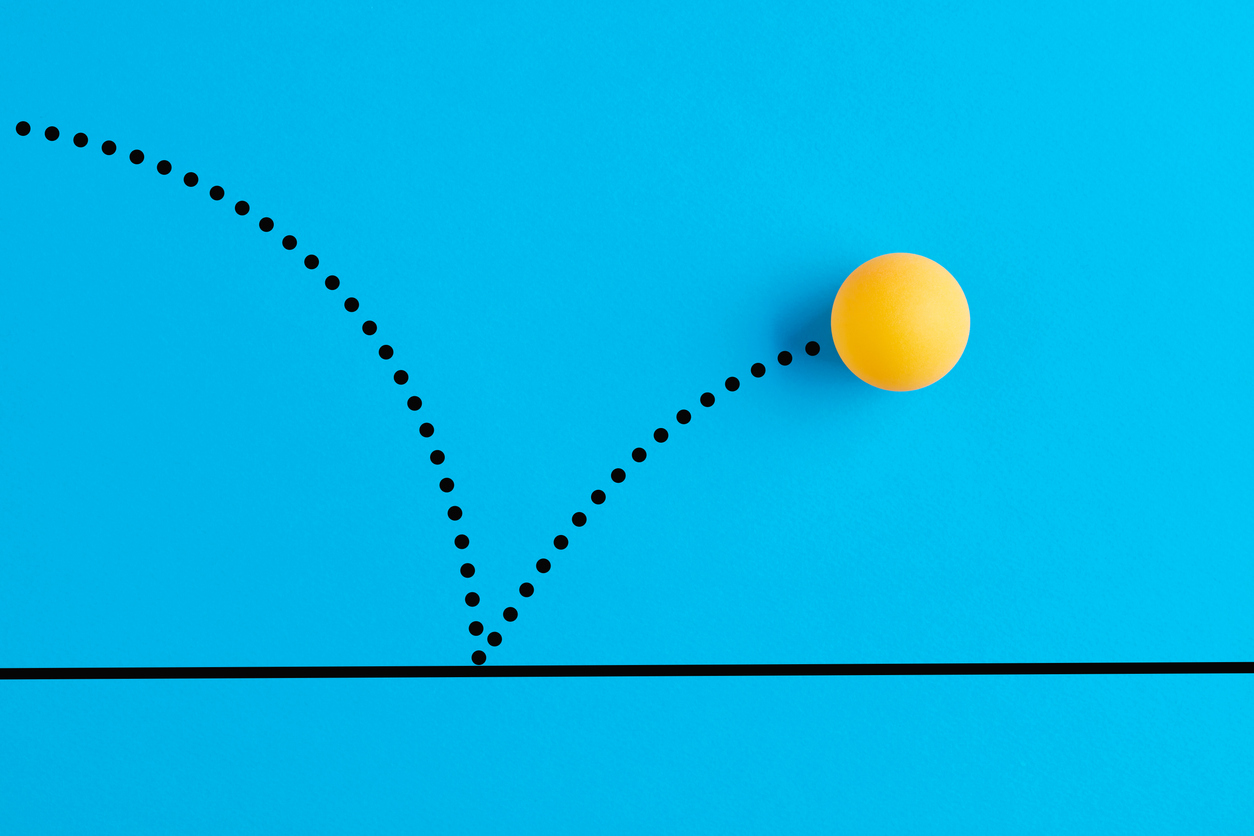
以下では、懇親会が盛り上がる体を動かす余興を4選紹介します。
フープくぐりリレー
フープくぐりリレーは、チーム全員で手をつないだままフラフープに体をくぐらせ、次の人へと送っていくリレー形式のゲームです。フープを通し終える速さを競うため、人の動きをきちんとみて、互いがフープを通しやすいように配慮したりする必要があります。
息を合わせて取り組むことで相互理解が深まり、メンバー同士の距離を縮める効果が期待できるでしょう。
大縄跳び
大縄跳びは、大きな縄を2人が回し、残りの参加者がリズムを合わせて連続で縄に入り、全員で跳び続けるゲームです。時間内に全員で何回跳べるかを競う形式や、順番に1人ずつ飛んで抜けてを繰り返した数を競う形式があります。
縄の動きを見極めて呼吸を揃えたり、飛びにくい人に合わせて気を配ったりする必要があるため、集中力と協調性、チームワークの向上が期待できるでしょう。
模写リレー
模写リレーは、持ち場から離れた位置に設置されたお題のイラストを確認しながら、模写を描き進めるゲームです。たとえば、参加者全員で1枚の絵を完成させる方式や、マスを設けて複数の絵を用意し、正確に描けたマスの数のみ加点する方式があります。
観察力と記憶力に加え、役割を引き継ぐ連携が求められるため、協力体制を築く効果が期待できます。
ピンポン球リレー
ピンポン球リレーは、スプーンやお玉にピンポン球を乗せて運び、次の人へつなぐリレー形式の競技です。落とさずにゴールまで届ける速さをチーム同士で競います。バランス感覚と集中力が求められるため、緊張と緩和が生まれ盛り上がりやすいでしょう。
また、成功させるために声を掛け合う流れが協力意識を高め、チームワークを深めるきっかけにつながることが期待できます。
【映像系】懇親会が盛り上がる余興3選

以下では、懇親会が盛り上がる映像系の余興を3選紹介します。
社員インタビュー映像
社員インタビュー映像は、異なる部署や世代の社員同士が対談やインタビューを行った映像を上映する企画です。普段の業務では見えにくい価値観やエピソードが語られることで、親近感が湧きやすく、ひいては会社に対する愛着として機能する可能性も高いでしょう。
また多様な視点に触れる機会を提供することで刺激を与え、組織全体のつながりを強める効果が期待できます。
社員の1日Vlog
社員の1日Vlogは、特定の社員に密着し、業務の様子や日常の過ごし方を動画で紹介する企画です。映像を通してさまざまな働き方や社員の人柄を発信することで、社内に届きにくい自社の取り組みやどんな人が働いているのかを伝えるコンテンツとして効果が期待できます。
家族からのコメント映像上映
家族からのコメント映像上映は、社員の家族に協力を依頼し、感謝や励ましのメッセージを収録した映像を流す企画です。普段は聞くことの少ない家族の思いが伝わることで、本人にとって特別で嬉しい体験となるのではないでしょうか。
加えて、社員が互いの背景を知ることで親近感を生み、関係を深めたり、円滑にしたりする効果が期待できます。
まとめ
懇親会とは、参加者同士が飲食や会話を通じて交流し、親睦を深めることを目的に行われる集まりのことです。懇親会で余興を行うことで、より関係の深化を図ることができるでしょう。
ここまで、懇親会が盛り上がる余興を大人数・実演型・少人数など6つに分類し、計30選紹介しました。実施の際は、会場の規模や参加者を踏まえながら計画するのがおすすめです。ぜひ本記事を、懇親会が盛り上がる余興の企画する際にご活用ください。
⇒年間1300件の実績、100種以上のサービスで支援!「トータルイベントプロデュース」の資料を受け取る